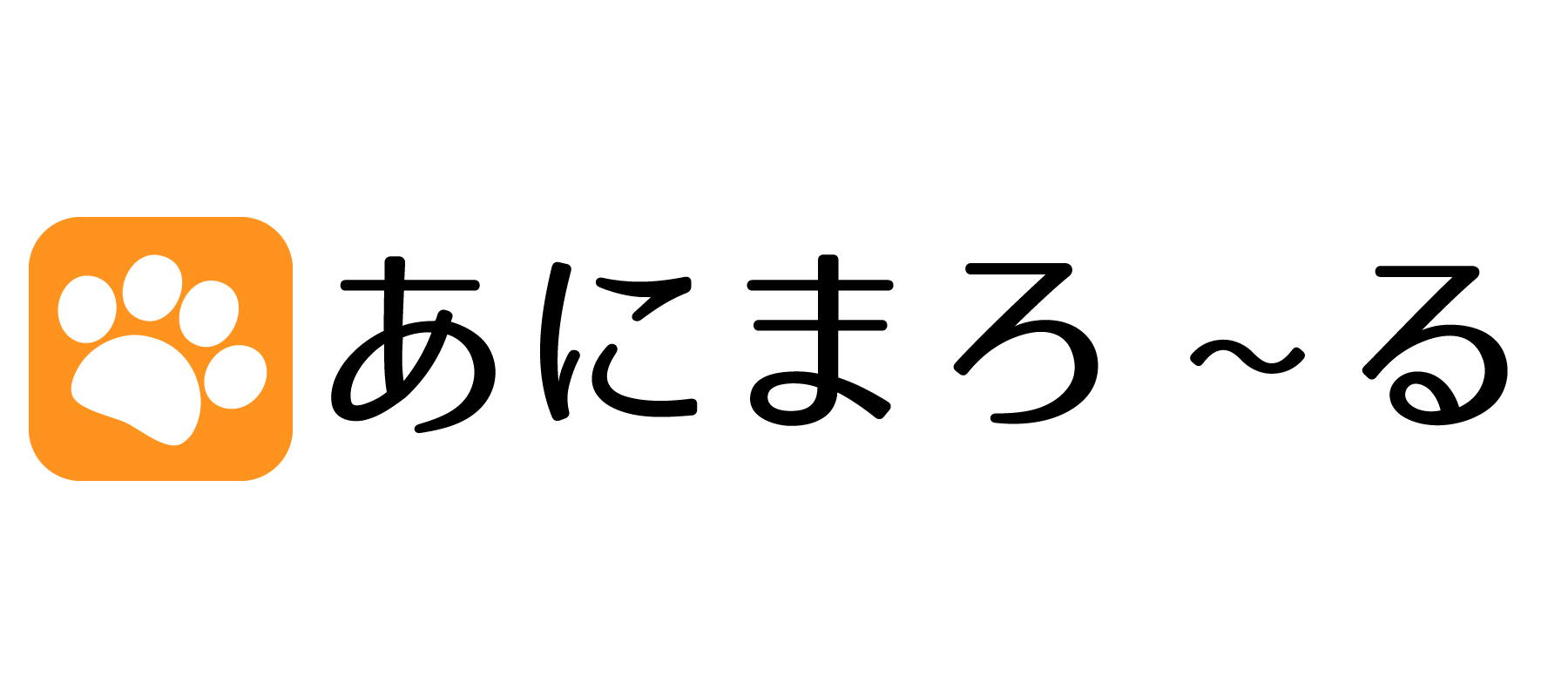意外と知らない犬の豆知識13選|犬好き必見の犬の生態における秘密
更新日:2024年03月28日

犬の習性・生態
賢くて従順で可愛らしいので、飼うなら絶対犬だという方も多いでしょう。
そんな犬と暮らしていく上で、犬の習性や生態をしっかりと押さえておくことはとても重要です。雑学と言われればそれまでですが、間違った飼い方をしたりトラブルを回避するためにも、犬の基本的なことをきちんと知っておくと安心です。
この記事では犬の習性や生態などについて、もともと野生の時から持っているものから、飼う上で特に気をつけるべきのものまで豆知識として13個ご紹介していきます。
そんな犬と暮らしていく上で、犬の習性や生態をしっかりと押さえておくことはとても重要です。雑学と言われればそれまでですが、間違った飼い方をしたりトラブルを回避するためにも、犬の基本的なことをきちんと知っておくと安心です。
この記事では犬の習性や生態などについて、もともと野生の時から持っているものから、飼う上で特に気をつけるべきのものまで豆知識として13個ご紹介していきます。
犬の豆知識13選とは?
ここでは、犬の習性や生態についての豆知識をご紹介します。
嗅覚が人間の100万倍という話は聞いたことのある方も多いでしょうが、味覚は未発達です。また、実は猫舌なので熱いものが食べられません。事前に分かっていれば食事を与える際も安心ですね。
犬に関する知識を知っているか知らないかで、犬との生活のしやすさが大きく変わります。既に犬を飼っている人もこれからの人もみんな豆知識を押さえておきましょう。
嗅覚が人間の100万倍という話は聞いたことのある方も多いでしょうが、味覚は未発達です。また、実は猫舌なので熱いものが食べられません。事前に分かっていれば食事を与える際も安心ですね。
犬に関する知識を知っているか知らないかで、犬との生活のしやすさが大きく変わります。既に犬を飼っている人もこれからの人もみんな豆知識を押さえておきましょう。
犬は人間の100万倍の嗅覚をもっている=人間より100万倍強く濃く匂いを感じているということではないのです。
出典: http://www.dogclover.com/2017/08/24/%E7%8A%AC%E3%81%AE%E5... |
イヌ達は、逆にその匂いが100万分の1の匂いになってもかぎ分けることができる嗅覚を持っているのです。
人間には感じ取ることができないほどの匂いもかぎ分けられるのだそうです。
犬に関する豆知識
- 実は猫舌
- 嗅覚は人間の100万倍
- 味覚は未発達
- ギネス登録される犬
- 世界の犬に関する規則
- 舌で体温調節する
- 胃腸が強い
- あくびは眠さからではない
- 肉球の秘密
- 常につま先立ち
- 鼻のしわが指紋替わり
- 血液型が13種類
犬の豆知識1:実は猫舌
飼っていくために重要な豆知識ですが、犬は実は猫舌です。猫が猫舌なのは有名ですが、実は猫に限らず犬を含めてほとんどの動物たちは熱いものが苦手です。
野生の動物たちは自然界の獲物を生のまま食べていました。体温以上の獲物は自然界には存在しないので、多くの動物は熱さに対する免疫がありません。
犬の食事を手作りしてあげる方も多くいますが、作ってすぐにあげてしまうと舌を火傷して舌炎という病気を発症する可能性もあります。食事は冷ましてから、もしくは人肌くらいの温度を目安にしてあげましょう。
野生の動物たちは自然界の獲物を生のまま食べていました。体温以上の獲物は自然界には存在しないので、多くの動物は熱さに対する免疫がありません。
犬の食事を手作りしてあげる方も多くいますが、作ってすぐにあげてしまうと舌を火傷して舌炎という病気を発症する可能性もあります。食事は冷ましてから、もしくは人肌くらいの温度を目安にしてあげましょう。
犬の豆知識2:嗅覚は人間の100万倍
犬の嗅覚は人間よりも何倍もすごいと言われていますが、実際、人間の100万倍の嗅覚を持っています。これは比較的よく知られた豆知識です。
実は匂いの種類によって感知できる倍率が異なります。犬が最も好み、敏感に感じ取れる匂いは「酸臭」という人間の汗の匂いに含まれている酸っぱい匂いで、この匂いだと人間の1億倍感知できます。
犬の嗅覚は、その能力を生かしてさまざまな場面で役立っています。たとえば警察犬だと、犯人の匂いを嗅ぎながら追跡していき、犯人のいる位置を特定することもできます。
実は匂いの種類によって感知できる倍率が異なります。犬が最も好み、敏感に感じ取れる匂いは「酸臭」という人間の汗の匂いに含まれている酸っぱい匂いで、この匂いだと人間の1億倍感知できます。
犬の嗅覚は、その能力を生かしてさまざまな場面で役立っています。たとえば警察犬だと、犯人の匂いを嗅ぎながら追跡していき、犯人のいる位置を特定することもできます。
犬の豆知識3:味覚は未発達
犬は嗅覚が非常に発達しているのに対して、実は味覚は未発達です。犬の舌にある味覚細胞は人間の6分の1しかないので、人間の6分の1程度しか味を感じることができません。
また、感じることのできる味覚も限られていて、食べ物の旨味はほとんど感じることができないと言われています。そのため、毎日ドッグフードでも特に飽きることなく食べられます。
もともと、野生の犬は毎日が生きるか死ぬかのサバイバルです。次いつ食べられるか分からないことから、目の前にある食べ物は味を気にせず食べるという習性に基づいています。
また、感じることのできる味覚も限られていて、食べ物の旨味はほとんど感じることができないと言われています。そのため、毎日ドッグフードでも特に飽きることなく食べられます。
もともと、野生の犬は毎日が生きるか死ぬかのサバイバルです。次いつ食べられるか分からないことから、目の前にある食べ物は味を気にせず食べるという習性に基づいています。
犬の豆知識4:ギネス登録される犬
犬の中にはギネスに認定されて登録される犬もいます。
世界最高齢の犬は1910年~1939年の間生きていたオーストラリアン・キャトル・ドッグという牧羊犬で、29歳5か月と犬の平均年齢の2倍以上生きました。
世界最小の犬は「ミリー」というチワワで体の大きさが9.65センチとマグカップ程度しかありません。また、世界最大の犬は「ハーヴェイ」というグレートデンで、肩までの体高が1.54mもあります。
最も長く泳いだ犬や最も高くジャンプした犬などもギネスに登録されています。トリビアとして話のネタにもなりますね。
世界最高齢の犬は1910年~1939年の間生きていたオーストラリアン・キャトル・ドッグという牧羊犬で、29歳5か月と犬の平均年齢の2倍以上生きました。
世界最小の犬は「ミリー」というチワワで体の大きさが9.65センチとマグカップ程度しかありません。また、世界最大の犬は「ハーヴェイ」というグレートデンで、肩までの体高が1.54mもあります。
最も長く泳いだ犬や最も高くジャンプした犬などもギネスに登録されています。トリビアとして話のネタにもなりますね。
犬の豆知識5:世界の犬に関する規則
日本に比べてイギリスやドイツでは犬と人間がしっかりと共存しています。また、きちんと共存できるように法律や規則が存在するのです。
まず、ドイツでは犬の殺処分が禁止されています。飼い主がいない犬は「ティアハイム」という民間の動物シェルターに保護され、引き取り手が見つかれば新たな家族の元へ行きますが、見つからなければ無期限でそこで生活することができます。
また、大人の半額の料金で公共交通機関に同乗することができます。イギリスでも飼う上での規定が存在し、飼い主がきちんと責任を持って飼えるようになっています。
まず、ドイツでは犬の殺処分が禁止されています。飼い主がいない犬は「ティアハイム」という民間の動物シェルターに保護され、引き取り手が見つかれば新たな家族の元へ行きますが、見つからなければ無期限でそこで生活することができます。
また、大人の半額の料金で公共交通機関に同乗することができます。イギリスでも飼う上での規定が存在し、飼い主がきちんと責任を持って飼えるようになっています。
犬の豆知識6:舌で体温調節する
初回公開日:2020年03月02日
記載されている内容は2020年03月02日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。