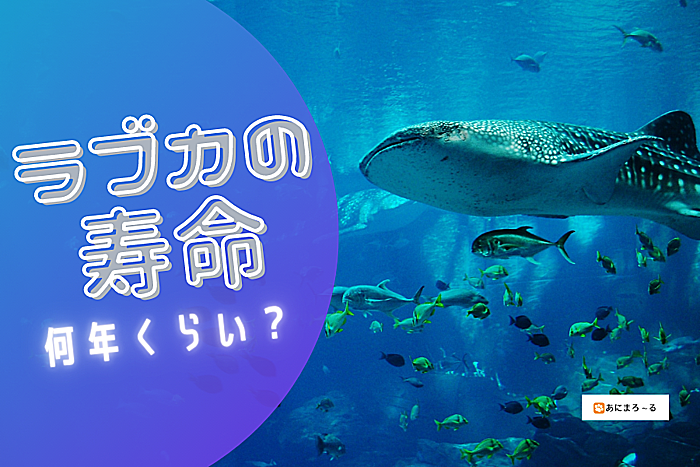「ラブカって魚は本当にサメなの?」
「生きた化石と呼ばれているラブカの生態は?」
「ラブカの寿命はどれくらいなの?」
このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
ラブカという魚は深海に生息しているサメの仲間ですが、このようなタイプのサメについて気になっていることはありませんか。
この記事では、ラブカの寿命や生態、さらには生きた化石といわれている所以などについて紹介しています。
本記事を読むことで、ラブカという珍しい深海魚の寿命に関する情報や生態、さらにはなぜ生きた化石といわれているのかを理解できるようになります。
ラブカの寿命や生態などについて気になっている方は、この記事をぜひチェックしてみてください。
「生きた化石と呼ばれているラブカの生態は?」
「ラブカの寿命はどれくらいなの?」
このような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。
ラブカという魚は深海に生息しているサメの仲間ですが、このようなタイプのサメについて気になっていることはありませんか。
この記事では、ラブカの寿命や生態、さらには生きた化石といわれている所以などについて紹介しています。
本記事を読むことで、ラブカという珍しい深海魚の寿命に関する情報や生態、さらにはなぜ生きた化石といわれているのかを理解できるようになります。
ラブカの寿命や生態などについて気になっている方は、この記事をぜひチェックしてみてください。
見た目が印象的なラブカの生態
ラブカかわいかった!らぶ!!! pic.twitter.com/vvV373tYxe
— nonoka@京都 (@mtnonnon113) August 23, 2022
近年、新聞やニュース、バラエティ番組などで取り上げられることが多くなっているのがこの深海魚「ラブカ」です。サメの仲間なのに他のサメとは一線を画す外見をしていること、そして原始的な特徴を残した「生きた化石」としても有名なサメです。
その独特な見た目から、ときには創作のモデルにされることもありますが、ラブカの寿命や生態については数多くの謎が残されていて、現在も研究や調査が進められているところです。ここでは、ラブカの生態について紹介します。
生息地
ラブカは、太平洋をはじめ、アフリカ中部西岸やノルウェー北部などの水深およそ120mから1,500mの海域に生息しています。中でも水深およそ500mから1,200mの海域に多く見られます。
日本では、千葉県の外海域、相模湾、八丈島周辺、駿河湾、紀伊水道の外海域、九州南部、沖縄にある舟状海盆南部に生息しています。これらの海域では捕獲されることもあり、地域によっては刺身などにして食べることもあります。
まれに水深100mより浅いところで目撃・捕獲されることがありますが、これについては謎も多く、さまざまな説が存在しています。
日本では、千葉県の外海域、相模湾、八丈島周辺、駿河湾、紀伊水道の外海域、九州南部、沖縄にある舟状海盆南部に生息しています。これらの海域では捕獲されることもあり、地域によっては刺身などにして食べることもあります。
まれに水深100mより浅いところで目撃・捕獲されることがありますが、これについては謎も多く、さまざまな説が存在しています。
体の大きさや特徴
ラブカは成体になると体長が最大で約2mになります。サメの仲間としては一般的な体の大きさですが、ラブカの特異な点はその体の特徴にあります。
まずラブカがほかの大半のサメと異なる点として、「口の位置」が挙げられます。一般的なサメの仲間は口が顔の下部についていることが多いのですが、ラブカの口はまるでウナギの仲間のように顔の先端についているのが特徴です。これは原始的なサメである「クラドセラケ」と共通する特徴でもあります。
次の特徴として、歯の形が挙げられます。ラブカの歯は1つの歯に3本程度の内向きに曲がった牙があるため、まるで矛のように見えます。
また、エラの形状や本数も独特です。ラブカのエラは、赤い部分(鰓弁)が飛び出していてフリルのような形状となっており、このことからも英名は「フリルドシャーク」となっています。エラの本数も、一般的なサメは5対なのに対し、ラブカは6対となっています。
まずラブカがほかの大半のサメと異なる点として、「口の位置」が挙げられます。一般的なサメの仲間は口が顔の下部についていることが多いのですが、ラブカの口はまるでウナギの仲間のように顔の先端についているのが特徴です。これは原始的なサメである「クラドセラケ」と共通する特徴でもあります。
次の特徴として、歯の形が挙げられます。ラブカの歯は1つの歯に3本程度の内向きに曲がった牙があるため、まるで矛のように見えます。
また、エラの形状や本数も独特です。ラブカのエラは、赤い部分(鰓弁)が飛び出していてフリルのような形状となっており、このことからも英名は「フリルドシャーク」となっています。エラの本数も、一般的なサメは5対なのに対し、ラブカは6対となっています。
食べるもの
ラブカが主食としているのは、主に深海にいるイカ・タコの仲間です。イカやタコを捕獲するには、引きはがすための顎の力や嚙み切るための歯の切れ味が必要となりますが、ラブカには顎の力も歯の切れ味もありません。
しかしここで活きるのが、その特徴的な歯の形状です。内向きに曲がった無数のトゲ状の歯が釣り針の「カエシ」のような役割を果たしていて、ガッチリと獲物を捉えます。このような特徴的な歯によって、ラブカはイカやタコを食べることを可能にしています。
ただし、普段はゆったりと泳ぐラブカが、比較的動きの速いこれらの獲物をどのようにして捕えるのかは現段階で不明となっています。
しかしここで活きるのが、その特徴的な歯の形状です。内向きに曲がった無数のトゲ状の歯が釣り針の「カエシ」のような役割を果たしていて、ガッチリと獲物を捉えます。このような特徴的な歯によって、ラブカはイカやタコを食べることを可能にしています。
ただし、普段はゆったりと泳ぐラブカが、比較的動きの速いこれらの獲物をどのようにして捕えるのかは現段階で不明となっています。
妊娠期間
ラブカの妊娠期間は、ほかのサメの仲間と比較しても非常に長く、約3年半と推定されています。たとえば、大型のホホジロザメで妊娠期間は約1年です。
ラブカの場合、初期の胚の成長がとても遅いことが、妊娠期間が長くなる理由と考えられています。なお、出産する際には50cmから60cmくらいまで成長した状態で生まれてきます。
ラブカの場合、初期の胚の成長がとても遅いことが、妊娠期間が長くなる理由と考えられています。なお、出産する際には50cmから60cmくらいまで成長した状態で生まれてきます。
ラブカの寿命はどれくらい?
「ラブカ?」で背景に魚がいたのはそういうことだったのか… pic.twitter.com/qB1dWQfGpV
— イヅ? (@idu_spla) August 21, 2022
ラブカの正確な寿命は、現段階では把握されていません。ほかの種類のサメの平均的な寿命を参考にした上で推測すると、20年から30年という寿命ではないかといわれています。
ラブカは、水族館などの人工的な環境では数日しか生きられないので、詳しい寿命が判明していません。ただし、ニシオンデンザメというラブカと同じ深海ザメの仲間は平均寿命が200歳となっていて、中には400歳を超えることもあるようです。
このことからラブカの寿命は意外と長いという可能性も考えられます。
ラブカの豆知識
カグラザメ目ラブカ科に属しているラブカは、とにかく謎が多い深海ザメです。見た目はもちろん、ウナギのような泳ぎ方についても他のサメとは違った印象です。
ここでは、寿命も分かっていない謎だらけのラブカに関するウワサ、耳寄り情報など、豆知識を紹介します。
ここでは、寿命も分かっていない謎だらけのラブカに関するウワサ、耳寄り情報など、豆知識を紹介します。
生きた化石といわれている
原始的なサメとして知られているラブカは、「生きた化石」ともいわれています。ラブカの口やエラの特徴が原始的であることなどが代表的な理由です。
はるか昔、3億年以上前に存在していた「クラドセラケ」と共通したウナギの仲間のような先端についた口はその特徴の1つですし、一般的なサメと異なる6対のエラも「クラドセラケ」などの原始的なサメとラブカの共通点となっています。
「生きた化石」といわれているほかのシーラカンスやハイギョ、カブトエビなどの例から考えて、ラブカは恐竜時代から現在まで生き残ってきたとする説もあります。
大半の魚類が属さないグループに属するシーラカンスやハイギョなどの一部の種が陸上進出し、両生類に進化したとされています。
未だに寿命も判明していないラブカも含めた「生きた化石」の研究は、現在も熱心に進められています。
はるか昔、3億年以上前に存在していた「クラドセラケ」と共通したウナギの仲間のような先端についた口はその特徴の1つですし、一般的なサメと異なる6対のエラも「クラドセラケ」などの原始的なサメとラブカの共通点となっています。
「生きた化石」といわれているほかのシーラカンスやハイギョ、カブトエビなどの例から考えて、ラブカは恐竜時代から現在まで生き残ってきたとする説もあります。
大半の魚類が属さないグループに属するシーラカンスやハイギョなどの一部の種が陸上進出し、両生類に進化したとされています。
未だに寿命も判明していないラブカも含めた「生きた化石」の研究は、現在も熱心に進められています。
大学で研究されている
ラブカは、生態や寿命について現時点では把握できていない部分が多い生物です。ラブカを研究すると魚類の進化を知る1つのカギとなるため、大学の研究所などでラブカをテーマにした研究プロジェクトが進められています。
東海大学海洋科学博物館とアクアマリンふくしまのラブカ共同研究は、サメ研究者の東海大学・田中彰教授と堀江琢講師とアクアマリンふくしまによるプロジェクトです。
このラブカ共同研究プロジェクトでは、駿河湾での聞き取り調査や生息調査、環境調査、ラブカの卵の体外飼育などが実施されました。このプロジェクトにより、最長で1か月から2か月間ラブカの赤ちゃんを生かすことに成功したり、361日もラブカの卵を人工保育することができたりしています。
このプロジェクトは、2016年4月1日に発足し研究を続けてきており、2021年7月15日にもラブカ生息環境調査を実施し、同年7月31日に調査結果が発表されています。
出典:東海大学海洋科学博物館×アクアマリンふくしま「ラブカ研究プロジェクト」
|東海大学海洋科学博物館
参照:https://www.umi.muse-tokai.jp/news/single.php?id=117
東海大学海洋科学博物館とアクアマリンふくしまのラブカ共同研究は、サメ研究者の東海大学・田中彰教授と堀江琢講師とアクアマリンふくしまによるプロジェクトです。
このラブカ共同研究プロジェクトでは、駿河湾での聞き取り調査や生息調査、環境調査、ラブカの卵の体外飼育などが実施されました。このプロジェクトにより、最長で1か月から2か月間ラブカの赤ちゃんを生かすことに成功したり、361日もラブカの卵を人工保育することができたりしています。
このプロジェクトは、2016年4月1日に発足し研究を続けてきており、2021年7月15日にもラブカ生息環境調査を実施し、同年7月31日に調査結果が発表されています。
出典:東海大学海洋科学博物館×アクアマリンふくしま「ラブカ研究プロジェクト」
|東海大学海洋科学博物館
参照:https://www.umi.muse-tokai.jp/news/single.php?id=117
一般的なサメよりゆっくり泳ぐ
ラブカは、大半のサメよりもゆっくりと泳ぎます。泳ぎ方としては、ウナギと同じように体をくねらせながら進んでいく方式です。
しかし、ラブカは動きが速いイカなども食べることがあります。ラブカの動きはゆっくりで遅いのに、どのようにして動きの速いイカなどを捕獲しているのかは謎となっています。
この件については諸説があり、傷ついて弱った個体を食べているという説や実は獲物を捕らえるときだけ素早く動くという説、吸い込んで捕獲するという説、特異な形状の歯が疑似餌となっているという説などがあります。
この特徴は、サメの仲間でもあるオンデンザメにも共通しています。オンデンザメの場合、動きの速いアザラシなどを捕食しているという報告もあって、やはり謎に包まれています。
しかし、ラブカは動きが速いイカなども食べることがあります。ラブカの動きはゆっくりで遅いのに、どのようにして動きの速いイカなどを捕獲しているのかは謎となっています。
この件については諸説があり、傷ついて弱った個体を食べているという説や実は獲物を捕らえるときだけ素早く動くという説、吸い込んで捕獲するという説、特異な形状の歯が疑似餌となっているという説などがあります。
この特徴は、サメの仲間でもあるオンデンザメにも共通しています。オンデンザメの場合、動きの速いアザラシなどを捕食しているという報告もあって、やはり謎に包まれています。
地震の前に見つかるという噂がある
ラブカも含め、深海魚が浅瀬までときどき上がってきて、ニュースになることがあります。浅い海域でラブカが捕獲されたという話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これについては、潮流に流されたという説や餌を追ってきたという説などがあることはすでに紹介していますが、このほかにも地震と関係しているという説も存在しています。
もの凄く大きな地震が来る前の海底の地層の変化などをラブカが感知して、不快感や危機を感じることで浅瀬までやって来ているという説です。実際に、大きな地震が起きる前にラブカのような深海生物が漂流してきたという事例は確かにあります。
しかし、こういう事例はあったとしてもあくまで今のところは科学的な根拠がない噂程度とみられています。ラブカは海上にいったん上がると寿命は数日となってしまいますし、浅瀬まで来る原因については、今でも謎が多く、分かっていません。
これについては、潮流に流されたという説や餌を追ってきたという説などがあることはすでに紹介していますが、このほかにも地震と関係しているという説も存在しています。
もの凄く大きな地震が来る前の海底の地層の変化などをラブカが感知して、不快感や危機を感じることで浅瀬までやって来ているという説です。実際に、大きな地震が起きる前にラブカのような深海生物が漂流してきたという事例は確かにあります。
しかし、こういう事例はあったとしてもあくまで今のところは科学的な根拠がない噂程度とみられています。ラブカは海上にいったん上がると寿命は数日となってしまいますし、浅瀬まで来る原因については、今でも謎が多く、分かっていません。
実は食べることができる
詳しい生態や寿命も判明していないラブカですが、実はおいしく食べることができます。地域によっては、刺身や寿司ネタに使われたり煮物やムニエルにしたりする場合もあるそうです。
ラブカは、白身のお魚で熱を通しても硬くなりません。また、刺身にすると脂の甘さと上品なうまみを味わえます。なお、ラブカの肝はアンコウなどの肝よりもコクと後味が良いとされているようです。
このようなラブカの身や肝を酒や醤油で煮つけにしても独特な食感や味わいが楽しめておいしいといわれています。さらに、ラブカの卵も食べることができるということで、卵焼きにすると麩を焼いたような食感と風味が味わえるそうです。
ただし、ラブカはサメの仲間なので長い間放置するとどうしてもアンモニア臭がきつくなります。そうなってしまうと食事に向かなくなる可能性が高くなるので注意が必要です。
ラブカは、白身のお魚で熱を通しても硬くなりません。また、刺身にすると脂の甘さと上品なうまみを味わえます。なお、ラブカの肝はアンコウなどの肝よりもコクと後味が良いとされているようです。
このようなラブカの身や肝を酒や醤油で煮つけにしても独特な食感や味わいが楽しめておいしいといわれています。さらに、ラブカの卵も食べることができるということで、卵焼きにすると麩を焼いたような食感と風味が味わえるそうです。
ただし、ラブカはサメの仲間なので長い間放置するとどうしてもアンモニア臭がきつくなります。そうなってしまうと食事に向かなくなる可能性が高くなるので注意が必要です。
生きた化石ラブカの寿命や生態について知ろう
「生きた化石」とされるラブカの寿命や生態、さらにはさまざまな謎などについて紹介しました。現時点でラブカについてはとても謎が多く、正確な寿命や詳しい生態は明らかにはなっていません。
とにかく謎が多いラブカですが、原始的な特徴をいくつも持っていて、およそ5,000万年から8,000万年前の地層からもラブカの化石は見つかっています。
また、ラブカの寿命はおよそ20年から30年と考えられています。水族館ではラブカが飼育されることはありますが、深海のようには生きられず、寿命は数日となってしまうケースがほとんどです。
ラブカの謎だらけの生態からしても寿命についてはまだまだ研究が必要です。大学などでは、ラブカの寿命も含めて研究が続けられています。より詳しいラブカの寿命もそのうち判明するのではないでしょうか。
生きる化石や幻の魚、古代ザメといわれている深海魚のラブカはこれからも注目されるでしょう。ラブカのサメらしい特徴というと鋭い歯を持っている点ですが、実は従来のサメとは異なる形態を持っています。
この鋭い歯は、トゲが出ているように見え、獲物となるイカやタコ、魚などを逃さないようになっています。このような謎だらけのラブカの寿命や生態を理解しつつ、1つでも謎を解明してみませんか。
とにかく謎が多いラブカですが、原始的な特徴をいくつも持っていて、およそ5,000万年から8,000万年前の地層からもラブカの化石は見つかっています。
また、ラブカの寿命はおよそ20年から30年と考えられています。水族館ではラブカが飼育されることはありますが、深海のようには生きられず、寿命は数日となってしまうケースがほとんどです。
ラブカの謎だらけの生態からしても寿命についてはまだまだ研究が必要です。大学などでは、ラブカの寿命も含めて研究が続けられています。より詳しいラブカの寿命もそのうち判明するのではないでしょうか。
生きる化石や幻の魚、古代ザメといわれている深海魚のラブカはこれからも注目されるでしょう。ラブカのサメらしい特徴というと鋭い歯を持っている点ですが、実は従来のサメとは異なる形態を持っています。
この鋭い歯は、トゲが出ているように見え、獲物となるイカやタコ、魚などを逃さないようになっています。このような謎だらけのラブカの寿命や生態を理解しつつ、1つでも謎を解明してみませんか。