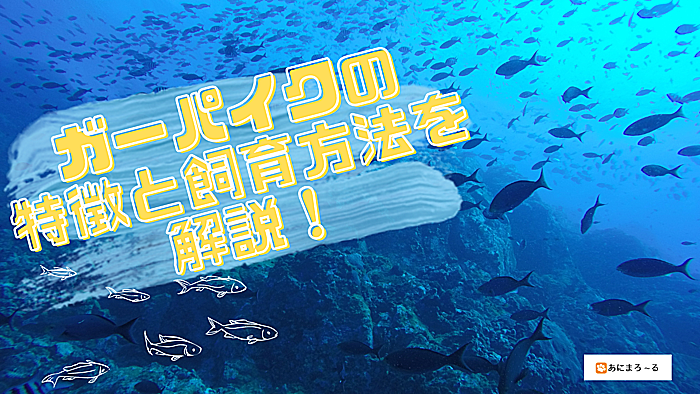「ガーパイクはどんな魚なの?」
「ガーパイクは飼育することができるの?」
「ガーパイクが規制されているって本当?」
このようにガーパイクに興味がある方や、実際に飼育してみたいと考える方には、いろいろな疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では、ガーパイクの特徴や種類などに加えて、ガーパイクの飼育方法についても紹介していきます。また、飼育する際の注意点についても解説していきます。
この記事を読むことで、ガーパイクの基本的な生態や、ガーパイクの飼育に必要な知識を得られます。今までガーパイクについてよく知らなかった方でも、詳しくなれるでしょう。
ガーパイクを好きな方や興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
「ガーパイクは飼育することができるの?」
「ガーパイクが規制されているって本当?」
このようにガーパイクに興味がある方や、実際に飼育してみたいと考える方には、いろいろな疑問や不安があるのではないでしょうか。
本記事では、ガーパイクの特徴や種類などに加えて、ガーパイクの飼育方法についても紹介していきます。また、飼育する際の注意点についても解説していきます。
この記事を読むことで、ガーパイクの基本的な生態や、ガーパイクの飼育に必要な知識を得られます。今までガーパイクについてよく知らなかった方でも、詳しくなれるでしょう。
ガーパイクを好きな方や興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
ガーパイクの飼育は規制されている?
そもそもガーパイクは飼育することができるのでしょうか。
実は、2018年4月1日からガーパイクの飼育や販売が規制されています。
これは特定外来生物に指定されたためで、指定された場合、飼養、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことが規制されます。輸入や販売が規制されているため、ショップなどで新たに販売されることもありません。
ガーパイクは飼育しきれなくなり川や池などに放流する人が相次ぎ、生態系が崩れる危険性があると判断されました。このため、環境省がガーパイクを特定外来生物に指定することを決定しました。
出典:ガーパイクの飼育や販売の規制|環境省
参照:https://hokkaido.env.go.jp/to_2018/30.html#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%AE%E9%A3%BC%E8%82%B2%E3%82%84%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%8C%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,%E3%82%AC%E3%83%BC%E7%A7%91%E3%81%AE%E5%85%A8%E7%A8%AE%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BA%A4%E9%9B%91%E5%80%8B%E4%BD%93%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%88%E9%80%9A%E7%A7%B0%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%EF%BC%89%E3%81%8C%E3%80%81%E5%B9%B3%E6%88%90%2030%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%A4%96%E6%9D%A5%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
実は、2018年4月1日からガーパイクの飼育や販売が規制されています。
これは特定外来生物に指定されたためで、指定された場合、飼養、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つことが規制されます。輸入や販売が規制されているため、ショップなどで新たに販売されることもありません。
ガーパイクは飼育しきれなくなり川や池などに放流する人が相次ぎ、生態系が崩れる危険性があると判断されました。このため、環境省がガーパイクを特定外来生物に指定することを決定しました。
出典:ガーパイクの飼育や販売の規制|環境省
参照:https://hokkaido.env.go.jp/to_2018/30.html#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%81%AE%E9%A3%BC%E8%82%B2%E3%82%84%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%8C%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,%E3%82%AC%E3%83%BC%E7%A7%91%E3%81%AE%E5%85%A8%E7%A8%AE%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BA%A4%E9%9B%91%E5%80%8B%E4%BD%93%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%EF%BC%88%E9%80%9A%E7%A7%B0%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AF%EF%BC%89%E3%81%8C%E3%80%81%E5%B9%B3%E6%88%90%2030%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%A4%96%E6%9D%A5%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%8C%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
申請すればガーパイクの飼育は可能か
ガーパイク規制法をもう少し考え直してくれんかな pic.twitter.com/EUhcDWdfs8
— P (@dinosaur_ell) February 2, 2022
ガーパイクが特定外来生物に指定されて飼育や販売が規制されたため、現在は新しく飼育を始めることができません。
しかし、規制される前からペットや鑑賞目的で飼育していたガーパイクについては規制されてから6か月以内に申請を提出し、許可を受けることで飼い続けることができます。
また、規制後も学術研究や展示、教育等の目的の場合は、許可を得ることで飼養などが可能となります。
出典:日本の外来種対策|環境省
参照:https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html
ガーパイクの生態・特徴について
ガーは美しい
— ユーキ (@yuki0328cb750fc) September 14, 2020
ガーパイク最高? pic.twitter.com/5S0lqAvz2V
ガーパイクはガー目ガー科に分類される魚で、ワニのように長い体が特徴です。
アメリカが主な生息地で、種類によっては体長3mまで成長することがあります。
また、ガーパイクは古代魚に分類され、生きた化石とも呼ばれます。古代から今でも変わらない姿が見られるとても生命力が高い生物です。
魚類は通常エラ呼吸をしますが、ガーパイクは空気呼吸で酸素を取り入れることもできます。そのため、陸上でも短時間であれば生きられるといわれます。
ガーパイクの種類
おはようございます☀ #ガーパイク pic.twitter.com/2FnYS9biu4
— タカヒロ (@aro_takahiro) April 6, 2022
ガーパイクは非常に種類の多い魚です。
種類によって大きさ、体の色や模様などが異なります。
ガーパイクは肉食ですが温和な魚のため、ほかの種類と混泳してもほとんど争うことがなく、ガーパイク同士を一緒に飼育することも可能です。
本記事ではガーパイクの種類の中から3種類を抜粋して紹介します。
ロングノーズガー
ロングノーズガーとは、名前の通り、長い吻(口先)が特徴のガーパイクです。
細長い吻は素早い動きの小魚などを捕まえるのに適しています。
野生のロングノーズガーは2mくらいまで成長すること個体ですが、水槽飼育の場合は1mほどの大きさで止まります。
ガーパイクの中でも広範囲に分布している種類で、主にアメリカやカナダ、メキシコなどに生息しています。
細長い吻は素早い動きの小魚などを捕まえるのに適しています。
野生のロングノーズガーは2mくらいまで成長すること個体ですが、水槽飼育の場合は1mほどの大きさで止まります。
ガーパイクの中でも広範囲に分布している種類で、主にアメリカやカナダ、メキシコなどに生息しています。
スポッテッドガー
ガーパイクが規制される前、一般的に多く飼育されてきたのがスポッテットガーとなります。
スポット状に模様が入っているのが特徴で、水槽では1m以下に収まることが多く、ガーパイクの種類の中では小型といえます。
スポッテッドガーはガーパイクの中では水質がきれいで、流れの緩やかな沼地や湿地を好んで生息しています。主にアメリカやメキシコに分布します。
地域により個体差があり、模様や吻の形が異なる種もいます。
主に小魚を主食にしますが、爬虫類や昆虫を捕食することもあります。
スポット状に模様が入っているのが特徴で、水槽では1m以下に収まることが多く、ガーパイクの種類の中では小型といえます。
スポッテッドガーはガーパイクの中では水質がきれいで、流れの緩やかな沼地や湿地を好んで生息しています。主にアメリカやメキシコに分布します。
地域により個体差があり、模様や吻の形が異なる種もいます。
主に小魚を主食にしますが、爬虫類や昆虫を捕食することもあります。
アリゲーターガー
ガーパイクの中で最大ともいわれる種類がアリゲーターガーです。野生のアリゲーターガーは最大3mにまで成長することがあり、飼育下でも2mくらいまで大きくなることもあります。
アリゲーターとはワニのことですが、アリゲーターガーをワニと間違えることもあるようです。
ガーパイクが規制される前は、アリゲーターガーの稚魚が安価で売られていました。気軽に飼い始めた人が、想像以上に大きく成長して飼育を続けることができず川や池などへ放流することが問題となりました。
アメリカやメキシコに生息しており、魚類を主食にしています。水鳥や爬虫類などを捕食することもあります。
アリゲーターとはワニのことですが、アリゲーターガーをワニと間違えることもあるようです。
ガーパイクが規制される前は、アリゲーターガーの稚魚が安価で売られていました。気軽に飼い始めた人が、想像以上に大きく成長して飼育を続けることができず川や池などへ放流することが問題となりました。
アメリカやメキシコに生息しており、魚類を主食にしています。水鳥や爬虫類などを捕食することもあります。
ガーパイクの飼育に必要なもの
こんにちは。
— タカヒロ (@aro_takahiro) July 14, 2022
ガーはやっぱりアリガーが一番‼️#ガーパイク pic.twitter.com/xGqJksSSIr
ガーパイクの飼育に必要なものとして、水槽があります。ガーパイクは一般的に飼育する魚の中では大型の種類になるため、飼育するガーパイクの大きさにあわせた水槽を用意する必要があります。
ガーパイクは体がとても硬く、また小さい水槽だと背中が曲がってしまうこともあるため、できるだけ大きい水槽でストレスがかからないように飼育しましょう。また、ガーパイクが飛び出してしまうことを防ぐために、水槽の蓋も用意しましょう。
適切な水温や水質で飼育するための、ヒーターとフィルターも必要です。
ガーパイクの餌は、メダカなどの魚や、コオロギなどの昆虫、エビやカニなどの甲殻類、人工飼料などを用意しましょう。
ガーパイクは空気呼吸をするため、水槽を満タンにせず、ガーパイクが水面に上がって息継ぎができるスペースを作りましょう。
- 水槽
- ヒーター
- フィルター
- 餌
ガーパイクの飼育について
ガーパイク増やしたい pic.twitter.com/FT0IbkpNMU
— P (@dinosaur_ell) July 17, 2022
魚の中では大型に分類されるガーパイクですが、飼育するときに気を付けるポイントがいくつかあります。
規制されているため、新しく飼育し始めることはできませんが、現在ガーパイクを飼育している人は次の4点に注意して育てましょう。
水槽の掃除について
大型魚であるガーパイクは餌をたくさん食べるため、その分水が汚れるのも早いです。
定期的に水槽の掃除や水換えをして、ガーパイクが住みやすい環境を作りましょう。
また、大きな水槽で飼育している場合が多いため、水換え用のホースを用意しておくとよいでしょう。
設置しているフィルターも汚れるため、定期的に掃除することが大切です。
定期的に水槽の掃除や水換えをして、ガーパイクが住みやすい環境を作りましょう。
また、大きな水槽で飼育している場合が多いため、水換え用のホースを用意しておくとよいでしょう。
設置しているフィルターも汚れるため、定期的に掃除することが大切です。
水質と水温について
ガーパイクは中性の水質、25度前後の水温を好みます。低い温度でも生活はできますが、水温を上げると成長が早まる傾向にあります。
体が大きく成長するほど水を汚しやすくなるため、しっかりとフィルターを稼働させて対策しましょう。
また、水道水に含まれる塩素はガーパイクに危険なのでカルキ抜きを使うとよいでしょう。
ガーパイクは丈夫な体を持ちますが、あまりにも水質が悪いと病気になってしまいます。定期的に水質をチェックしてガーパイクにストレスがかからないよう注意しましょう。
体が大きく成長するほど水を汚しやすくなるため、しっかりとフィルターを稼働させて対策しましょう。
また、水道水に含まれる塩素はガーパイクに危険なのでカルキ抜きを使うとよいでしょう。
ガーパイクは丈夫な体を持ちますが、あまりにも水質が悪いと病気になってしまいます。定期的に水質をチェックしてガーパイクにストレスがかからないよう注意しましょう。
餌について
ガーパイクはメダカや金魚などの魚類や、ミルワームやコオロギなどの昆虫類、エビやカニなどの甲殻類、人工飼料などなんでも食べます。
背曲がりなどの成長障害が出ることもあるため、人工飼料だけでの飼育ではなく、生餌とバランスよく与えるのがよいでしょう。
幼魚のうちは赤虫などを配合して与えますが、このころに栄養バランスが悪いと、成長したときの体型に異常をきたす場合があります。
またクリルばかり与えると、消化不良や背骨の異常などが起こる危険もあるため注意が必要です。
背曲がりなどの成長障害が出ることもあるため、人工飼料だけでの飼育ではなく、生餌とバランスよく与えるのがよいでしょう。
幼魚のうちは赤虫などを配合して与えますが、このころに栄養バランスが悪いと、成長したときの体型に異常をきたす場合があります。
またクリルばかり与えると、消化不良や背骨の異常などが起こる危険もあるため注意が必要です。
病気について
ガーパイクは非常に丈夫な魚のため、病気にはめったにかかりません。
幼魚のうちは水質や水温に注意した方がよいですが、成長すればほとんど病気になることはありません。
病気にならないように日頃の管理をしっかりして、万が一病気になった場合には水換えして様子をみるとよいでしょう。治らないときには薬を使いますが、古代魚に分類されるガーパイクは薬に弱いといわれているため、注意が必要です。
また、ガーパイクの飼育には体型障害に注意が必要です。これはほとんどが成長期の栄養不足や水槽の狭さによるストレスが原因です。障害のある個体は長生きできないため、適切な餌や水槽などの環境をそろえましょう。
幼魚のうちは水質や水温に注意した方がよいですが、成長すればほとんど病気になることはありません。
病気にならないように日頃の管理をしっかりして、万が一病気になった場合には水換えして様子をみるとよいでしょう。治らないときには薬を使いますが、古代魚に分類されるガーパイクは薬に弱いといわれているため、注意が必要です。
また、ガーパイクの飼育には体型障害に注意が必要です。これはほとんどが成長期の栄養不足や水槽の狭さによるストレスが原因です。障害のある個体は長生きできないため、適切な餌や水槽などの環境をそろえましょう。
ガーパイクは混泳可能?
な~さん。水族館(自称)のアロワナ
— な~さん。 (@naasan626) June 28, 2019
ガーパイク等の古代魚達が泳ぐ
3000×1200×900メイン水槽です!( ̄▽ ̄)ゞ
夢を見始めて約10年、構想1年
夢の水槽を実現する事が出来ました! pic.twitter.com/HgXIhdgIcX
ガーパイクはおとなしい性格をしているため混泳させやすい魚です。
同サイズのおとなしい魚や、生活域が異なる魚がよいでしょう。
アロワナやポリプテルス、淡水エイなどとの混泳がおすすめです。
ガーパイク同士の混泳もできるため、複数のガーパイクを飼育している人は混泳させてもよいでしょう。
混泳する場合は、魚によって餌を食べるスピードが異なるため、しっかりと餌がいきわたるように注意しましょう。
ガーパイクは新たに飼育できないことを覚えておこう
やっぱガーパイクは最高? pic.twitter.com/gquOwr32Qr
— R O D E O (@RODEO83441060) April 18, 2018
大型魚でおとなしい性格のガーパイクを飼育したいと考える人もいるかもしれませんが、残念ながら規制されてしまい新しく飼い始めることはできません。
規制前から飼育している人は許可を受ければ飼育を続けることができるため、責任感を持って飼育しましょう。
ガーパイクは日本国内で新規に飼育することができなくなった貴重な古代魚です。
決して川や池に放流したりせず、寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。