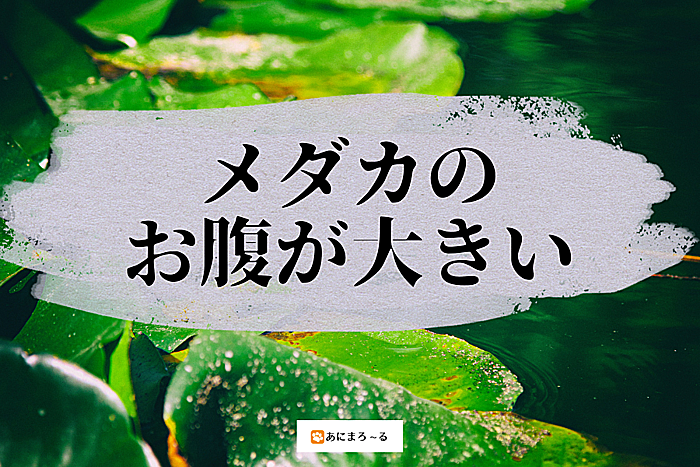メダカを飼育している時に、いつもよりお腹が大きいことはありませんか?
自然と解消される場合もあれば、改善されない事もあります。
お腹が大きくなってしまって元に戻らない場合、対処に迷う方は多いでしょう。
本記事ではメダカのお腹が大きくなってしまって困った方のために、その原因と対処方を詳しくみていきます。メダカのお腹が大きくなるのには理由があり、原因によって対処方法が異なっている為、本記事では主な原因と、それに対応する対処方法を併わせて紹介します。
本記事を読んで頂ければ、原因と対処方法がわかるようになるので、今後より一層メダカの飼育が楽しくなることでしょう。
メダカを飼育している方はもちろん、これから飼育したいという方にも有用な情報ですので、是非最後まで記事をチェックしてみてください。
自然と解消される場合もあれば、改善されない事もあります。
お腹が大きくなってしまって元に戻らない場合、対処に迷う方は多いでしょう。
本記事ではメダカのお腹が大きくなってしまって困った方のために、その原因と対処方を詳しくみていきます。メダカのお腹が大きくなるのには理由があり、原因によって対処方法が異なっている為、本記事では主な原因と、それに対応する対処方法を併わせて紹介します。
本記事を読んで頂ければ、原因と対処方法がわかるようになるので、今後より一層メダカの飼育が楽しくなることでしょう。
メダカを飼育している方はもちろん、これから飼育したいという方にも有用な情報ですので、是非最後まで記事をチェックしてみてください。
メダカのお腹が大きいときに考えられる6つの原因
まずは、メダカのお腹が大きい時に考えられる原因を6つ紹介します。「えさの食べ過ぎ」や「便秘」などの複数の原因が考えられる状態です。それぞれ対処方法が異なってきますので、原因となる部分を確認していきましょう。
原因によっては初期の対処が非常に重要になってきます。日頃からメダカの様子を観察してあげて、これから紹介する原因と対処方法を是非参考にしてください。
原因によっては初期の対処が非常に重要になってきます。日頃からメダカの様子を観察してあげて、これから紹介する原因と対処方法を是非参考にしてください。
1:卵が排出できず詰まってしまう「過抱卵病」
もし飼育しているメダカがメスの場合、お腹が大きい理由として考えられる原因として上がるのが過抱卵病になります。過抱卵病はお腹の卵を排出できずに、お腹の中に卵が溜まってしまう病気です。
過抱卵病の原因として考えられるものには相性がいいオスがいなかったり、メスの生殖孔が詰まってしまったりなどの原因が考えられます。
過抱卵病の原因として考えられるものには相性がいいオスがいなかったり、メスの生殖孔が詰まってしまったりなどの原因が考えられます。
2:浮力の調整ができなくなる「転覆病」
一番わかりやすい症状が出てくるのが転覆病です。転覆病はメダカのお腹にガスが溜まってしまい、浮き袋での浮力調整が出来なくなってしまう病気です。浮力の調整が出来なくなってしまうため、上下逆さまの状態で泳ぐのが特徴となります。
そのままにしておくと、メダカは衰弱して力尽きてしまうため、発見した場合にはすぐに対処をおこないましょう。
そのままにしておくと、メダカは衰弱して力尽きてしまうため、発見した場合にはすぐに対処をおこないましょう。
3:お腹が膨れて鱗が逆立つ「松かさ病」
次に紹介するのが松かさ病です。この病気もわかりやすい症状が出てくるので、比較的見分けはつきやすいものになります。松かさ病を発症すると、メダカのお腹が大きい状態になり、鱗が逆立つので見分けはつきやすいです。
この病気はエロモナス菌という細菌感染によって引き起こされ、発症初期から治療を行う事が重要になってきます。メダカの鱗が逆立ってお腹が大きい等の症状が見られた場合には、早急に対処しましょう。
この病気はエロモナス菌という細菌感染によって引き起こされ、発症初期から治療を行う事が重要になってきます。メダカの鱗が逆立ってお腹が大きい等の症状が見られた場合には、早急に対処しましょう。
4:どんどんお腹が膨らんでいく「腹水病」
メダカのお腹に水が溜まってしまう腹水病を紹介いたします。この病気を発症した際にもメダカのお腹はだんだんと大きい状態になって、末期には破裂しそうなほど大きい状態になる程です。腹水病は消化不良や内臓疾患によって引き起こされる病気で、特徴としては細長い糞をするようになります。
最初はご飯の食べ過ぎや、便秘などと見分けがつかないことが多いですが、腹水病の場合は餌を与えなくてもお腹は徐々に大きくなっていきます。
最初はご飯の食べ過ぎや、便秘などと見分けがつかないことが多いですが、腹水病の場合は餌を与えなくてもお腹は徐々に大きくなっていきます。
5:エサの食べ過ぎ
病気ではありませんが、メダカは餌の食べ過ぎでもお腹が大きい状態になることがあります。餌を食べ過ぎてしまい、お腹が大きい状態が続くと他の病気の引き金になる事もあるので、餌は適切な量を与えるようにしましょう。
6:便秘
餌の食べ過ぎから続きますが、お腹が大きい状態になってしまう症状として考えられるのが便秘です。餌を食べ過ぎてしまったり、古い餌を食べたりした場合に引き起こされる消化不良によってメダカも便秘になります。特に、水温が低い時に餌を与えると便秘になりやすくなるので注意が必要です。
便秘になってしまうと、メダカは糞を出すことができなくなってしまうため、そのまま放置すると死んでしまいます。もし、糞が出ないメダカがいたら早急に対処してあげましょう。
便秘になってしまうと、メダカは糞を出すことができなくなってしまうため、そのまま放置すると死んでしまいます。もし、糞が出ないメダカがいたら早急に対処してあげましょう。
オスのメダカのお腹が大きい場合の原因
オスのメダカの場合は過抱卵病以外の原因が主に考えられます。ですが、オスのメダカにだけ見られる特殊な原因として布袋メダカと呼ばれるものがあり、オスからメスに性転換する突然変異体のことです。この場合お腹が大きい時は、精巣や卵巣が大きくなっていることが考えられます。
布袋メダカの場合はお腹が大きい状態でも病気ではないので、そのまま見守る事が重要です。
布袋メダカの場合はお腹が大きい状態でも病気ではないので、そのまま見守る事が重要です。
【原因別】メダカのお腹が大きいときの対処法
メダカのお腹が大きくなる原因を紹介してきましたが、ここからはお腹が大きくなった場合の対処方法を原因別に紹介いたします。原因によって対処方法が異なってきますので、メダカをよく観察して適切な対処をしてあげましょう。
病気によっては初期の対処が重要となりますので、異常を感じた場合にはメダカの様子を観察して、原因ごとに対処していく事が非常に大切です。
病気によっては初期の対処が重要となりますので、異常を感じた場合にはメダカの様子を観察して、原因ごとに対処していく事が非常に大切です。
過抱卵病の場合
過抱卵病のメダカは卵が産めず、お腹が大きくなってしまう事があります。その場合の対処方法は4点ありますので、もしメスのメダカで過抱卵病が疑われる場合には参考にしてください。
他のオスとペアにする
オスとメスを同じ水槽で1匹ずつペアリングしている場合には、相性が悪くて交尾をせずに卵も産めなくなるため、過抱卵病になってしまいます。もしオスとメスのペアリングで相性が悪い場合には、他のオスにかえて相性を見てみましょう。
水槽で複数のメダカを飼育している場合は、オスの数が十分かどうか確認して下さい。メス2匹に対してオス1匹の割合で飼育すると、バランスよく交尾と産卵を促すことができます。
出典:メダカのお腹が膨らむ原因① 過抱卵の対処法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medakas-stomach-swells/#i-5
水槽で複数のメダカを飼育している場合は、オスの数が十分かどうか確認して下さい。メス2匹に対してオス1匹の割合で飼育すると、バランスよく交尾と産卵を促すことができます。
出典:メダカのお腹が膨らむ原因① 過抱卵の対処法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medakas-stomach-swells/#i-5
飼育している容器を変える
オスとメスの比率を見直しても、なかなか改善されない場合もあります。その場合には飼育容器を変えるなど、環境の変化で刺激を与えてあげる事も有効です。その後もメダカの様子を観察してあげましょう。
水換えをする
また、水槽を変えるタイミングで水換えするのも有効です。水換えの際は全体の1/3程度にして、10リットルに対して一つまみの塩を入れてあげるのも、雑菌を防ぐ効果があるので効果的に使ってあげましょう。
生殖孔を綿棒などで刺激する
上記の方法でもメダカの様子が改善できない場合は、産卵孔が詰まってしまっていて卵を産めていない可能性があります。この場合にはメスの産卵孔を綿棒などで刺激してあげる事で、卵を排出させてあげる事も有効です。
もし産卵孔が分からない場合は糞が出る肛門付近を目安にして、綿棒などで刺激してあげると排卵を促すことができます。
もし産卵孔が分からない場合は糞が出る肛門付近を目安にして、綿棒などで刺激してあげると排卵を促すことができます。
転覆病の場合
もしメダカが転覆病になってしまった場合には、発症した個体を隔離して治療してあげましょう。転覆病を発症した個体を塩分濃度が0.5%の水槽で塩浴をさせ、水温は25℃~28℃程と少し高めに設定してあげると効果的です。
転覆病は餌の食べ過ぎた場合の消化器官の機能低下が原因で発症する場合が多く、絶食なども併せて消化器官の回復を行うのも重要です。発症初期の場合は回復する場合が多いので、日頃から観察していきましょう。
出典:メダカのお腹が膨らむ原因④ 転覆病の対処法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medakas-stomach-swells/#i-8
転覆病は餌の食べ過ぎた場合の消化器官の機能低下が原因で発症する場合が多く、絶食なども併せて消化器官の回復を行うのも重要です。発症初期の場合は回復する場合が多いので、日頃から観察していきましょう。
出典:メダカのお腹が膨らむ原因④ 転覆病の対処法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medakas-stomach-swells/#i-8
松かさ病の場合
松かさ病はエロモナス菌という常在菌の感染によって引き起こされます。症状が出てくると完治させるのが非常に困難な病気です。松かさ病の場合にも隔離して塩浴をして、毎日水換えを行う事が完治に有効な手段になります。
毎日水換えが難しい場合は2日~3日に一回は水を変えてあげましょう。また、専用の抗菌剤入りのお薬を使って、可能であれば初期の段階で治療してあげる事も必要です。発症してしまうと完治させるのはかなり難しい病気なので、早めの発見と対処を心がけましょう。
出典:メダカのお腹が膨らむ原因⑤ 松かさ病の対処法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medakas-stomach-swells/#i-9
毎日水換えが難しい場合は2日~3日に一回は水を変えてあげましょう。また、専用の抗菌剤入りのお薬を使って、可能であれば初期の段階で治療してあげる事も必要です。発症してしまうと完治させるのはかなり難しい病気なので、早めの発見と対処を心がけましょう。
出典:メダカのお腹が膨らむ原因⑤ 松かさ病の対処法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medakas-stomach-swells/#i-9
腹水病の場合
腹水病の場合も塩浴をすることで改善させる事も可能です。まず腹水病を発症してしまったメダカを隔離容器に移し、飼育水を半分ほど入れて残りは新しい水を入れましょう。この際、隔離容器に移したメダカに負担をかけないように元の飼育環境からあまり変化をつけず、水温は25℃~28℃程を維持しましょう。
元の飼育環境の水温が低かった場合は、1日に1℃ずつ上げるなどして調整していきます。
出典:メダカの腹水病の治療方法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medaka-ascites-disease/
元の飼育環境の水温が低かった場合は、1日に1℃ずつ上げるなどして調整していきます。
出典:メダカの腹水病の治療方法|メダカの飼い方.com
参照:https://medaka.papa77.com/medaka-ascites-disease/
食べ過ぎの場合
餌を食べ過ぎてお腹が膨れてしまった場合の対処方法は、他の病気に比べて簡単です。餌を食べ過ぎてお腹が大きくなったメダカがいた場合は、2日~3日程絶食させてあげることで改善させることができます。お腹の大きさが元通りになったら、少しずつ餌を与えるようにしましょう。
元通りになった場合でも、食べ過ぎにならないよう注意して給餌してあげるのが重要になります。
元通りになった場合でも、食べ過ぎにならないよう注意して給餌してあげるのが重要になります。
便秘の場合
便秘のメダカは消化器官の機能が低下しているので、メダカの消化器官を回復させるのが必要になります。メダカの絶食を行い、こまめな水換えで新陳代謝を高めて排便を促すことが重要です。
便秘になるメダカは寒い時期に出てくることが多い為、水温を25℃~28℃程にしてあげるのも有効ですが、一気に上げず少しずつ水温を上げていきましょう。水温を上げていくことで新陳代謝をよくし、消化器官を活性化させてあげると便秘の解消にも有効です。
出典:消化不良で便秘になる|ペッター
参照:https://petr.jp/medaka-onaka-ookii-7373
便秘になるメダカは寒い時期に出てくることが多い為、水温を25℃~28℃程にしてあげるのも有効ですが、一気に上げず少しずつ水温を上げていきましょう。水温を上げていくことで新陳代謝をよくし、消化器官を活性化させてあげると便秘の解消にも有効です。
出典:消化不良で便秘になる|ペッター
参照:https://petr.jp/medaka-onaka-ookii-7373
メダカのお腹が大きいときの注意点
メダカのお腹が大きくなってしまった場合には、注意深く観察して適切な対処を行う事が必要です。メダカのお腹が大きくなるのは様々な原因があり、間違った対処を行うと死んでしまう事もあります。
異常を発見した際には、メダカの動きや飼育環境などを注意深く観察していく事が非常に重要です。
異常を発見した際には、メダカの動きや飼育環境などを注意深く観察していく事が非常に重要です。
お腹が破裂しそうなほどパンパンになる前に対処する
普段からメダカの様子を観察し、異常を感じたらすぐに対処することが重要です。対処が遅れてしまった場合、お腹がパンパンになってしまったメダカは内臓圧排による衰弱や、お腹が破裂して死んでしまう事もあります。
特に松かさ病、腹水病、続いて転覆病などは初期に対処できるかできないかで、メダカが死んでしまうかもしれませんので注意深く観察していきましょう。
特に松かさ病、腹水病、続いて転覆病などは初期に対処できるかできないかで、メダカが死んでしまうかもしれませんので注意深く観察していきましょう。
お腹がパンパンでも元気な場合は様子をみる
メダカのお腹が大きくても元気に泳いでいる場合は、少し様子を見てあげるのも大事です。オスのメダカのお腹が大きい場合には対処法が無い為、そのまま様子見をしても問題はありません。
餌の食べ過ぎが原因でお腹が大きくなっている場合には、餌の量を減らして糞が出るのを待てば問題ありません。メダカのお腹が大きくなり始めたらこまめに様子を観察して、異常を感じた場合は対処を行いましょう。
その上でも元気な場合には病気である可能性は低くなります。注意しないといけないのは松かさ病と腹水病です。その病気だけ気を付けて様子を見るのが重要になります。
餌の食べ過ぎが原因でお腹が大きくなっている場合には、餌の量を減らして糞が出るのを待てば問題ありません。メダカのお腹が大きくなり始めたらこまめに様子を観察して、異常を感じた場合は対処を行いましょう。
その上でも元気な場合には病気である可能性は低くなります。注意しないといけないのは松かさ病と腹水病です。その病気だけ気を付けて様子を見るのが重要になります。
メダカのお腹が大きいときは適切に対処しよう
メダカのお腹が大きくなってしまった場合の原因と、それに対応する対処方法を紹介させて頂きましたが参考になりましたでしょうか?メダカは小さいため、観察しないとわからないことも多いです。
危なくない病気もあれば、進行が早くて危険な病気などもあります。これらの病気は気が付いた時には手遅れな状態になっている場合もありますので、発症しないように予防することが非常に重要です。
メダカの様子を観察して適切な対処を行ってあげる事で、メダカを元気にしてあげる事もできるので、日頃からメダカの様子を確認してあげましょう。もしメダカのお腹が大きくなってお困りの際は参考にしてください。
危なくない病気もあれば、進行が早くて危険な病気などもあります。これらの病気は気が付いた時には手遅れな状態になっている場合もありますので、発症しないように予防することが非常に重要です。
メダカの様子を観察して適切な対処を行ってあげる事で、メダカを元気にしてあげる事もできるので、日頃からメダカの様子を確認してあげましょう。もしメダカのお腹が大きくなってお困りの際は参考にしてください。