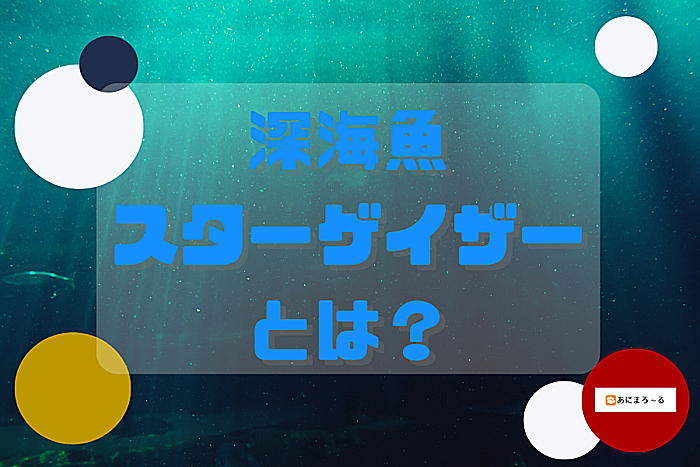深海魚スターゲイザーの名前の由来
スターゲイザーとは外国の名前
スターゲイザーとはなんだかカッコいい名前だと思う人も多いでしょう。しかし、スターゲイザーが本当の名前ではありません。スターゲイザーとはオコゼという魚の仲間についた別名です。
これから紹介する魚は体の上部に目があります。よって、常に上を向いていることから常に星空を見ているような姿に見え、「スターゲイザー」英語で「星を見つめる者」「天文学者、占星術師」という意味の名前がつきました。スターゲイザーとは、オコゼの仲間についた英名のことを指します。
日本の代表的なスターゲイザーである「ミシマオコゼ」の英語名は「Japanese Stargazer」で、直訳すると「日本の星を見る者」です。アメリカに生息する「Northen Stargazer」は「北の星を見る者」です。生息する地域によって名前がつけられていますが、訳してみるとロマンチックな名前の魚とも言えるでしょう。
これから紹介する魚は体の上部に目があります。よって、常に上を向いていることから常に星空を見ているような姿に見え、「スターゲイザー」英語で「星を見つめる者」「天文学者、占星術師」という意味の名前がつきました。スターゲイザーとは、オコゼの仲間についた英名のことを指します。
日本の代表的なスターゲイザーである「ミシマオコゼ」の英語名は「Japanese Stargazer」で、直訳すると「日本の星を見る者」です。アメリカに生息する「Northen Stargazer」は「北の星を見る者」です。生息する地域によって名前がつけられていますが、訳してみるとロマンチックな名前の魚とも言えるでしょう。
日本の"ミシマオコゼ"とは?
日本に生息する代表的なスターゲイザーは「ミシマオコゼ」という魚です。ミシマとは醜いことから有名な三島女郎から来ていて、三島女郎のように醜い魚であることからその名がつきました。また、オコゼという魚に似ていることからオコゼの名がついていますが、スターゲイザーとオニオコゼなどの魚は別の科に属する魚です。
深海魚スターゲイザーの生態と特徴
オコゼの仲間のことを言う
スターゲイザー(Stargazer)とは、紹介したとおりオコゼの仲間スズキ目ワニギス亜目ミシマオコゼ科に属する魚についた英名です。このミシマオコゼ科は、現在は世界に約8属50種いるとされています。そのうち、日本に生息するのは4属7種です。
上の写真は、スターゲイザーではなくフサカサゴ科に属するオニオコゼという魚です。オコゼというと一般的にこの種類を思い浮かべたり、知っていたりする人が多いでしょう。これらのオコゼと違う点は体の形です。オニオコゼは棘状の背びれがありますが、スターゲイザーは砂の中にもぐって身を隠すため、立方体の体を持っています。
スターゲイザーは、体長は25~40㎝ほどの肉食性の魚で、魚類やエビやカニなどの甲殻類、シャコ類、タコやイカの頭足類と、いろんな動物を捕食します。夜行性なので昼間はずっと砂の中に隠れ、獲物が来るのを待ち伏せしています。
上の写真は、スターゲイザーではなくフサカサゴ科に属するオニオコゼという魚です。オコゼというと一般的にこの種類を思い浮かべたり、知っていたりする人が多いでしょう。これらのオコゼと違う点は体の形です。オニオコゼは棘状の背びれがありますが、スターゲイザーは砂の中にもぐって身を隠すため、立方体の体を持っています。
スターゲイザーは、体長は25~40㎝ほどの肉食性の魚で、魚類やエビやカニなどの甲殻類、シャコ類、タコやイカの頭足類と、いろんな動物を捕食します。夜行性なので昼間はずっと砂の中に隠れ、獲物が来るのを待ち伏せしています。
目
スターゲイザーという名前の由来となり、大きく印象づけるのがこの大きな目です。その目は、顔の上部についています。これは、砂にもぐっても目だけは砂の上に出すことができ、獲物を発見することができるからです。目の周りの体の模様は砂時にそっくりなので、擬態することができ、外敵や獲物に発見されづらい体になっています。
歯
スターゲイザーが恐ろしい顔をしていると感じるのは、その歯の多さにもあります。映画に出てくる怪獣のような歯をしています。これは、スターゲイザーが獲物を丸呑みする修正と関係しています。
スターゲイザーは、時に自分より大きな獲物を捕食します。丸呑みするためには、獲物に逃げられないようにその歯でしっかりと捕まえる必要があります。獲物が近づいてきたらスターゲイザーは一瞬で捕まえ、丸呑みします。その一瞬を逃さないためには、しっかりとした歯が必要になります。
スターゲイザーは、時に自分より大きな獲物を捕食します。丸呑みするためには、獲物に逃げられないようにその歯でしっかりと捕まえる必要があります。獲物が近づいてきたらスターゲイザーは一瞬で捕まえ、丸呑みします。その一瞬を逃さないためには、しっかりとした歯が必要になります。
電気を発する
アメリカに生息するノーザンスターゲイザーはデンキウナギと同じように、電気を発することでも知られています。両目の後ろに電気を発する器官をもっています。ダイバーが誤って触った際に発したことから、獲物である小魚を気絶させるためや身を守るためだと言われていますが、明確な理由はまだわかっていません。
深海魚スターゲイザーがいる海
どこにいるの?
スターゲイザーは世界中の海にいます。世界のミシマオコゼ科だと日本各地だけでなく太平洋、大西洋、インド洋、パラオ海嶺と分布は広きにわたっています。日本のミシマオコゼ(Japanese Stargazer)は、日本各地と東シナ海~朝鮮半島、台湾、中国東シナ海沿岸に主に分布しています。
水深
スターゲイザーは水深250mで見つかった例もあるため、深海魚と言えます。しかし、多く分布するのは沿岸域から大陸棚縁辺域といったきわめて浅い場所です。ミシマオコゼなど一部の種類は、河口域にまで生息地を広めているものもいます。
ダイビングで見られる?
このように変わった魚を実際に見てみたいとおもった人もいるでしょう。実は、実際にスターゲイザーを見ることができます。それは、ダイビングで海に潜って見に行く方法です。
日本のダイビングスポットの代表である伊豆の海では、スターゲイザーの一種であるメガネウオがよくみられます。メガネウオは、スターゲイザーの中でも特に浅い水深に生息する魚で、100mよりも深い場所にはいません。したがって、ダイビングで潜れる場所で見られるということです。
ダイビングは、体験だけならライセンスは必要ありませんが、潜れる水深に制限があります。確実にメガネウオを見たい場合は、ライセンスを取ることをします。
日本のダイビングスポットの代表である伊豆の海では、スターゲイザーの一種であるメガネウオがよくみられます。メガネウオは、スターゲイザーの中でも特に浅い水深に生息する魚で、100mよりも深い場所にはいません。したがって、ダイビングで潜れる場所で見られるということです。
ダイビングは、体験だけならライセンスは必要ありませんが、潜れる水深に制限があります。確実にメガネウオを見たい場合は、ライセンスを取ることをします。
深海魚スターゲイザーの獲物の捕り方
スターゲイザーのエサの採り方を動画で見てみましょう。スターゲイザーは、一日中砂の中にもぐり餌となる小魚が来るのをじっと待っています。そして、少し開いた口から下あごについている突起物を出し入れします。これはアンコウもやる方法で、小魚となるゴカイを偽装した疑似餌の役割を果たしています。
そして、小魚が目の前まで近づいてきたら大きな口で一気に丸呑みします。動画では、自分の口の幅より大きな魚やタコまで捕食しています。スターゲイザーは、餌を採るために魚釣りをする魚とも言えるでしょう。
そして、小魚が目の前まで近づいてきたら大きな口で一気に丸呑みします。動画では、自分の口の幅より大きな魚やタコまで捕食しています。スターゲイザーは、餌を採るために魚釣りをする魚とも言えるでしょう。
スターゲイザーはおいしい魚!?
見た目は恐ろしい姿をしているスターゲイザーですが、おいしく食べることができる魚です。スターゲイザーは、積極的に漁で取ろうとすることはありませんが、網に紛れ込んでいることがありそれを調理します。
スターゲイザーの旬は、夏で刺身にするとおいしい白身魚です。しかし、どのような調理法でもおいしいとされています。煮つけ、鍋、天ぷら、唐揚げ、干物にして焼くなどさまざまな調理法に向いています。しかし、鮮度が早く落ちやすいのと鰓周辺にある棘に注意しなければなりません。
スターゲイザーの旬は、夏で刺身にするとおいしい白身魚です。しかし、どのような調理法でもおいしいとされています。煮つけ、鍋、天ぷら、唐揚げ、干物にして焼くなどさまざまな調理法に向いています。しかし、鮮度が早く落ちやすいのと鰓周辺にある棘に注意しなければなりません。
スターゲイザーはかっこいい魚なのか
初めて見た人の印象に強く残る独特な名前と見た目のスターゲイザーに対して、インターネット上ではさまざまな声が挙げられています。
長女が、おさかな図鑑の名前索引のページを見ながら 「スターゲイザーっていうかっこいい名前の魚がいる!英語で『星を見つめる者』って意味だって!超かっこいい!どんな魚…」 って言いながらスターゲイザーのページ見たらコイツが出てきて固まってる。
https://togetter.com/li/1028357
確かに、星を見つめるお魚ではある そして、絶対に名前負けしてる
https://togetter.com/li/1028357
スターゲイザーに対して「カッコイイ」「ロマンチスト」という称賛の声も上がっていますが、それは見た目ではなく「星を見つめる者」という英名に対して多く挙げられています。見た目に関しては「ブサイク」「名前負けしている」という声が上がっていることから、醜いことで有名な三島女郎が由来になったのも納得できるでしょう。
見た目に関してはあまりいい評価を得られていませんが、その身はおいしいということで「人は見た目によらない」「綺麗な花には棘がある」といった言葉に似ていると言っても良いでしょう。
見た目に関してはあまりいい評価を得られていませんが、その身はおいしいということで「人は見た目によらない」「綺麗な花には棘がある」といった言葉に似ていると言っても良いでしょう。
深海にすむ魚は面白い
今回は、深海魚スターゲイザーについて紹介しました。体の上部についている目やたくさんの歯が生えていることから「怖い」「独特」であるという印象を抱いた人も少なくないでしょう。スターゲイザーのこの独特の姿は、砂にもぐって獲物を待ち伏せし捕食するため、すなわち生きるために進化した結果です。
スターゲイザーだけでなく、近年はさまざまな深海魚が話題になっています。それらの最大の魅力は、スターゲイザーと同じく「独特の見た目をしている」点です。姿かたちを見るだけでも面白いですが、なぜそのような姿をしているのか考えながら見ると、さらに面白くなるのがスターゲイザーなどの深海魚です。
スターゲイザーだけでなく、近年はさまざまな深海魚が話題になっています。それらの最大の魅力は、スターゲイザーと同じく「独特の見た目をしている」点です。姿かたちを見るだけでも面白いですが、なぜそのような姿をしているのか考えながら見ると、さらに面白くなるのがスターゲイザーなどの深海魚です。