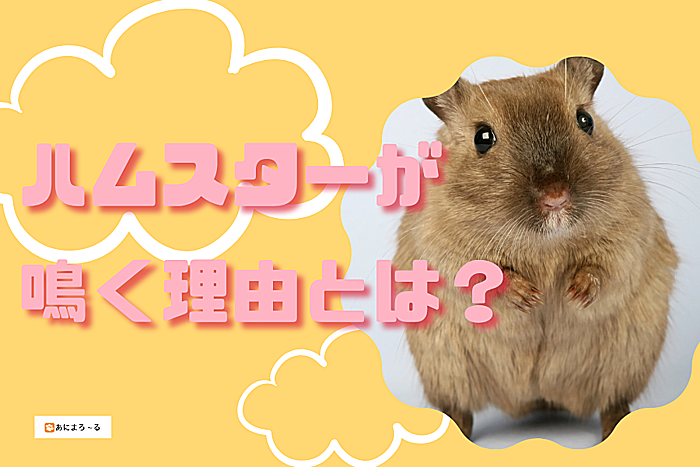ハムスターが鳴く理由とは?
ハムスターが鳴く理由を知っているでしょうか。鳴いている表情と意味を把握することでハムスターの気持ちを理解することができます。次に、ハムスターの鳴く理由を紹介します。
どのような意味で鳴いているのか知りたい人は参考にしてください。
どのような意味で鳴いているのか知りたい人は参考にしてください。
ハムスターが鳴く理由1:ストレスが溜まっている
ハムスターはストレスがたまると鳴くようになります。ストレスが原因で鳴いている場合はストレスを解消させてあげることで鳴き声を止めることができます。
ハムスターのストレスはさまざま考えられますが、運動不足や寝不足によることが多いです。運動不足の場合は、回し車の遊びをさせてあげると解決することができます。
ペットショップで比較的安く購入することが可能です。寝不足の原因は昼間に寝れる環境が整っていないことが原因であるため、音がしない場所にケージを移動させましょう。
ハムスターのストレスはさまざま考えられますが、運動不足や寝不足によることが多いです。運動不足の場合は、回し車の遊びをさせてあげると解決することができます。
ペットショップで比較的安く購入することが可能です。寝不足の原因は昼間に寝れる環境が整っていないことが原因であるため、音がしない場所にケージを移動させましょう。
ハムスターが鳴く理由2:威嚇している
ハムスターは威嚇する際にも鳴き声を発するようになります。鳴き声と表情を見れば威嚇していることを知ることができます。
威嚇している鳴き声を発している時に触れようとすると噛まれることもあるため、注意しましょう。
威嚇による鳴き声を辞めさせるためには、慣らし方をマスターすることをします。慣らし方はさまざまありますが、餌をあげたり、匂いを覚えさせることで徐々になれてきます。
威嚇する相手が飼い主だけとは限らず、多頭飼いをしている場合に喧嘩などが原因で威嚇し合うこともあります。
威嚇している鳴き声を発している時に触れようとすると噛まれることもあるため、注意しましょう。
威嚇による鳴き声を辞めさせるためには、慣らし方をマスターすることをします。慣らし方はさまざまありますが、餌をあげたり、匂いを覚えさせることで徐々になれてきます。
威嚇する相手が飼い主だけとは限らず、多頭飼いをしている場合に喧嘩などが原因で威嚇し合うこともあります。
ハムスターが鳴く理由3:何か要求している
ハムスターが何かを求めている際にも鳴き声を発します。何かを求めている際に発する鳴き声は飼い主のことを信頼している証拠でもあるため、ある程度信頼関係が築けています。
しかし、なにを求めているのかをハムスターの気持ちになって考える必要があります。求めている物はさまざまありますが、餌を欲しがっていたり、散歩に行きたいなどが考えられます。
エサをあげたばかりにも関わらず、甘えるような鳴き声をする場合は散歩の場合が多いです。また、ケージから出たがる場合は散歩に出してあげましょう。
しかし、なにを求めているのかをハムスターの気持ちになって考える必要があります。求めている物はさまざまありますが、餌を欲しがっていたり、散歩に行きたいなどが考えられます。
エサをあげたばかりにも関わらず、甘えるような鳴き声をする場合は散歩の場合が多いです。また、ケージから出たがる場合は散歩に出してあげましょう。
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち
ハムスターの鳴き声にはさまざまな種類があるため、ハムスターの気持ちになってどのような気持ちなのかを考えるようにしましょう。鳴き声の種類と気持ちを把握してあげることでより懐くようにもなります。
| 鳴き声 | 気持ち |
|---|---|
| ジージー・ギューギュー | 怒っている |
| キュッ | 怖がっている |
| キュッ・キュッ | 驚いている |
| キューキュー・チューチュー | 弱っている |
| チュチュ | 喜んでいる |
| クンクン | お腹が空いている |
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち1:怒っている時
ハムスターが怒るとジージーやギューギューなどの濁音が混じった鳴き声をするようになります。ハムスターはあまり鳴くことがない動物ですが、怒ると他の動物のように鳴き声を発します。
怒っている理由はさまざま考えられますが、ハムスター同士を同じケージ内で飼育すると発生しやすいです。特に、繁殖期にオス同士を入れてしまうと高い確率で怒りだします。
喧嘩になることも珍しいことではなく、怪我をしてしまうリスクもあるため、多頭飼いは控えましょう。なつかない状態の時でも怒りやすいため、手などを出さないようにしましょう。
怒っている理由はさまざま考えられますが、ハムスター同士を同じケージ内で飼育すると発生しやすいです。特に、繁殖期にオス同士を入れてしまうと高い確率で怒りだします。
喧嘩になることも珍しいことではなく、怪我をしてしまうリスクもあるため、多頭飼いは控えましょう。なつかない状態の時でも怒りやすいため、手などを出さないようにしましょう。
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち2:怖がっている時
ハムスターは驚いた場合や怖がっている場合にキュッっと鳴き声をあげます。比較的臆病な性格のハムスターの鳴き声であるため、性格の違いによって鳴く頻度が変わってきます。
性格はハムスターの種類によっても違いがあります。掃除をする際に驚かせてしまったり、不本意に大きな音を立ててしまうと怖がられてしまう可能性が高まります。
安心感を再び与えることができれば、怖がっている鳴き声をやめさせることができますが、一度嫌われてしまうとなかなかなついてくれない場合が多いです。
性格はハムスターの種類によっても違いがあります。掃除をする際に驚かせてしまったり、不本意に大きな音を立ててしまうと怖がられてしまう可能性が高まります。
安心感を再び与えることができれば、怖がっている鳴き声をやめさせることができますが、一度嫌われてしまうとなかなかなついてくれない場合が多いです。
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち3:驚いた時
ハムスターが驚いた際にも鳴き声を発しますが、上記でも紹介した怖がっている時と同じような鳴き声になります。
ハムスターの種類によって活発なハムスターもいますが、臆病なハムスターもいます。自身が飼っているハムスターの種類が臆病な性格の場合は、驚かせないように注意することが大切です。
驚かせてしまった場合は、無理に抱っこしたりするとより驚かせたり、怖がらせたりしてしまいます。
また、背後から触ることも驚かせてしまう原因です。懐かせることで驚く頻度を下げることも可能です。
ハムスターの種類によって活発なハムスターもいますが、臆病なハムスターもいます。自身が飼っているハムスターの種類が臆病な性格の場合は、驚かせないように注意することが大切です。
驚かせてしまった場合は、無理に抱っこしたりするとより驚かせたり、怖がらせたりしてしまいます。
また、背後から触ることも驚かせてしまう原因です。懐かせることで驚く頻度を下げることも可能です。
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち4:苦しんでいる時
ハムスターが苦しんでいる時は、キューキューやチューチューといった鳴き声になります。また、元気にキューキュー鳴くのではなく、元気なく間延びしたように鳴く特徴があります。
苦しんでいる原因はさまざまな考えられますが、素人では判断できない場合が多いです。そのため、キューキュー鳴いている場合は早めに病院に連れていくことをします。
病気以外でキューキュー鳴いている原因に老化の可能性もあります。
苦しんでいる原因はさまざまな考えられますが、素人では判断できない場合が多いです。そのため、キューキュー鳴いている場合は早めに病院に連れていくことをします。
病気以外でキューキュー鳴いている原因に老化の可能性もあります。
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち5:喜んでいる時
ハムスターが喜んでいる際にはキュッキュッやチュチュと鳴くようになります。
喜んでいる鳴き声を多く発するようになることはそれだけ飼い主との信頼関係が築かれている証拠でもあるため、かなり懐いている状態です。
キュッキュッと頻繁に鳴くようになればハムスターの飼い主として十分やるべきことをしている証しにもなります。
喜ぶ鳴き声を発する主な場面はエサをあげた際や散歩などでケージの外に出した時です。
喜ぶハムスターを見ればより可愛らしく思えるため、喜んでいる鳴き声をよく聞けるように飼育しましょう。
喜んでいる鳴き声を多く発するようになることはそれだけ飼い主との信頼関係が築かれている証拠でもあるため、かなり懐いている状態です。
キュッキュッと頻繁に鳴くようになればハムスターの飼い主として十分やるべきことをしている証しにもなります。
喜ぶ鳴き声を発する主な場面はエサをあげた際や散歩などでケージの外に出した時です。
喜ぶハムスターを見ればより可愛らしく思えるため、喜んでいる鳴き声をよく聞けるように飼育しましょう。
ハムスターの鳴き声の種類と気持ち6:お腹が空いている時
ハムスターがエサを求める際には、クンクンと鳴きます。特に、飼い主が近づいた際に鳴くことが多く、エサを与えることで鳴きやみます。
しかし、ハムスターは巣箱にエサを蓄える習慣があるため、与えれば与えるほど口に含んで巣箱に持ち帰ってしまいます。
そのようなことを続けていると肥満体形になる原因になります。クンクン鳴くときはお腹が空いている気持ちのあらわれですが、与えすぎには注意しましょう。
エサをねだるような行為をすることはそれだけ飼い主になれている証拠でもあります。
しかし、ハムスターは巣箱にエサを蓄える習慣があるため、与えれば与えるほど口に含んで巣箱に持ち帰ってしまいます。
そのようなことを続けていると肥満体形になる原因になります。クンクン鳴くときはお腹が空いている気持ちのあらわれですが、与えすぎには注意しましょう。
エサをねだるような行為をすることはそれだけ飼い主になれている証拠でもあります。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法
ハムスターが鳴き声を発する種類は、シチュエーションによって分けることができます。場合によっては鳴き声に対処することに困ることもあります。
次に、ハムスターが鳴いている状況別の対処方法を紹介します。
次に、ハムスターが鳴いている状況別の対処方法を紹介します。
| 鳴いている時の状況 | 鳴き声 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 散歩中 | チュチュ・キュキュ | 喜んでいるので様子見 |
| 寝ている時 | クック | いびきなので様子見 |
| 過敏性反応が出ている時 | スースー・プスプス | ひどい場合は病院に連れていく |
| 発情期 | ギーギー | 個別に飼育する |
| 喧嘩している時 | ヂュー | 個別に飼育する |
| 遊んでいる時 | チュチュ・lキュキュ | 遊んであげる |
| 多頭飼いしている時 | ジージー | 個別に飼育する |
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法1:散歩中の時
ハムスターを散歩させることでストレス解消をしたり、運動不足を解消する効果があります。
また、より懐くようにもなりやすいため、飼い始めてからある程度期間がたてば散歩をさせることができようになります。
散歩する際に鳴いている主な原因は、なれていない場所による警戒心や好奇心です。今までに複数回散歩をしていれば喜んでいる気持ちのあらわれとして鳴くこともあります。
警戒心で鳴いている場合は、なれれば鳴かなくなるため、しばらく様子見をするようにしましょう。
また、より懐くようにもなりやすいため、飼い始めてからある程度期間がたてば散歩をさせることができようになります。
散歩する際に鳴いている主な原因は、なれていない場所による警戒心や好奇心です。今までに複数回散歩をしていれば喜んでいる気持ちのあらわれとして鳴くこともあります。
警戒心で鳴いている場合は、なれれば鳴かなくなるため、しばらく様子見をするようにしましょう。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法2:寝ている時
寝ている時に鳴いている場合は、いびきであるため、見守ることをします。
疲れている時にクックッといびきをかきますが、熟睡している証拠であるため、特に対処することはありません。
必要以上に心配して起こしてしまう方が睡眠不足になる恐れがあり、しません。熟睡している時にはクックッと鳴きますが、怖い夢などを見ているとジージーと鳴きます。
熟睡している時と同じように何もする必要はありませんが、うなるように鳴いている場合は起こしてあげることも優しさの一つです。
疲れている時にクックッといびきをかきますが、熟睡している証拠であるため、特に対処することはありません。
必要以上に心配して起こしてしまう方が睡眠不足になる恐れがあり、しません。熟睡している時にはクックッと鳴きますが、怖い夢などを見ているとジージーと鳴きます。
熟睡している時と同じように何もする必要はありませんが、うなるように鳴いている場合は起こしてあげることも優しさの一つです。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法3:過敏性反応が出ている時
ハムスターは過敏性反応や風邪を引くとスースーやプスプスという鳴き声を発します。過敏性反応の場合は過敏性反応の原因を突き止め、解決することで鳴きやませることができます。
ハムスターがよく発症する過敏性反応の中にハウスダストが含まれています。
ハウスダストは人間でも起きる過敏性反応であり、部屋などを掃除してほこりやごみをなくすことで解決する場合が多いです。
しかし、長引くようなら病院に行くことをします。
ハムスターがよく発症する過敏性反応の中にハウスダストが含まれています。
ハウスダストは人間でも起きる過敏性反応であり、部屋などを掃除してほこりやごみをなくすことで解決する場合が多いです。
しかし、長引くようなら病院に行くことをします。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法4:発情期の時
発情期になるとメスはオスを呼ぶためにギーギーと鳴くようになります。オスは鳴くことがないため、できるだけ静かに飼育したい場合はオスを購入することをします。
発情しているメスに対して鳴きやますことは実質無理であるため、多頭飼いをしている場合は個別に飼育するようにしましょう。
また、鳴き声が気になる場合は少し離れた室内に移動することもします。発情期を過ぎれば鳴かなくなるため、待つことが最大の対処方法でもあります。
発情しているメスに対して鳴きやますことは実質無理であるため、多頭飼いをしている場合は個別に飼育するようにしましょう。
また、鳴き声が気になる場合は少し離れた室内に移動することもします。発情期を過ぎれば鳴かなくなるため、待つことが最大の対処方法でもあります。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法5:喧嘩している時
ハムスターを多頭飼いしていると喧嘩をしてしまいやすくなり、ヂューと激しく鳴きあいます。
一度喧嘩が始まってしまうと、どちらかがぼろぼろになるまで続けてしまうため、早急にケージを分けることをします。
飼い主自身も怪我をしてしまうリスクがあり、注意しましょう。特に、発情期や新しく仲間に加える際に喧嘩が発生しやすくなります。
一度喧嘩が始まってしまうと、どちらかがぼろぼろになるまで続けてしまうため、早急にケージを分けることをします。
飼い主自身も怪我をしてしまうリスクがあり、注意しましょう。特に、発情期や新しく仲間に加える際に喧嘩が発生しやすくなります。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法6:遊んでいる時
遊んでいる時に鳴くことがありますが、喜んでいる証拠や興奮している証拠でもあるため、特に対処する必要はありません。散歩や砂遊びをさせると鳴くことが多いです。
思う存分遊ばせてあげることはストレス発散にもつながるため、無理に止めてしまうと逆効果になってしまいます。暴れまわることもあるため、周りには注意を払いましょう。
思う存分遊ばせてあげることはストレス発散にもつながるため、無理に止めてしまうと逆効果になってしまいます。暴れまわることもあるため、周りには注意を払いましょう。
シチュエーション別ハムスターが鳴いている時の対処法7:多頭飼いを始めた時
多頭飼いする際に新入りは周りの環境に慣れていないため、鳴くことが多いです。しかし、なれれば次第に鳴かなくなるため、見守るようにしましょう。
上記でも紹介したように喧嘩をしてしまう可能性もあるため、頻繁に様子をうかがうことをします。
多頭飼いをする場合は鳴き声や喧嘩にも注意する必要がありますが、繁殖に対する配慮や対策も考えるようにしましょう。
上記でも紹介したように喧嘩をしてしまう可能性もあるため、頻繁に様子をうかがうことをします。
多頭飼いをする場合は鳴き声や喧嘩にも注意する必要がありますが、繁殖に対する配慮や対策も考えるようにしましょう。
ハムスターの鳴き声で気持ちを判断しよう
ハムスターの鳴き声で気持ちを把握することができ、仲良くなるきっかけにもなります。ハムスターを懐かせるためにはまず、鳴き声の種類と気持ちを把握することをします。
気持ちを把握するとともに対処方法を学ぶことでハムスターと一気に仲良しになることができます。
ハムスターを飼育することが初めての場合やなかなかなついてくれない人は鳴き声の意味を理解するようにしましょう。
気持ちを把握するとともに対処方法を学ぶことでハムスターと一気に仲良しになることができます。
ハムスターを飼育することが初めての場合やなかなかなついてくれない人は鳴き声の意味を理解するようにしましょう。