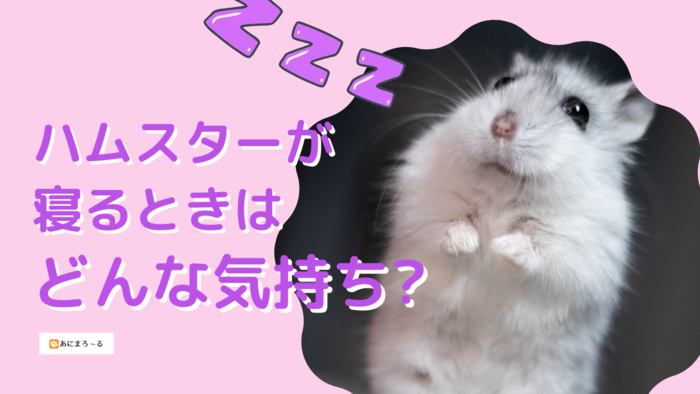行動で見るハムスターの気持ち
ハムスターが寝るときはどんな気持ちなのでしょう。寝るのだからリラックスしているのでしょうか、寝るほど疲れているのでしょうか。
ハムスターの行動はどれもかわいいものばかりですが、警戒心や不快感のサインのこともあるため、気持ちを読み取ってあげましょう。
ハムスターの行動はどれもかわいいものばかりですが、警戒心や不快感のサインのこともあるため、気持ちを読み取ってあげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち
- 耳が寝ている
- 耳がピンとしている
- 体を伸ばして寝る
- 寝ながら食べる
- 鼻をヒクヒクさせる
- フンを食べる
- フンを飛ばす
- 立ち上がってキョロキョロする
- 手を噛む
- キーキー、ジージー鳴く
- はいつくばってウロウロする
- すぐに背中を見せる
- 回し車で突然止まる
- 自分のシッポを追いかける
- 一点を見つめる
- うんていをする
- 後ろ足で立って耳を澄ます
- 死んだふりをする
行動で見るハムスターの気持ち1:耳が寝ている
ハムスターが行動を取る時に耳が立つか寝るかを見ることは、気持ちを読み取るためのポイントです。
ハムスターの耳が寝ている時は、リラックスしている状態です。ですから、寝る時には耳も寝ることが多いでしょう。
また、穴掘りをしたり、何かをかじったりと、夢中になって集中している時にも耳が寝るのを見ることができるでしょう。
周囲を警戒している時は耳を使いますから、耳が寝るのは警戒モードも寝ている状態と言えるでしょう。ハムスターの耳が寝るのを見たら、そっとしておいてあげましょう。
ハムスターの耳が寝ている時は、リラックスしている状態です。ですから、寝る時には耳も寝ることが多いでしょう。
また、穴掘りをしたり、何かをかじったりと、夢中になって集中している時にも耳が寝るのを見ることができるでしょう。
周囲を警戒している時は耳を使いますから、耳が寝るのは警戒モードも寝ている状態と言えるでしょう。ハムスターの耳が寝るのを見たら、そっとしておいてあげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち2:耳がピンとしている
ハムスターの寝る耳と双璧をなすかわいさの耳が、ピンと立てた耳です。ハムスターの耳がピンとしている時は、気になる音に注意を向けている状態です。
ハムスターの聴覚は、敵がいることを瞬時に知るために、とても発達しています。人間には聞き取れないような音でも、ハムスターには聞き取ることができます。
ピンと立てた耳は、見た目はかわいいですが、生き残るためにハムスターに秘められた能力を発揮している場面であると言えるでしょう。
ハムスターの聴覚は、敵がいることを瞬時に知るために、とても発達しています。人間には聞き取れないような音でも、ハムスターには聞き取ることができます。
ピンと立てた耳は、見た目はかわいいですが、生き残るためにハムスターに秘められた能力を発揮している場面であると言えるでしょう。
行動で見るハムスターの気持ち3:体を伸ばして寝る
ハムスターが体を伸ばして寝るのは、人間が寝る時と同じで、疲れている時とリラックスしている時の両方があります。
暑い夏の時期など、ハムスターが疲れていることが考えられる場合には、環境を見直してあげましょう。
そうでなければ、ハムスターは飼い主の方にすっかり懐いて、安心して寝ることができるようになったということでしょう。
おなかを出して寝るのは、とてもリラックスできている状態です。飼い始めの頃はなかなか見ることができませんが、長く大切に飼っていると見せてくれるようになるでしょう。
暑い夏の時期など、ハムスターが疲れていることが考えられる場合には、環境を見直してあげましょう。
そうでなければ、ハムスターは飼い主の方にすっかり懐いて、安心して寝ることができるようになったということでしょう。
おなかを出して寝るのは、とてもリラックスできている状態です。飼い始めの頃はなかなか見ることができませんが、長く大切に飼っていると見せてくれるようになるでしょう。
行動で見るハムスターの気持ち4:寝ながら食べる
ハムスターが寝ながら餌を食べているのを見ると、寝るか食べるかどちらかにしなさいとしつけをしたくなる方もあるでしょう。
ハムスターは敵のいない安全な巣穴で餌を食べる習性があり、寝ながら餌を食べるのも、だらしないのではなく、げっ歯類の本能からの行動であり、生き残るための知恵であると言えます。
警戒心の強いハムスターですから、寝るというリラックス状態では、安心して餌を食べられるのでしょう。ほお袋に餌をため込んだまま寝るハムスターを見ても、あたたかく見守ってあげましょう。
ハムスターは敵のいない安全な巣穴で餌を食べる習性があり、寝ながら餌を食べるのも、だらしないのではなく、げっ歯類の本能からの行動であり、生き残るための知恵であると言えます。
警戒心の強いハムスターですから、寝るというリラックス状態では、安心して餌を食べられるのでしょう。ほお袋に餌をため込んだまま寝るハムスターを見ても、あたたかく見守ってあげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち5:鼻をヒクヒクさせる
ハムスターは耳と同じく鼻も発達していて、人間以上ににおいに敏感です。ハムスターは、鼻をヒクヒクさせてにおいを嗅ぐことで、さまざまな情報収集をしています。
餌や飼い主の情報も鼻で感知します。また、ハムスターは縄張り意識の強い動物で、縄張りには自分のにおいを付けています。
においはハムスターにとって重要な情報源です。普段から鼻に注目してあげて、食品などの強いにおいの出る物には注意するようにしていて下さい。
もし、鼻に異常があるようなら、すぐに病院へ連れて行ってあげましょう。
餌や飼い主の情報も鼻で感知します。また、ハムスターは縄張り意識の強い動物で、縄張りには自分のにおいを付けています。
においはハムスターにとって重要な情報源です。普段から鼻に注目してあげて、食品などの強いにおいの出る物には注意するようにしていて下さい。
もし、鼻に異常があるようなら、すぐに病院へ連れて行ってあげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち6:フンを食べる
ハムスターがフンを食べるのを初めて見ると、とても驚くことでしょう。
ハムスターがフンを食べるのは、食糞行動と言い、栄養を効率よく摂取するために必要なことであり、ハムスターの習性ですので、心配はありません。
ハムスターは、通常のフンとは別に盲腸糞と呼ばれるフンをします。盲腸糞は、食物繊維などを盲腸で分解したもので、一度の食事で摂取しきれなかった栄養を摂取することができます。
餌が足りないからフンを食べるのではなく、餌が十分でもフンを食べます。無理にやめさせると、ストレスになることがありますので、注意して下さい。
ハムスターがフンを食べるのは、食糞行動と言い、栄養を効率よく摂取するために必要なことであり、ハムスターの習性ですので、心配はありません。
ハムスターは、通常のフンとは別に盲腸糞と呼ばれるフンをします。盲腸糞は、食物繊維などを盲腸で分解したもので、一度の食事で摂取しきれなかった栄養を摂取することができます。
餌が足りないからフンを食べるのではなく、餌が十分でもフンを食べます。無理にやめさせると、ストレスになることがありますので、注意して下さい。
行動で見るハムスターの気持ち7:フンを飛ばす
ハムスターがフンを食べるのも驚きですが、フンを飛ばすこともあります。
このハムスターがフンを飛ばすという行動にも何か深い意味がありそうですが、深い意味はありません。ハムスターがフンを飛ばすのは、退屈しのぎに遊んでいるだけです。
一見、何かに不満があるようにも思えますが、退屈しのぎに遊んでいるということはリラックス状態ですから、心配することはありません。汚いからやめさないとしつけようとしたりせず、見守っていてあげると良いでしょう。
このハムスターがフンを飛ばすという行動にも何か深い意味がありそうですが、深い意味はありません。ハムスターがフンを飛ばすのは、退屈しのぎに遊んでいるだけです。
一見、何かに不満があるようにも思えますが、退屈しのぎに遊んでいるということはリラックス状態ですから、心配することはありません。汚いからやめさないとしつけようとしたりせず、見守っていてあげると良いでしょう。
行動で見るハムスターの気持ち8:立ち上がってキョロキョロする
ハムスターが立ち上がってキョロキョロしている時は、周囲を警戒している状態で、耳や鼻を使って情報を収集しています。
人間なら、立ち上がってキョロキョロする時は主に目で情報収集をしますが、ハムスターは目があまりよくなく、耳や鼻での情報収集となります。
ハムスターが立ち上がってキョロキョロしている様子はとてもかわいいですが、実は重大な仕事をしているのですから、驚かせたりしないであげましょう。
人間なら、立ち上がってキョロキョロする時は主に目で情報収集をしますが、ハムスターは目があまりよくなく、耳や鼻での情報収集となります。
ハムスターが立ち上がってキョロキョロしている様子はとてもかわいいですが、実は重大な仕事をしているのですから、驚かせたりしないであげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち9:手を噛む
ハムスターが手を噛むのは、噛んで確認しているだけですが、痛いほど強く噛む場合は、怖がっている時です。
甘噛みなら、食べ物かどうか確認しているのでしょうから心配ありません。ですが、痛いほど強く噛まれたら、ハムスターを怖がらせたり驚かせたりしたと考えられます。
思い当たることがない場合は、たまたまハムスターが寝るところで、寝ぼけて噛みついただけということもあります。
ですが、懐いていたのに急に噛みつくようになった場合、病気やけがの可能性もありますから、異常を感じたら病院に連れて行ってあげて下さい。
甘噛みなら、食べ物かどうか確認しているのでしょうから心配ありません。ですが、痛いほど強く噛まれたら、ハムスターを怖がらせたり驚かせたりしたと考えられます。
思い当たることがない場合は、たまたまハムスターが寝るところで、寝ぼけて噛みついただけということもあります。
ですが、懐いていたのに急に噛みつくようになった場合、病気やけがの可能性もありますから、異常を感じたら病院に連れて行ってあげて下さい。
行動で見るハムスターの気持ち10:キーキー、ジージー鳴く
ハムスターがキーキー、ジージー鳴くのは、怒っているサインです。飼い始めたばかりで慣れていない時や、嫌がることをされた時に、キーキー、ジージーと鳴くことがあります。
仰向けに寝る状態で鳴いている場合は、ハムスターがとても嫌がっています。かわいいからもっと見ていたくなっても、すぐにやめてあげて下さい。
鳴き止まない場合は、病気の可能性もありますから、病院に連れて行ってあげましょう。
仰向けに寝る状態で鳴いている場合は、ハムスターがとても嫌がっています。かわいいからもっと見ていたくなっても、すぐにやめてあげて下さい。
鳴き止まない場合は、病気の可能性もありますから、病院に連れて行ってあげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち11:はいつくばってウロウロする
ハムスターは縄張り意識が強いです。自分のにおいを付けて縄張りを広げていきます。
ハムスターにとって、自分のにおいが付いていない場所は縄張りの外であり、未知の場所なので、はいつくばってウロウロします。
人間にも、未知の場所では警戒して、低い姿勢になって危険を察知しようとする場面がありますが、それと似たようなことだと理解してあげましょう。
初めは心配になるでしょうが、慣れてきたらしなくなりますから、見守ってあげて下さい。
ハムスターにとって、自分のにおいが付いていない場所は縄張りの外であり、未知の場所なので、はいつくばってウロウロします。
人間にも、未知の場所では警戒して、低い姿勢になって危険を察知しようとする場面がありますが、それと似たようなことだと理解してあげましょう。
初めは心配になるでしょうが、慣れてきたらしなくなりますから、見守ってあげて下さい。
行動で見るハムスターの気持ち12:すぐに背中を見せる
ハムスターをてのひらに乗せたときに、すぐに背中を見せるのは、怖がっているからです。
ハムスターの目は敵を見つけやすいように上向きについています。ですから、てのひらに乗せるときは、上からつかむとびっくりしてしまいますので、注意しましょう。
餌を食べるときに背中を見せるのは、餌を取られると警戒しているからです。なんともかわいいですが、いじわるせず、ゆっくり食べさせてあげましょう。
ハムスターの目は敵を見つけやすいように上向きについています。ですから、てのひらに乗せるときは、上からつかむとびっくりしてしまいますので、注意しましょう。
餌を食べるときに背中を見せるのは、餌を取られると警戒しているからです。なんともかわいいですが、いじわるせず、ゆっくり食べさせてあげましょう。
行動で見るハムスターの気持ち13:回し車で突然止まる
回し車で元気に走っていたハムスターが突然止まると、何かあったのかと不安になるでしょうが、野生の名残で今の状況を確認するために止まっただけなので、心配はいりません。
野生のハムスターはとても活動的でたくさん移動をしますので、どこまで来たかや、敵がいないかを確認するために立ち止まることがあります。
ペットのハムスターもその名残で止まることがあります。この理屈から言えば、ハムスターは回し車では立ち止まる必要はないのでしょうが、かわいいですし、安心して見てあげて下さい。
野生のハムスターはとても活動的でたくさん移動をしますので、どこまで来たかや、敵がいないかを確認するために立ち止まることがあります。
ペットのハムスターもその名残で止まることがあります。この理屈から言えば、ハムスターは回し車では立ち止まる必要はないのでしょうが、かわいいですし、安心して見てあげて下さい。
行動で見るハムスターの気持ち14:自分のシッポを追いかける
ハムスターが自分のシッポを追いかけてぐるぐると回る場合は、病気の可能性があります。
中耳炎や内耳炎の疑いがあります。お散歩中に高い所から落ちてしまった後に、自分のシッポを追いかけてぐるぐると回るようになったとしたら、大けがをしている可能性も考えられます。
いずれにしても、すぐに病院へ連れていってあげましょう。
中耳炎や内耳炎の疑いがあります。お散歩中に高い所から落ちてしまった後に、自分のシッポを追いかけてぐるぐると回るようになったとしたら、大けがをしている可能性も考えられます。
いずれにしても、すぐに病院へ連れていってあげましょう。
行動で見るムスターの気持ち15:一点を見つめる
ハムスターは目がよくないため、一点を見つめていたとしても、単純に今の状況を確認しようとしているだけでしょう。
ハムスターにじっと見つめられたら、何か伝えようとしているのかなと気になるでしょうが、深い意味はないでしょう。人間でも近眼の人が、見えにくい物を見ようとしている様子をイメージすると分かりやすいです。
また、人間と同じように、驚いて体の動きが固まってしまった時に、視線も固まってしまうこともあります。
ハムスターにじっと見つめられたら、何か伝えようとしているのかなと気になるでしょうが、深い意味はないでしょう。人間でも近眼の人が、見えにくい物を見ようとしている様子をイメージすると分かりやすいです。
また、人間と同じように、驚いて体の動きが固まってしまった時に、視線も固まってしまうこともあります。
行動で見るハムスターの気持ち16:うんていをする
ハムスターがケージによじ登ってうんていをすることがありますが、危険なので、環境を見直すなどして、やめさせてあげましょう。
餌を欲しがる時や、運動不足解消やストレス解消をしたい時に、ハムスターはうんていをすることがあります。見ているとかわいいのですが、ケージに挟まったり、落ちたりすることがあり、危ないです。
うんていの防止には、登れないように、金網を使わないケージに変えてあげるのが一番でしょう。もちろん、餌や運動、ストレスを管理してあげるのも有効です。
餌を欲しがる時や、運動不足解消やストレス解消をしたい時に、ハムスターはうんていをすることがあります。見ているとかわいいのですが、ケージに挟まったり、落ちたりすることがあり、危ないです。
うんていの防止には、登れないように、金網を使わないケージに変えてあげるのが一番でしょう。もちろん、餌や運動、ストレスを管理してあげるのも有効です。
行動で見るハムスターの気持ち17:後ろ足で立って耳を澄ます
ハムスターが後ろ足で立って耳を澄ますのは警戒している時で、あやしい物音がしないか探っています。
後ろ足で立って口を開けて歯を見せると、威嚇のポーズです。後ろ足で立つことで体を大きく見せようとしているのでしょう。熊の威嚇にも似ています。
威嚇されたら怖がっているということですから、不安を取り除いてあげるようにしましょう。急に触ろうとしたり、ケージを乱暴に掃除したり、大きな音を立てたりしないように注意して下さい。
後ろ足で立って口を開けて歯を見せると、威嚇のポーズです。後ろ足で立つことで体を大きく見せようとしているのでしょう。熊の威嚇にも似ています。
威嚇されたら怖がっているということですから、不安を取り除いてあげるようにしましょう。急に触ろうとしたり、ケージを乱暴に掃除したり、大きな音を立てたりしないように注意して下さい。
行動で見るハムスターの気持ち18:死んだふりをする
ハムスターが死んだふりをするのは、死ぬほど驚いた時であると考えられ、とても危険なことです。
人間よりずっと耳の良いハムスターにとって、大きな音は私たちが想像できないほど怖いはずですから、死んだふりをしているというよりも、怖すぎて死にかけていると考えてあげて下さい。
死んだふりがかわいいからと、大きな音でハムスターを驚かせることは絶対にしないようにして下さい。病気になるだけではなく、本当に死んでしまうこともありえます。
人間よりずっと耳の良いハムスターにとって、大きな音は私たちが想像できないほど怖いはずですから、死んだふりをしているというよりも、怖すぎて死にかけていると考えてあげて下さい。
死んだふりがかわいいからと、大きな音でハムスターを驚かせることは絶対にしないようにして下さい。病気になるだけではなく、本当に死んでしまうこともありえます。
ハムスターの愛情表現
警戒心の強いハムスターの愛情表現は、警戒しないこと、つまり近づいてきてくれることです。
あまがみしてくれるハムスターもかわいいのですが、残念ながらハムスターには愛情をあまがみで表現する習性はありません。
あまがみしてくれるハムスターもかわいいのですが、残念ながらハムスターには愛情をあまがみで表現する習性はありません。
ハムスターの愛情表現1:近づいてくる
警戒心の強いハムスターは、鋭い聴覚と嗅覚でいつも敵から距離を取ろうとします。
ハムスターが飼い主に近づいてくるのは、その声やにおいから敵ではなく味方だと判断したということであり、ハムスターの愛情表現であると言えます。
ハムスターは視力と記憶力があまりよくないので、声とにおいを毎日覚えさせてあげましょう。
ハムスターが飼い主に近づいてくるのは、その声やにおいから敵ではなく味方だと判断したということであり、ハムスターの愛情表現であると言えます。
ハムスターは視力と記憶力があまりよくないので、声とにおいを毎日覚えさせてあげましょう。
ハムスターの愛情表現2:あまがみ
甘えて噛むあまがみはかわいいのですが、ハムスターの場合は、愛情表現としてあまがみをする習性がないので、残念ながら確認のために噛んだだけでしょう。
ハムスターのあまがみは、驚いて反射的に噛んでしまったり、よく見えなくて噛んでしまったりすることがほとんどでしょう。強く噛まれたのでなければ、それほど気にせず許してあげましょう。
ハムスターのあまがみは、驚いて反射的に噛んでしまったり、よく見えなくて噛んでしまったりすることがほとんどでしょう。強く噛まれたのでなければ、それほど気にせず許してあげましょう。
ハムスターの行動から気持ちを読み取ってあげよう
ハムスターの行動から気持ちを読み取ってあげて懐いてもらうには「警戒心」から取る行動がポイントで、それらを取り除いてあげるようにすると良いでしょう。
懐いていることがわかる行動としては「寝る」行動がポイントで、耳が寝る、おなかを見せて寝るなどの行動から、気を許してくれていることが分かります。
ハムスターの武器である耳や鼻を使っている時は警戒モード、おなかを見せて寝るのはリラックスモードと言えるでしょう。
ハムスターは何をしてもかわいいので、いろんな行動を見ていたくなりますが、危険な行動は避けることが、より長くそのかわいさを堪能できることにつながります。
懐いていることがわかる行動としては「寝る」行動がポイントで、耳が寝る、おなかを見せて寝るなどの行動から、気を許してくれていることが分かります。
ハムスターの武器である耳や鼻を使っている時は警戒モード、おなかを見せて寝るのはリラックスモードと言えるでしょう。
ハムスターは何をしてもかわいいので、いろんな行動を見ていたくなりますが、危険な行動は避けることが、より長くそのかわいさを堪能できることにつながります。