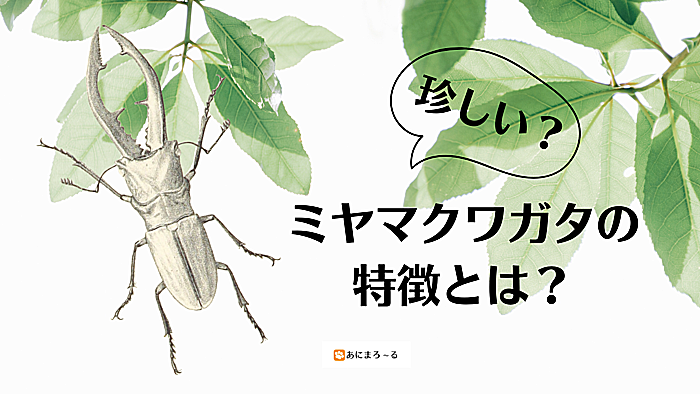「珍しいミヤマクワガタはどこに生息しているの?」
「ミヤマクワガタについて詳しく知りたい。」
「ミヤマクワガタの飼育は難しい?」
クワガタやカブトムシ好きも憧れるミヤマクワガタに、上記のような疑問を持たれているのではないでしょうか?
本記事では、ミヤマクワガタの詳しい生態についてご紹介しています。ミヤマクワガタの生息する場所や、体の特徴、飼育の仕方まで記載していますので、飼育してみたいという方はご一読ください。
ミヤマクワガタのオスは、他のクワガタに比べると、少し特徴的な姿をしていますが、メスは全く違った形をしていて、その点も非常に魅力的です。このメスの特徴についても載せていますので、あまり興味がなかった方も、これを読めば注目したくなるでしょう。
魅力を知ると、会ってみたくなること間違いなしです。是非飼育などもご検討ください。
「ミヤマクワガタについて詳しく知りたい。」
「ミヤマクワガタの飼育は難しい?」
クワガタやカブトムシ好きも憧れるミヤマクワガタに、上記のような疑問を持たれているのではないでしょうか?
本記事では、ミヤマクワガタの詳しい生態についてご紹介しています。ミヤマクワガタの生息する場所や、体の特徴、飼育の仕方まで記載していますので、飼育してみたいという方はご一読ください。
ミヤマクワガタのオスは、他のクワガタに比べると、少し特徴的な姿をしていますが、メスは全く違った形をしていて、その点も非常に魅力的です。このメスの特徴についても載せていますので、あまり興味がなかった方も、これを読めば注目したくなるでしょう。
魅力を知ると、会ってみたくなること間違いなしです。是非飼育などもご検討ください。
ミヤマクワガタは珍しい昆虫なのか
ミヤマクワガタというと、珍しいイメージがあるようです。クワガタ自体、緑の多い場所にしか生息していないので、都会で目にすることはできません。
加えてミヤマクワガタは、他のクワガタと違って昼間に行動することが多く、クワガタを採集するときによく行う夜間の昆虫採集時は見つけるのは困難です。
ただミヤマクワガタが生息している場所に、珍しいと言われるヒントがあります。比較的涼しい場所を好むミヤマクワガタは、近年温暖化に伴い数が減少している可能性もあるようです。涼しい場所を求めて北上し、そこに多数生息していることも確認されています。
今後絶滅を心配されていて、生息域の環境調査のため、指標昆虫になっているようです。
加えてミヤマクワガタは、他のクワガタと違って昼間に行動することが多く、クワガタを採集するときによく行う夜間の昆虫採集時は見つけるのは困難です。
ただミヤマクワガタが生息している場所に、珍しいと言われるヒントがあります。比較的涼しい場所を好むミヤマクワガタは、近年温暖化に伴い数が減少している可能性もあるようです。涼しい場所を求めて北上し、そこに多数生息していることも確認されています。
今後絶滅を心配されていて、生息域の環境調査のため、指標昆虫になっているようです。
ミヤマクワガタと呼ばれる由来
ミヤマクワガタは、漢字で「深山」と書きます。その名の通り、山の深い場所に生息しているのでこう呼ばれるようになりました。
手入れがされていない、自然が残る山奥が好きなミヤマクワガタなので、見つけるのが難しいと言われるのかもしれません。また気温が低い土地では、山奥でなくてもミヤマクワガタを見ることができるようです。
手入れがされていない、自然が残る山奥が好きなミヤマクワガタなので、見つけるのが難しいと言われるのかもしれません。また気温が低い土地では、山奥でなくてもミヤマクワガタを見ることができるようです。
ミヤマクワガタの生息地
ミヤマクワガタは一部の離島や南西諸島を除いて、ほぼ日本全土に生息しています。特に湿度の高い涼しい場所を好み、幼虫も単なる朽木ではなく、腐食した朽木で成長します。この条件を満たしているのが、標高の高い山奥というわけです。
ミヤマクワガタには、2亜種存在が確認されています。一般的に見られるミヤマクワガタと、伊豆諸島に生息するイズミヤマクワガタで、オスの頭部と耳状突起がイズミヤマクワガタの方はあまり発達していません。
伊豆半島のそれぞれの島の中でも、若干個体の違いがあるようです。
ミヤマクワガタには、2亜種存在が確認されています。一般的に見られるミヤマクワガタと、伊豆諸島に生息するイズミヤマクワガタで、オスの頭部と耳状突起がイズミヤマクワガタの方はあまり発達していません。
伊豆半島のそれぞれの島の中でも、若干個体の違いがあるようです。
珍しいと言われがちなミヤマクワガタの特徴
#ミヤマクワガタ がこんなに長生きしたの、初めてです?
— 和根崎剛 (@OVw2fuxiBKmQ46E) September 29, 2022
しかも、ペアで☀️
ということは、卵は期待できないかな…? pic.twitter.com/M3zi9XIxLT
ミヤマクワガタが珍しいと言われる理由は、生息地が行きづらい場所だからだけではありません。ミヤマクワガタの姿形にも、他とは違う魅力がたくさんあります。
ここからは、体の作りについてご説明します。他のクワガタにはない、珍しいチャームポイントも押さえておきましょう。
- 体に毛が生えている
- 顎や足の力が強い
- 体の大きさに個体差がある
体に毛が生えている
ミヤマクワガタのオスの体表には、細かい産毛が生えています。この毛によって、体色が金色や褐色に見えるのです。ミヤマクワガタの体色は艶がなく、木に擬態して目立たない効果があります。
また若い個体には産毛が多数見られますが、老齢になるとこの産毛が抜け落ちて、ほとんど見られない個体もあるようです。
メスの体表には毛がありませんが、腹側に産毛が生えています。
また若い個体には産毛が多数見られますが、老齢になるとこの産毛が抜け落ちて、ほとんど見られない個体もあるようです。
メスの体表には毛がありませんが、腹側に産毛が生えています。
顎や足の力が強い
ミヤマクワガタのオスの大顎は、エゾ型、ヤマ型(基本型)、サト型(フジ型)の3種類に分けられています。顎の先端が二股に分かれていますが、その大きさと、第一内歯と第三内歯の長さで種類を分けています。
顎の先端が鋭利であり、挟む力も強いので、怪我をしないように注意が必要です。
また足の力が非常に強いので、木の表面に這っているミヤマクワガタを剥がそうとしてもなかなか引き剥がすことができません。足を一本つずゆっくり剥がしていくと取れるので、無理に引き剥がそうとしないことがポイントです。
顎の先端が鋭利であり、挟む力も強いので、怪我をしないように注意が必要です。
また足の力が非常に強いので、木の表面に這っているミヤマクワガタを剥がそうとしてもなかなか引き剥がすことができません。足を一本つずゆっくり剥がしていくと取れるので、無理に引き剥がそうとしないことがポイントです。
体の大きさに個体差がある
ミヤマクワガタに限らずクワガタは、幼虫の時の育った環境や餌の量によって、成虫になった時の大きさが変わります。単純に大きさや顎の形が違うだけでなく、ミヤマクワガタのオスには他のクワガタにはない珍しい特徴があるのです。
オスの頭部には耳状突起と呼ばれる張り出した部分があります。この突起が大型の個体であればある程はっきり大きく突き出しています。
逆に小型のミヤマクワガタは、この突起が目立たず、ミヤマクワガタと見分けるのも難しいくらい他のクワガタと同じような姿になります。
大きいものは8cm近くにもなり、小さいものは3cm程度と、同じ種類とは思えないほど違いがあるので面白いです。
オスの頭部には耳状突起と呼ばれる張り出した部分があります。この突起が大型の個体であればある程はっきり大きく突き出しています。
逆に小型のミヤマクワガタは、この突起が目立たず、ミヤマクワガタと見分けるのも難しいくらい他のクワガタと同じような姿になります。
大きいものは8cm近くにもなり、小さいものは3cm程度と、同じ種類とは思えないほど違いがあるので面白いです。
ミヤマクワガタのメスの特徴
田代湿原にミヤマクワガタのメスがいました!
— ネイチャーガイド ファイブセンス@上高地 (@fivesense1500) August 1, 2021
木道の上でひっくり返っていたため、近くの木に移動させました。夏を感じる出会いですね。
もも pic.twitter.com/ZxiEkq1cHO
ミヤマクワガタのメスは、オスと姿形が大きく違います。カブトムシやクワガタはオスの方が注目されがちですが、ミヤマクワガタのメスはとても格好よく、非常に人気です。
ここからはメスの特徴についてご紹介します。
- 大顎と腿節の色
- メスが多くいる場所
大顎と腿節の色
ミヤマクワガタのオスは表面全体に産毛が生えているのに対し、メスの体表は黒色でつるっと艶があり、見た目は全然違います。一見すると、ミヤマクワガタのメスだと見分けがつかない程です。メスは腹の部分に産毛が生えています。
大顎はニッパーのような形をしており、他のクワガタのメスに比べるととても太い顎を持っています。これを使って硬い木に傷つけて樹液を舐めるので、力もとても強く、挟まれると危険です。
太ももに位置する腿節の部分には、黄色い紋が入っています。腹の産毛と大顎の形、腿節を見てミヤマクワガタのメスだと判別するのです。
大顎はニッパーのような形をしており、他のクワガタのメスに比べるととても太い顎を持っています。これを使って硬い木に傷つけて樹液を舐めるので、力もとても強く、挟まれると危険です。
太ももに位置する腿節の部分には、黄色い紋が入っています。腹の産毛と大顎の形、腿節を見てミヤマクワガタのメスだと判別するのです。
メスが多くいる場所
基本はオスと同じく、気温が低く湿度の高い森や山に生息しています。涼しい日陰などを好み、25℃以上の暑さは苦手です。
クヌギの木が好きで、樹液を舐めているところを確認することもできますが、枝分かれの部分に身を潜めて休んでいる姿がよく見られます。
また腐敗した朽木で幼虫は育つため、その近くの土に産卵する場合が多いです。腐敗した朽木付近を探すと、メスが多く見つかります。
クヌギの木が好きで、樹液を舐めているところを確認することもできますが、枝分かれの部分に身を潜めて休んでいる姿がよく見られます。
また腐敗した朽木で幼虫は育つため、その近くの土に産卵する場合が多いです。腐敗した朽木付近を探すと、メスが多く見つかります。
ミヤマクワガタのメスと間違いやすいクワガタ
ミヤマクワガタのオスは特に他のクワガタと違う特徴を持っていますが、小型の場合やメスは、他のクワガタと見分けがつかない場合もあります。
ここでは、ミヤマクワガタに似ている他のクワガタの種類や生態についてご紹介します。他のクワガタの特徴を掴んでおくと、実際にミヤマクワガタを捕獲する際に見分けられてとても便利です。
ここでは、ミヤマクワガタに似ている他のクワガタの種類や生態についてご紹介します。他のクワガタの特徴を掴んでおくと、実際にミヤマクワガタを捕獲する際に見分けられてとても便利です。
アカアシクワガタ
アカアシクワガタはその名の通り、腿節部分が赤いところが特徴です。オスの背の色は黒く艶があり、産毛も生えていないため、簡単にミヤマクワガタと見分けがつくでしょう。
問題はメスです。メスの腿節部分も赤く、ミヤマクワガタのメスには黄色い紋が入っているので、見比べると分かりますが、単体での判別は難しくなります。
アカアシクワガタのメスは、表面的には識別できるポイントがあまりありません。ミヤマクワガタのメスには腹の部分の産毛でそれと判別できるので、採取した際は覚えておくと判別しやすいでしょう。
問題はメスです。メスの腿節部分も赤く、ミヤマクワガタのメスには黄色い紋が入っているので、見比べると分かりますが、単体での判別は難しくなります。
アカアシクワガタのメスは、表面的には識別できるポイントがあまりありません。ミヤマクワガタのメスには腹の部分の産毛でそれと判別できるので、採取した際は覚えておくと判別しやすいでしょう。
ノコギリクワガタ
ノコギリクワガタは、オスとメスの体表が赤っぽいところが特徴です。体長もミヤマクワガタと同じくらいで、オスの大きな顎とスリムな体は、一見するとミヤマクワガタと似ています。
メスは特に他のクワガタと同じような姿形をしていて、すぐにノコギリクワガタと判断するのは難しいかもしれませんが、他のメスに比べると顎が非常に小さいのが特徴です。体表の赤さと顎の小ささに注目してください。
ノコギリクワガタは暖かく湿った場所を好み、生息地がミヤマクワガタと少し違います。本州から九州で見ることができ、山だけでなく低地でも確認できます。見つけた場所で判断することもできるかもしれません。
メスは特に他のクワガタと同じような姿形をしていて、すぐにノコギリクワガタと判断するのは難しいかもしれませんが、他のメスに比べると顎が非常に小さいのが特徴です。体表の赤さと顎の小ささに注目してください。
ノコギリクワガタは暖かく湿った場所を好み、生息地がミヤマクワガタと少し違います。本州から九州で見ることができ、山だけでなく低地でも確認できます。見つけた場所で判断することもできるかもしれません。
ヒラタクワガタ
ヒラタクワガタも同様に、オスは体が横に平べったい形をしているので、ミヤマクワガタとは全然違っています。また艶消しタイプの黒い色をしているので、すぐにヒラタクワガタと判別できるでしょう。
メスは体表全体に艶があって黒く、横幅が広くコロンとした形をしています。よく観察すると、上バネの部分に薄いスジが入っている所もヒラタクワガタの特徴です。メスの顎はミヤマクワガタに比べるととても小さいので、これらの点で見分けることができます。
メスは体表全体に艶があって黒く、横幅が広くコロンとした形をしています。よく観察すると、上バネの部分に薄いスジが入っている所もヒラタクワガタの特徴です。メスの顎はミヤマクワガタに比べるととても小さいので、これらの点で見分けることができます。
ミヤマクワガタを飼育する際に気をつけたいこと
ミヤマクワガタは、他のクワガタに比べて成虫になってからの寿命が短いと言われています。温度や湿度に敏感で、野生の個体は人の手があまり入っていない場所を好んで生息しているので、他のクワガタと比較すると少し難しいかもしれません。
ここからは、ミヤマクワガタを飼育する時に特に気を配りたいポイントについてご説明します。放置せずしっかり観察しながら、ミヤマクワガタがストレスなく安心して住める環境を整えてあげましょう。
ここからは、ミヤマクワガタを飼育する時に特に気を配りたいポイントについてご説明します。放置せずしっかり観察しながら、ミヤマクワガタがストレスなく安心して住める環境を整えてあげましょう。
環境を整えてあげる
先述通り、ミヤマクワガタは涼しい環境に生息しています。適正温度は20℃〜23℃とされており、これ以上暑くなってしまうと寿命が短くなってしまう可能性があります。夏場の暑い時期に飼育する場合は、クーラーを利用して室温を下げるように心がけましょう。
より自然に近い環境にするために、飼育ケースの中に腐葉土と朽木マットを混ぜたものを使用すると良いと言われています。腐葉土は園芸用を使用する場合、農薬や殺虫剤が含まれていないことを確認してから使用してください。
腐葉土と朽木マットをよく混ぜて、飼育ケースの高さの半分以上、厚く敷いてあげるのが理想的です。ミヤマクワガタは上によじ登ろうとする習性があり、よく転倒してしまいます。これを繰り返すと早く弱ってしまう可能性あるので、できるだけ登らなくても良い高さに保ってあげましょう。
より自然に近い環境にするために、飼育ケースの中に腐葉土と朽木マットを混ぜたものを使用すると良いと言われています。腐葉土は園芸用を使用する場合、農薬や殺虫剤が含まれていないことを確認してから使用してください。
腐葉土と朽木マットをよく混ぜて、飼育ケースの高さの半分以上、厚く敷いてあげるのが理想的です。ミヤマクワガタは上によじ登ろうとする習性があり、よく転倒してしまいます。これを繰り返すと早く弱ってしまう可能性あるので、できるだけ登らなくても良い高さに保ってあげましょう。
適切な餌を与える
ミヤマクワガタの餌は、常温の昆虫ゼリーをあげると良いでしょう。ゼリーにはクワガタに必要な栄養素が含まれているので安心です。皿状の小さい丸太が販売されているので、その皿木にのせてあげると、ゼリーがひっくり返らず、ケース内を綺麗に保てます。
リンゴやバナナも好んで食べるので、小さめにカットして与えてください。果物はいたみも早いので、食べ残しがある場合はすぐに取り除きましょう。
同じ果物でもスイカやメロンのような水分の多いものはオススメしません。お腹を下す原因になったり、飼育環境の悪化を招く恐れがあるからです。
蜂蜜や砂糖水で代用する方法を聞いたことがあるかもしれませんが、こちらもあまりオススメできません。蜂蜜の場合は粘度が高いので、そのままあげると蜂蜜が体にまとわりついてしまい、動けなくなってしまいます。
砂糖水はサラサラとしていて甘いので、クワガタも好んで寄ってくるかもしれませんが、栄養価が低いので、メインは栄養がある餌にしましょう。ほぼ水分でお腹を壊してしまうことがあるので注意してください。
リンゴやバナナも好んで食べるので、小さめにカットして与えてください。果物はいたみも早いので、食べ残しがある場合はすぐに取り除きましょう。
同じ果物でもスイカやメロンのような水分の多いものはオススメしません。お腹を下す原因になったり、飼育環境の悪化を招く恐れがあるからです。
蜂蜜や砂糖水で代用する方法を聞いたことがあるかもしれませんが、こちらもあまりオススメできません。蜂蜜の場合は粘度が高いので、そのままあげると蜂蜜が体にまとわりついてしまい、動けなくなってしまいます。
砂糖水はサラサラとしていて甘いので、クワガタも好んで寄ってくるかもしれませんが、栄養価が低いので、メインは栄養がある餌にしましょう。ほぼ水分でお腹を壊してしまうことがあるので注意してください。
越冬について
ミヤマクワガタは成虫になって交配と産卵を終えると、亡くなってしまいます。ですので基本的には越冬しないと考えられています。
ただし交配と産卵をしなかった個体については、稀に越冬して次の春まで生きる場合があるようです。飼育下でも冬眠して寒い冬を越したミヤマクワガタが確認されていますが、この場合も交配と産卵はしていない個体のみ成功したようです。
ただし交配と産卵をしなかった個体については、稀に越冬して次の春まで生きる場合があるようです。飼育下でも冬眠して寒い冬を越したミヤマクワガタが確認されていますが、この場合も交配と産卵はしていない個体のみ成功したようです。
ストレスを与えないよう注意する
ミヤマクワガタにストレスを与えないことも、長く飼育するために必要な条件の一つです。ミヤマクワガタに限らず、昆虫は触られることにとてもストレスを感じます。直接触れる機会は、餌やりの時に場所を確保する場合や、飼育ケースの掃除の時のみに抑えると、ミヤマクワガタが快適に過ごせる空間になります。
また相性の悪いオスとメスを一緒に入れておくことも、大きなストレスになります。ケンカになったり、互いを傷つけあったりする場合があるので、交配させたい時は、同じケースに入れてしばらく観察し、争っている様子が見られたら、どちらかを即別のケースに移しましょう。
オス同士、メス同士のケンカにも注意が必要です。
また相性の悪いオスとメスを一緒に入れておくことも、大きなストレスになります。ケンカになったり、互いを傷つけあったりする場合があるので、交配させたい時は、同じケースに入れてしばらく観察し、争っている様子が見られたら、どちらかを即別のケースに移しましょう。
オス同士、メス同士のケンカにも注意が必要です。
ミヤマクワガタを繁殖させる方法はあるの?
【ワイルド ミヤマクワガタ 山形県産?】
— くわがたはうす?? (@Kuwagata_House) July 15, 2022
ミヤマクワガタのペアを採集しました?
ミヤマクワガタを沢山見つけることができましたが、現地の個体数が減少して欲しくないので、見つけたほとんどの個体をリリースしました⛰
クワガタの住処となる自然の破壊や乱獲は本当に行われて欲しくないです? pic.twitter.com/HrDWtnjciZ
ミヤマクワガタのオスとメスの成虫がいたら、繁殖にトライしてみるのも良いでしょう。先ほども記載した通り、相性の良さを見極めるのも重要です。一緒のケースに入れてみて、ケンカをしなければ、10日間程度で交配します。
交配したメスが産卵できるように、産卵用に準備した飼育ケースに移してあげましょう。産卵用のケースには、高さの7割程度までマットを敷き、地をしっかり固めてあげます。その上からふんわりともう一度マットを敷き、フワフワの足場を作ります。止まり木と昆虫ゼリーなどの餌を置いたら準備完了です。
幼虫はさらに温度の低い場所を好むので、卵が確認できたら16℃〜20℃を保ちましょう。
珍しいと言われがちなミヤマクワガタを捕まえる方法
ミヤマクワガタは標高の高い山にいるので珍しいと考えられていますが、いる場所が分かれば探すことも十分可能です。涼しい山に採取しに行きましょう。
ミヤマクワガタがいそうな場所を見つけたら、以下の方法で捕まえてみることをオススメします。
ミヤマクワガタがいそうな場所を見つけたら、以下の方法で捕まえてみることをオススメします。
光に集まる習性を利用する
他のクワガタと同様に、ミヤマクワガタも光に集まる習性があります。白や青っぽい色の光を好み、黄色っぽい光やLEDには寄ってきません。
白っぽい街灯や自動販売機付近を狙って探すのもオススメです。
白い布にライトを当て、虫を誘き寄せるライトトラップを使った方法もありますが、これは場所によって禁止されている場合があるので注意が必要です。行う場合は事前に確認しましょう。
白っぽい街灯や自動販売機付近を狙って探すのもオススメです。
白い布にライトを当て、虫を誘き寄せるライトトラップを使った方法もありますが、これは場所によって禁止されている場合があるので注意が必要です。行う場合は事前に確認しましょう。
木を蹴って捕まえる
木の高い所に登るミヤマクワガタは、見つけてもなかなか捕まえることができません。その場合は、木を足で蹴って驚かせると、ビックリして固まり、そのまま下に落ちてきます。
クワガタは驚くと、死んだふりをしたような状態で落下し、狙われた鳥などから逃げる習性があるのです。それをうまく利用した方法ですが、一発目のキックをしっかり強めに入れることが大切です。蹴り方が甘いと、かえってミヤマクワガタの警戒を煽り、その後蹴っても落ちてこなくなる可能性があります。
落ちてきたミヤマクワガタは、すぐに逃げてしまうので、見失わないようにすぐに捕まえましょう。
クワガタは驚くと、死んだふりをしたような状態で落下し、狙われた鳥などから逃げる習性があるのです。それをうまく利用した方法ですが、一発目のキックをしっかり強めに入れることが大切です。蹴り方が甘いと、かえってミヤマクワガタの警戒を煽り、その後蹴っても落ちてこなくなる可能性があります。
落ちてきたミヤマクワガタは、すぐに逃げてしまうので、見失わないようにすぐに捕まえましょう。
珍しいと言われがちなミヤマクワガタの特徴や飼育方法を知っておこう
ミヤマクワガタが珍しいと言われる理由がお分かりいただけたと思います。なかなか出会う機会はありませんが、出没情報などを調べて探してみてください。
生態や飼育について知ることができたので、興味のある方は採集して飼ってみるのもオススメです。飼育する場合は大切にお世話してあげましょう。
生態や飼育について知ることができたので、興味のある方は採集して飼ってみるのもオススメです。飼育する場合は大切にお世話してあげましょう。