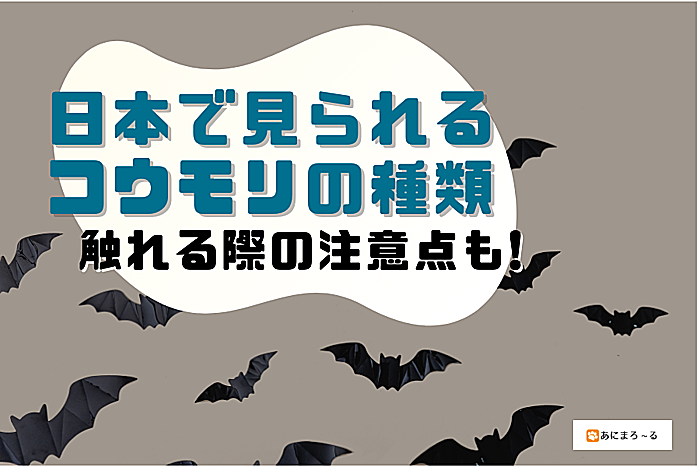「コウモリって飼えるの?」
「コウモリにはどんな種類がいるの?」
「どんな食べ物を餌にしているの?」
など、動物やペットの飼育に興味のある方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、あまり知られていないコウモリの生態やその種類の解説に加え、コウモリと触れ合う場合の注意点についても触れています。
私たちの身近に生息しているコウモリは、特に春頃、夕方になるとパタパタと飛んでいる姿をよく見かけますが、その生態について詳しく知っている人は意外に少ない動物でもあります。
この記事を読むことで、コウモリにはさまざまな種類が存在し、どんな生活をしているのかが分かるため、コウモリの生態に興味のある方は、ぜひこの記事をご一読ください。
「コウモリにはどんな種類がいるの?」
「どんな食べ物を餌にしているの?」
など、動物やペットの飼育に興味のある方の中には、このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、あまり知られていないコウモリの生態やその種類の解説に加え、コウモリと触れ合う場合の注意点についても触れています。
私たちの身近に生息しているコウモリは、特に春頃、夕方になるとパタパタと飛んでいる姿をよく見かけますが、その生態について詳しく知っている人は意外に少ない動物でもあります。
この記事を読むことで、コウモリにはさまざまな種類が存在し、どんな生活をしているのかが分かるため、コウモリの生態に興味のある方は、ぜひこの記事をご一読ください。
コウモリの特徴
コウモリは、哺乳綱翼手目に分類される動物です。
空を飛ぶので、鳥類の仲間だと思っている読者の方もいるのではないでしょうか。
しかし、コウモリは哺乳類の仲間です。
コウモリには、空を飛ぶための翼があります。
驚くことに、コウモリの翼は元々は手のひらだったものが、空を飛ぶために進化したと言われています。
また、鳥は全身羽で覆われていますが、コウモリの場合は翼の部分が飛膜という伸縮性のある膜でできているのも特筆すべき点です。
この飛膜を操って、コウモリは自在に飛び回ります。
ただし、前脚が進化した分、後ろ脚は弱く立つことができません。
コウモリが休むときに後ろ脚で何かにぶらさがり、逆さまになった状態になるのもそのためです。
他にも、逆さまになるのはすぐに脚を離して飛ぶことができるから、という理由があります。
空を飛ぶので、鳥類の仲間だと思っている読者の方もいるのではないでしょうか。
しかし、コウモリは哺乳類の仲間です。
コウモリには、空を飛ぶための翼があります。
驚くことに、コウモリの翼は元々は手のひらだったものが、空を飛ぶために進化したと言われています。
また、鳥は全身羽で覆われていますが、コウモリの場合は翼の部分が飛膜という伸縮性のある膜でできているのも特筆すべき点です。
この飛膜を操って、コウモリは自在に飛び回ります。
ただし、前脚が進化した分、後ろ脚は弱く立つことができません。
コウモリが休むときに後ろ脚で何かにぶらさがり、逆さまになった状態になるのもそのためです。
他にも、逆さまになるのはすぐに脚を離して飛ぶことができるから、という理由があります。
コウモリの生態
コウモリは夜行性なので、昼間は人の目につかない暗い場所で休んでいます。時には、人の家の屋根裏や倉庫を巣にしている場合もあります。
ところで、なぜコウモリは暗い夜に餌を探すことができるのでしょうか。
それはコウモリの特別な身体のつくりにヒントがあります。
コウモリには小さくて可愛らしい目がありますが、ほとんど見えていません。その代わりに、口や鼻から超音波を出して、跳ね返ってきた音を聞いて自分の位置や障害物の場所を把握して飛んでいます。これが、コウモリが真っ暗な夜の空を自在に飛び回って活動できる理由です。
繁殖力は低いとされていますが、長く生きる個体もおり、中には20年以上生きた個体もいたそうです。
ただし、一般的には約3~5年で寿命を全うする個体が多いと言われています。
コウモリのように小さな体で、長寿な哺乳類は珍しいでしょう。
ところで、なぜコウモリは暗い夜に餌を探すことができるのでしょうか。
それはコウモリの特別な身体のつくりにヒントがあります。
コウモリには小さくて可愛らしい目がありますが、ほとんど見えていません。その代わりに、口や鼻から超音波を出して、跳ね返ってきた音を聞いて自分の位置や障害物の場所を把握して飛んでいます。これが、コウモリが真っ暗な夜の空を自在に飛び回って活動できる理由です。
繁殖力は低いとされていますが、長く生きる個体もおり、中には20年以上生きた個体もいたそうです。
ただし、一般的には約3~5年で寿命を全うする個体が多いと言われています。
コウモリのように小さな体で、長寿な哺乳類は珍しいでしょう。
コウモリの大きさ
コウモリは小さい種類が多いですが、中には大きくなるものもいます。
小さなコウモリで体重は3~60g、大きなコウモリは300~530gほどの大きさをしています。
日本でよく見かけるコウモリは約5cm、10gほどの小さな種類です。
小さな体ですがかなりよく食べるので、その体のサイズからは想像つかないようなたくさんのフンや尿をします。そのため、コウモリの糞尿被害に悩まされている方も多いようです。
小さなコウモリで体重は3~60g、大きなコウモリは300~530gほどの大きさをしています。
日本でよく見かけるコウモリは約5cm、10gほどの小さな種類です。
小さな体ですがかなりよく食べるので、その体のサイズからは想像つかないようなたくさんのフンや尿をします。そのため、コウモリの糞尿被害に悩まされている方も多いようです。
日本で見られるコウモリの種類
コウモリは世界各地に約1000種類存在し、南極大陸を除く全ての大陸に生息しています。
日本では、約35種類のコウモリが確認されているそうです。
ここでは、日本に生息しているコウモリ6種類について詳しく紹介しましょう。
日本では、約35種類のコウモリが確認されているそうです。
ここでは、日本に生息しているコウモリ6種類について詳しく紹介しましょう。
アブラコウモリ
日本で最もよく見かけられるコウモリです。アブラコウモリは、日本に生息するコウモリの中で唯一人の家に棲みつく種類で、家のない森の中や洞窟ではほとんど見かけられません。
そのため、「イエコウモリ」とも呼ばれており、私たちに身近な種類と言えるでしょう。
日本全国に分布し、大きさは体長約5cmと小さく、黒や灰色の体色をしています。
特にまだ幼い個体の体色は、黒っぽい色です。
小さな隙間から家屋に侵入し、天井裏や瓦の下、倉庫の中などに棲みつきます。
成熟したオスは1匹で過ごしますが、メスと幼体は一緒に家族単位で過ごすのが特徴です。
夜になると、棲み処から餌となる虫がいる場所まで飛んでいって狩りをします。
蚊や蛾など、人間にとって迷惑になる虫を食べてくれることでは私たちの役に立っている面もありますが、その糞尿や騒音などで駆除対象ともされているケースも多く見られます。
そのため、「イエコウモリ」とも呼ばれており、私たちに身近な種類と言えるでしょう。
日本全国に分布し、大きさは体長約5cmと小さく、黒や灰色の体色をしています。
特にまだ幼い個体の体色は、黒っぽい色です。
小さな隙間から家屋に侵入し、天井裏や瓦の下、倉庫の中などに棲みつきます。
成熟したオスは1匹で過ごしますが、メスと幼体は一緒に家族単位で過ごすのが特徴です。
夜になると、棲み処から餌となる虫がいる場所まで飛んでいって狩りをします。
蚊や蛾など、人間にとって迷惑になる虫を食べてくれることでは私たちの役に立っている面もありますが、その糞尿や騒音などで駆除対象ともされているケースも多く見られます。
ニホンウサギコウモリ
変わった名前の種類ですが、その名の通り、ウサギのような耳を持っているコウモリです。
耳は頭よりも大きく、見つけたらすぐに本種と判別することができます。
日本では、中国地方や三重県、和歌山県などを除いた全国に分布していますが、その数は減少傾向にあり、一時は絶滅の恐れがあると言われた時期もありました。現在では、また少しずつ数が増えているそうです。
大きさはアブラコウモリよりも少し大きいくらいで、薄い茶色や灰色っぽい体色をしています。もともとは木に巣を作って暮らしていましたが、現在は建物に棲みついていることも多いようです。
飛ぶ速さは他の種類と比べて遅く、超音波周波数もあまり高くありません。
前述の通り見た目に特徴があるため、見かけたらすぐに本種だとわかります。ぜひ探してみてください。
耳は頭よりも大きく、見つけたらすぐに本種と判別することができます。
日本では、中国地方や三重県、和歌山県などを除いた全国に分布していますが、その数は減少傾向にあり、一時は絶滅の恐れがあると言われた時期もありました。現在では、また少しずつ数が増えているそうです。
大きさはアブラコウモリよりも少し大きいくらいで、薄い茶色や灰色っぽい体色をしています。もともとは木に巣を作って暮らしていましたが、現在は建物に棲みついていることも多いようです。
飛ぶ速さは他の種類と比べて遅く、超音波周波数もあまり高くありません。
前述の通り見た目に特徴があるため、見かけたらすぐに本種だとわかります。ぜひ探してみてください。
オヒキコウモリ
日本に生息している食虫性のコウモリの中で、最も大きな種類です。
大きさは約8~10㎝で、尻尾が長くそれを引きずって歩く姿からこの名前がつけられました。耳が大きく丸いのも特徴です。体色はこげ茶っぽい色をしています。
日本全国で見かけられますが、その数は減少傾向にあるため、現在は絶滅危惧種に認定されています。
空を飛ぶスピードはとても速く、その速さは時速160㎞にまで達すると言われています。
群れを作って岩の隙間や建物などを隠れ家にして生活します。
本種もウンカやカメムシなどを食べてくれるため、益獣とされているようです。
大きさは約8~10㎝で、尻尾が長くそれを引きずって歩く姿からこの名前がつけられました。耳が大きく丸いのも特徴です。体色はこげ茶っぽい色をしています。
日本全国で見かけられますが、その数は減少傾向にあるため、現在は絶滅危惧種に認定されています。
空を飛ぶスピードはとても速く、その速さは時速160㎞にまで達すると言われています。
群れを作って岩の隙間や建物などを隠れ家にして生活します。
本種もウンカやカメムシなどを食べてくれるため、益獣とされているようです。
オガサワラオオコウモリ
体の大きい本種は、オオコウモリ科に分類される種類で、小さなコウモリと違って虫を食べないのが大きな特徴です。
名前の通り小笠原諸島など、南西諸島にのみ分布している日本の固有種で、昭和44年頃には国の天然記念物に指定されました。
また、棲み処となる森林周辺の開発や、他の生き物との競争に負けて生息数が減少していることから、現在では絶滅危惧種にも認定されています。
体長は約20~25cmで翼を広げると最大で80cmほどと、とても大きいコウモリです。体色は暗褐色で、ところどころ光沢がある白っぽい毛が混ざっています。
オオコウモリの仲間は、超音波を出さず目で見て活動するのが特徴です。そのため、本種は目が大きく耳は小さくなっています。主食となるのは植物で、植物の葉や果実、花蜜などを餌にします。
名前の通り小笠原諸島など、南西諸島にのみ分布している日本の固有種で、昭和44年頃には国の天然記念物に指定されました。
また、棲み処となる森林周辺の開発や、他の生き物との競争に負けて生息数が減少していることから、現在では絶滅危惧種にも認定されています。
体長は約20~25cmで翼を広げると最大で80cmほどと、とても大きいコウモリです。体色は暗褐色で、ところどころ光沢がある白っぽい毛が混ざっています。
オオコウモリの仲間は、超音波を出さず目で見て活動するのが特徴です。そのため、本種は目が大きく耳は小さくなっています。主食となるのは植物で、植物の葉や果実、花蜜などを餌にします。
キクガシラコウモリ
日本全国に分布する種類です。
鼻にひだがあり、その形が菊の花に似ていることが名前の由来です。
体長は約6~8cm、体色は茶褐色です。普段は洞窟や家屋などを棲み処にして休み、繁殖期以外はオスとメスが別々の群れを作って生活するのが特徴です。
動物食で蛾やコガネムシ、蝉など大きめの虫をよく食べ、時には木の上や地表にいる虫を食べると言われています。本種も、生息数が減少していることから、現在は準絶滅危惧種に指定されています。
2003年頃に発生した重症急性呼吸器症候群 (SARS) を覚えている方も多いと思いますが、中国国内に生息するキクガシラコウモリから、このSARSウイルスによく似たウイルスが検出されたことで、SARSの元凶となったのではないかとも考えられています。
鼻にひだがあり、その形が菊の花に似ていることが名前の由来です。
体長は約6~8cm、体色は茶褐色です。普段は洞窟や家屋などを棲み処にして休み、繁殖期以外はオスとメスが別々の群れを作って生活するのが特徴です。
動物食で蛾やコガネムシ、蝉など大きめの虫をよく食べ、時には木の上や地表にいる虫を食べると言われています。本種も、生息数が減少していることから、現在は準絶滅危惧種に指定されています。
2003年頃に発生した重症急性呼吸器症候群 (SARS) を覚えている方も多いと思いますが、中国国内に生息するキクガシラコウモリから、このSARSウイルスによく似たウイルスが検出されたことで、SARSの元凶となったのではないかとも考えられています。
カグラコウモリ
日本では、石垣島や与那国島などの八重山諸島に分布している固有種です。
本種は日本で唯一の熱帯系コウモリで、本種が属するカグラコウモリ科の生物は、オーストラリアやアフリカなどの暖かい地域に生息しています。
体長は約6~9cmで体色は褐色や赤褐色です。
鼻の部分がヒダ状になっており、その形が神楽のお面に似ていることからこの名前がつけられました。
洞窟に生息し、他の種類とは違って1匹ずつで縄張りを作って生活しています。
棲み処の周辺に餌が無い場合には、集団で離れた場所まで移動することもあります。
本種も絶滅危惧種で生息数はかなり少ないようですが、それを見に観光客が来ることで繁殖がうまくいかなかったり、驚いて洞窟から姿を消してしまったりすることが問題になっているそうです。
本種は日本で唯一の熱帯系コウモリで、本種が属するカグラコウモリ科の生物は、オーストラリアやアフリカなどの暖かい地域に生息しています。
体長は約6~9cmで体色は褐色や赤褐色です。
鼻の部分がヒダ状になっており、その形が神楽のお面に似ていることからこの名前がつけられました。
洞窟に生息し、他の種類とは違って1匹ずつで縄張りを作って生活しています。
棲み処の周辺に餌が無い場合には、集団で離れた場所まで移動することもあります。
本種も絶滅危惧種で生息数はかなり少ないようですが、それを見に観光客が来ることで繁殖がうまくいかなかったり、驚いて洞窟から姿を消してしまったりすることが問題になっているそうです。
コウモリの食べ物
コウモリは、主に昆虫、動物の血、果物や花などを食べて生活しています。
ただし、全てのコウモリがこれらを食べている訳ではなく、昆虫しか食べないものや果物や花しか食べないものなども存在します。
体が小さなココウモリの仲間は昆虫食ですが、体の大きなオオコウモリの仲間は植物食です。コウモリというと、吸血する怖いイメージがあるかもしれませんが、血を餌にする種類は意外に少なく、多くの種類は爬虫類と同じような食性です。
では、コウモリが食べる昆虫や果実、花はどんなものなのでしょうか。またどんな動物から血を吸うのでしょうか。
ここからは、それぞれの食べ物について詳しく説明していきます。
ただし、全てのコウモリがこれらを食べている訳ではなく、昆虫しか食べないものや果物や花しか食べないものなども存在します。
体が小さなココウモリの仲間は昆虫食ですが、体の大きなオオコウモリの仲間は植物食です。コウモリというと、吸血する怖いイメージがあるかもしれませんが、血を餌にする種類は意外に少なく、多くの種類は爬虫類と同じような食性です。
では、コウモリが食べる昆虫や果実、花はどんなものなのでしょうか。またどんな動物から血を吸うのでしょうか。
ここからは、それぞれの食べ物について詳しく説明していきます。
昆虫
ココウモリの仲間は、主に昆虫を捕まえて食べています。
捕食する昆虫は、蚊やユスリカ、蛾、カメムシ、ウンカ、蜂など小さな虫から少し大きな虫までさまざまです。
どれも人間の私たちにとっては害のあるものばかりなので、それを食べてくれるコウモリは益獣として役立っています。
空を飛んでいる虫を捕まえることもあれば、地表にいる虫を捕まえることもあります。
特に春頃には、餌となる虫が活発に動き始めるため、コウモリたちも活動的になるようです。
捕食する昆虫は、蚊やユスリカ、蛾、カメムシ、ウンカ、蜂など小さな虫から少し大きな虫までさまざまです。
どれも人間の私たちにとっては害のあるものばかりなので、それを食べてくれるコウモリは益獣として役立っています。
空を飛んでいる虫を捕まえることもあれば、地表にいる虫を捕まえることもあります。
特に春頃には、餌となる虫が活発に動き始めるため、コウモリたちも活動的になるようです。
動物の血
動物の血を餌にするのは、数多く存在するコウモリの種類の中でも、わずか3種類のみです。
・チスイコウモリ属
・シロチスイコウモリ属
・ケアシチスイコウモリ属
上記のコウモリは、日本には生息していません。
牛や馬、ヤギや、まれに人間など、哺乳類の皮膚を鋭い歯で切り裂いて血を舐めます。中には鳥の血を好む種類もいるようです。
血をすする吸血鬼のようなイメージがありますが、これらの種類のコウモリは特別な舌のつくりをしており、管のような形を作って血を吸い上げる方法をとります。
血を餌にするコウモリの唾液には、血を固まりにくくする成分が含まれています。そのため、スムーズに血を吸い上げられるのは、この種のコウモリの特筆すべき特徴でしょう。
なかなか十分な量の血を探すことができないときには、集団の中で特にお腹がすいている個体に対し、充分栄養を蓄えた個体が血を分けることもあります。
・チスイコウモリ属
・シロチスイコウモリ属
・ケアシチスイコウモリ属
上記のコウモリは、日本には生息していません。
牛や馬、ヤギや、まれに人間など、哺乳類の皮膚を鋭い歯で切り裂いて血を舐めます。中には鳥の血を好む種類もいるようです。
血をすする吸血鬼のようなイメージがありますが、これらの種類のコウモリは特別な舌のつくりをしており、管のような形を作って血を吸い上げる方法をとります。
血を餌にするコウモリの唾液には、血を固まりにくくする成分が含まれています。そのため、スムーズに血を吸い上げられるのは、この種のコウモリの特筆すべき特徴でしょう。
なかなか十分な量の血を探すことができないときには、集団の中で特にお腹がすいている個体に対し、充分栄養を蓄えた個体が血を分けることもあります。
果物や花
体の大きなオオコウモリの仲間は植物の葉や果物、花、蜜などを餌にします。
そのため「フルーツコウモリ」などと呼ばれることもあるそうです。
大きな体を維持するために、昆虫や血などを餌にする必要があると考えがちですが、これらの種類のコウモリは草食です。口に入れた花の蜜や果物から水分だけを体内に取り入れ、それ以外の繊維質はペッと吐き出します。
オオコウモリの仲間は昆虫や血を与える必要がないので、ペットとしても飼いやすいでしょう。ペットショップなどでも、稀に販売されていることがあります。
自宅で飼育する場合は、バナナやマンゴーなどを餌として与えます。
そのため「フルーツコウモリ」などと呼ばれることもあるそうです。
大きな体を維持するために、昆虫や血などを餌にする必要があると考えがちですが、これらの種類のコウモリは草食です。口に入れた花の蜜や果物から水分だけを体内に取り入れ、それ以外の繊維質はペッと吐き出します。
オオコウモリの仲間は昆虫や血を与える必要がないので、ペットとしても飼いやすいでしょう。ペットショップなどでも、稀に販売されていることがあります。
自宅で飼育する場合は、バナナやマンゴーなどを餌として与えます。
コウモリは鳥獣保護管理法で保護されている
コウモリのことを知り、実物を見てみたいと考えた方もいるでしょうが、もし見つけても捕まえることはできません。
コウモリは「鳥獣保護管理法」という法律で保護されているため、捕獲が禁止されています。
そのため、コウモリを捕獲したり傷つけたりした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
法律によってコウモリが守られている理由は、日本に生息している多くのコウモリが絶滅の危機にあるためです。
万一捕獲する場合は、自治体などに許可をもらう必要があります。
また、コウモリにはたくさんの病原菌がついている可能性があることも、法律でコウモリが守られている理由のひとつです。
知らずに触ってしまうと、感染症やアレルギーなどを発症する危険があります。
出典・参照:コウモリについてのお知らせ|朝倉市
コウモリは「鳥獣保護管理法」という法律で保護されているため、捕獲が禁止されています。
そのため、コウモリを捕獲したり傷つけたりした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
法律によってコウモリが守られている理由は、日本に生息している多くのコウモリが絶滅の危機にあるためです。
万一捕獲する場合は、自治体などに許可をもらう必要があります。
また、コウモリにはたくさんの病原菌がついている可能性があることも、法律でコウモリが守られている理由のひとつです。
知らずに触ってしまうと、感染症やアレルギーなどを発症する危険があります。
出典・参照:コウモリについてのお知らせ|朝倉市
コウモリに触れる際の注意点
コウモリを捕獲できない理由は前述の通りですが、もしも家の敷地内や屋外で傷ついたコウモリを見つけた場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
人との関わりの中で怪我をしたり傷ついたりしたコウモリであれば、一時的に保護することが許されています。
ただし、申告せず長期間保護したり、そのまま飼育したりすることはできません。保護した場合は、すぐに居住地の市町村に連絡してください。
また、保護する際に素手で触ってはいけません。軍手など厚みのある手袋をはめて、直接コウモリに触れることや噛まれることを防ぎましょう。そして、手袋越しであっても、触った後は必ず手を洗ってください。
保護中にはミルワームなどの昆虫を与え、暗く静かな場所に置いてあげましょう。
ただし、あくまでも怪我を治して野生に返すのが保護の目的です。
愛着がわいたとしても、コウモリを身近に置いておくリスクは大きいことを理解しておいてください。
出典・参照:傷病鳥獣の救護等について|京都府
人との関わりの中で怪我をしたり傷ついたりしたコウモリであれば、一時的に保護することが許されています。
ただし、申告せず長期間保護したり、そのまま飼育したりすることはできません。保護した場合は、すぐに居住地の市町村に連絡してください。
また、保護する際に素手で触ってはいけません。軍手など厚みのある手袋をはめて、直接コウモリに触れることや噛まれることを防ぎましょう。そして、手袋越しであっても、触った後は必ず手を洗ってください。
保護中にはミルワームなどの昆虫を与え、暗く静かな場所に置いてあげましょう。
ただし、あくまでも怪我を治して野生に返すのが保護の目的です。
愛着がわいたとしても、コウモリを身近に置いておくリスクは大きいことを理解しておいてください。
出典・参照:傷病鳥獣の救護等について|京都府
コウモリの種類や食べ物について知ろう
本記事では、日本に生息しているコウモリの種類やその生態について解説してきました。
一口に「コウモリ」と言ってもさまざまな種類が存在し、種類によって餌となる食べ物も異なることを理解できたことでしょう。
吸血鬼のような恐ろしいイメージを持たれやすいコウモリですが、血を餌にする種類はごくわずかで、実際は昆虫や花、果物を食べる種類がほとんどです。
残念ながら、多くの種類はその生息数が減少傾向にあり、絶滅危惧種に指定されています。そのため、可愛いからといって野生のコウモリを捕まえてペットとして飼育することは許されていません。
この記事を読んでコウモリに興味が湧いたという方も、野生のコウモリを見かけた場合は、静かに見守ってください。
また、自宅に棲みついて糞尿などで困っている場合は、勝手に駆除せずに専門の業者に相談しましょう。
一口に「コウモリ」と言ってもさまざまな種類が存在し、種類によって餌となる食べ物も異なることを理解できたことでしょう。
吸血鬼のような恐ろしいイメージを持たれやすいコウモリですが、血を餌にする種類はごくわずかで、実際は昆虫や花、果物を食べる種類がほとんどです。
残念ながら、多くの種類はその生息数が減少傾向にあり、絶滅危惧種に指定されています。そのため、可愛いからといって野生のコウモリを捕まえてペットとして飼育することは許されていません。
この記事を読んでコウモリに興味が湧いたという方も、野生のコウモリを見かけた場合は、静かに見守ってください。
また、自宅に棲みついて糞尿などで困っている場合は、勝手に駆除せずに専門の業者に相談しましょう。