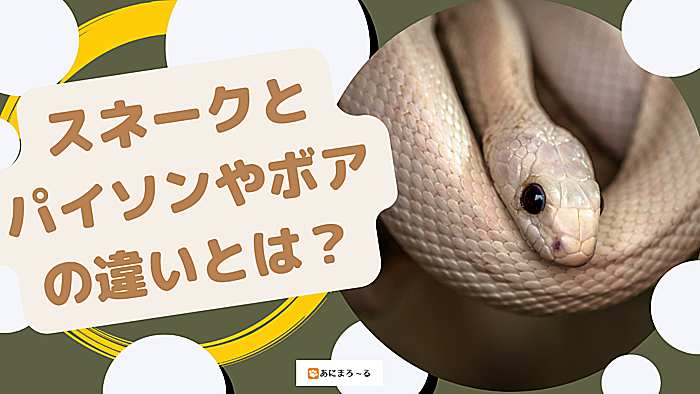ヘビの呼び名にはスネーク以外に、パイソンやボアといった表現もあります。スネークやパイソンまでなら、服飾品の柄などに使われたりするため聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、具体的な違いはわからない、という方が多いのではないでしょうか。
この記事ではスネークとパイソンとボアの3つの呼び名の意味や、指し示す対象について具体的な例をあげながら紹介しています。
該当するヘビの具体的な名称や特徴も取り上げているため、ヘビに興味があり飼育を考えている方は、知っておくと購入する際に欲しい個体の分類がよりわかりやすくなるでしょう。
ヘビの呼び名の様々な意味や違いを整理したいという方は、ぜひこの記事を読み確かめてください。
この記事ではスネークとパイソンとボアの3つの呼び名の意味や、指し示す対象について具体的な例をあげながら紹介しています。
該当するヘビの具体的な名称や特徴も取り上げているため、ヘビに興味があり飼育を考えている方は、知っておくと購入する際に欲しい個体の分類がよりわかりやすくなるでしょう。
ヘビの呼び名の様々な意味や違いを整理したいという方は、ぜひこの記事を読み確かめてください。
スネークとは?
スネークは日本語で言うヘビの英名に該当し、基本的にはヘビ全般を指す言葉です。ヘビは四肢を持たず細長い体をくねらせて移動する姿や、毒を持つものもいるため嫌う人も多いのではないでしょうか。
しかし、品種によっては無毒でおとなしく、近年は犬猫以外のコンパニオンアニマルとして爬虫類を飼う人も増えてきていて、綺麗な柄も多いヘビはペットとして人気が高いです。
生息地は種によって異なり、森林や草原、砂漠などの陸地以外に、川や海に住むウミヘビなどもいます。肉食性で自然下ではネズミやカエルのほかウサギなどそれぞれの体の大きさにあった動物が主食です。
寿命は短いものでも10年程度は生きるため、ペットとして飼育する際は最後まで世話できるかしっかりと確認した上で購入してください。品種によって寿命以外にも成体となった際の大きさや毒性の有無なども全く異なり、必要な飼育環境も注意点もまったく違うためヘビの品種については事前に細かく調べましょう。
しかし、品種によっては無毒でおとなしく、近年は犬猫以外のコンパニオンアニマルとして爬虫類を飼う人も増えてきていて、綺麗な柄も多いヘビはペットとして人気が高いです。
生息地は種によって異なり、森林や草原、砂漠などの陸地以外に、川や海に住むウミヘビなどもいます。肉食性で自然下ではネズミやカエルのほかウサギなどそれぞれの体の大きさにあった動物が主食です。
寿命は短いものでも10年程度は生きるため、ペットとして飼育する際は最後まで世話できるかしっかりと確認した上で購入してください。品種によって寿命以外にも成体となった際の大きさや毒性の有無なども全く異なり、必要な飼育環境も注意点もまったく違うためヘビの品種については事前に細かく調べましょう。
パイソンやボアはスネークの一種?
ヘビを指す言葉はスネークだけではありません。パイソンやボアといった呼び名を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
ヘビには毒の有無や大きさなどの特徴で、細かく分類した呼び方がいくつかあり、パイソンは元はヘビの品種の一つですが、大きさに特徴のあるヘビ全般を指す言葉でもあります。一方でボアはヘビの品種名です。
スネークがヘビ全般を指す場合は、パイソンやボアはスネークの一種だといえます。しかし、パイソンのように大きさや毒性などの特徴で分類した呼び名が別にあるため、その分類に当てはまらない「小さくて毒性がなく大人しいヘビ」を指す言葉としてスネークが使われる場合もあるのです。
とはいえ、仮に英語話者の人がペットのヘビをスネークと言って見せた場合は、毒ヘビも含むヘビ全般を指していると考え注意しましょう。安易に触れて毒ヘビだった場合が大変です。
ここではパイソンとボアについてそれぞれ詳しく紹介します。
ヘビには毒の有無や大きさなどの特徴で、細かく分類した呼び方がいくつかあり、パイソンは元はヘビの品種の一つですが、大きさに特徴のあるヘビ全般を指す言葉でもあります。一方でボアはヘビの品種名です。
スネークがヘビ全般を指す場合は、パイソンやボアはスネークの一種だといえます。しかし、パイソンのように大きさや毒性などの特徴で分類した呼び名が別にあるため、その分類に当てはまらない「小さくて毒性がなく大人しいヘビ」を指す言葉としてスネークが使われる場合もあるのです。
とはいえ、仮に英語話者の人がペットのヘビをスネークと言って見せた場合は、毒ヘビも含むヘビ全般を指していると考え注意しましょう。安易に触れて毒ヘビだった場合が大変です。
ここではパイソンとボアについてそれぞれ詳しく紹介します。
パイソンとは?
パイソンとはニシキヘビ科の仲間を指す英名で、現在確認されているヘビの中でも、東南アジアで最大級の大きさと言われるアミメニシキヘビが所属する品種です。大きさは成体の小さいもので2mほどで、最大のもの10mほどと言われています。
同種の中には大人の男性の太腿くらいの太さまで成長するものも多く体型は太めです。色柄は褐色に濃い色の斑紋を持つものが多く、柄が美しく体格が大きいものが多いため様々な革製品に加工しやすく、パイソン柄の商品は親しまれています。パイソンという言葉に聞き覚えがある方が多いのはこのためでしょう。
また、パイソンは全長5m以上で毒を持たず、噛み付いた獲物を締め上げて、心臓を止めてから捕食するスタイルの大蛇全般を指す言葉でもあります。そのためニシキヘビ科に属さないボア科のヘビの一部も大蛇の一つという意味でパイソンとよばれる場合もあるため混同しないように注意しましょう。
同種の中には大人の男性の太腿くらいの太さまで成長するものも多く体型は太めです。色柄は褐色に濃い色の斑紋を持つものが多く、柄が美しく体格が大きいものが多いため様々な革製品に加工しやすく、パイソン柄の商品は親しまれています。パイソンという言葉に聞き覚えがある方が多いのはこのためでしょう。
また、パイソンは全長5m以上で毒を持たず、噛み付いた獲物を締め上げて、心臓を止めてから捕食するスタイルの大蛇全般を指す言葉でもあります。そのためニシキヘビ科に属さないボア科のヘビの一部も大蛇の一つという意味でパイソンとよばれる場合もあるため混同しないように注意しましょう。
ボアとは?
ボアはヘビの一種でボア科やボア亜科に属するヘビ全般を言います。大きさは最小のパシフィックボアで約60cmで、他のボア科だと約2〜4mのものが多くニシキヘビ科のパイソンと違い小さめの種が多いです。
同種の中でもっとも大きく成長するのが知る人も多いアナコンダ系のボア種で、オオアナコンダは9m以上を超える個体も発見されています。ニシキヘビ科のパイソンと同様に無毒で獲物を締め落として捕食するタイプのヘビです。
アナコンダ系のボア種は5m以上になる場合もある大型のヘビのため、大蛇という意味でパイソンの一種として一括りにされたりもします。
ボア種でよく知られているのが、ボアコンストリクターという品種で愛好家にはボアコンの名前で親しまれていてペットに迎える方もいます。しかし、コンストリクターとは「絞め殺すもの」という意味で、名前に違わず締め付ける力が強いため、ペットとして飼育する場合は締め付けられないよう注意が必要です。
同種の中でもっとも大きく成長するのが知る人も多いアナコンダ系のボア種で、オオアナコンダは9m以上を超える個体も発見されています。ニシキヘビ科のパイソンと同様に無毒で獲物を締め落として捕食するタイプのヘビです。
アナコンダ系のボア種は5m以上になる場合もある大型のヘビのため、大蛇という意味でパイソンの一種として一括りにされたりもします。
ボア種でよく知られているのが、ボアコンストリクターという品種で愛好家にはボアコンの名前で親しまれていてペットに迎える方もいます。しかし、コンストリクターとは「絞め殺すもの」という意味で、名前に違わず締め付ける力が強いため、ペットとして飼育する場合は締め付けられないよう注意が必要です。
それぞれの呼び名の使われるヘビの例
スネークはヘビ全般を指す場合と小型で毒のないおとなしいヘビを指す場合があり、パイソンもヘビの一品種を指す場合と大蛇を指す場合があります。では、固有名にスネークやパイソン、ボアという言葉が入ったヘビは具体的にどんなヘビなのでしょうか。
例えばコーンスネークはペットのヘビとしてメジャーな品種ですが、小型で毒のないおとなしいヘビのため、スネークが指す二つの意味の両方が当てはまるケースだと言えるでしょう。しかし、スネークは基本的にヘビ全般を指す言葉のため、スネークと名のついたヘビの中には毒ヘビもいます。
同様にパイソンも元は日本でいうニシキヘビの英名のため、すべてが大蛇と呼べるほど大型のものではありません。それは大蛇という意味でパイソンの一種と言われる場合もあるボアも同じで、固有名にボアと名のつくヘビには大きくないものもいます。
ここではスネークやパイソン、ボアという言葉が固有名に入ったヘビを具体的に紹介します。
例えばコーンスネークはペットのヘビとしてメジャーな品種ですが、小型で毒のないおとなしいヘビのため、スネークが指す二つの意味の両方が当てはまるケースだと言えるでしょう。しかし、スネークは基本的にヘビ全般を指す言葉のため、スネークと名のついたヘビの中には毒ヘビもいます。
同様にパイソンも元は日本でいうニシキヘビの英名のため、すべてが大蛇と呼べるほど大型のものではありません。それは大蛇という意味でパイソンの一種と言われる場合もあるボアも同じで、固有名にボアと名のつくヘビには大きくないものもいます。
ここではスネークやパイソン、ボアという言葉が固有名に入ったヘビを具体的に紹介します。
「スネーク」のつくヘビ
スネークと名のつくヘビにはコーンスネークやカリフォルニアキングスネークなどがいます。二種の特徴は以下の通りです。
1.コーンスネーク
毒がなくおとなしい性格で成長しても1.5mほどの大きさでペットとして人気が高いヘビの一つです。和名がアカダイショウで、日本でよく知られているアオダイショウと同じ科のヘビです。原種は濃い橙色ですが、品種改良され現在では様々なカラーがあります。
2.カリフォルニアキングスネーク
コーンスネークに次いでペットとして人気の高いヘビで基本的には性格もおとなしく成長してもサイズは1.5mほどです。毒も持っていません。基本的には餌の食いつきがよく餌を与えてくれる人間に寄ってくるようにもなります。
また、日本では名の知れたアオダイショウも英名はジャパニーズラットスネークです。アオダイショウは毒性がなく大人しいヘビのためペットとして飼う人もいます。しかし、成体のサイズは大きいもので2mと決して小さくはありません。
他にも英名ではスネークのつくヘビとして、セイブシシバナヘビ(ウエスタンホッグノーズスネーク)やヒゲミズヘビ(タンタクルスネーク)などがいます。これら二種は小型ですがこれまで例にあげたものと違い有毒種のため扱う際は注意が必要です。
1.コーンスネーク
毒がなくおとなしい性格で成長しても1.5mほどの大きさでペットとして人気が高いヘビの一つです。和名がアカダイショウで、日本でよく知られているアオダイショウと同じ科のヘビです。原種は濃い橙色ですが、品種改良され現在では様々なカラーがあります。
2.カリフォルニアキングスネーク
コーンスネークに次いでペットとして人気の高いヘビで基本的には性格もおとなしく成長してもサイズは1.5mほどです。毒も持っていません。基本的には餌の食いつきがよく餌を与えてくれる人間に寄ってくるようにもなります。
また、日本では名の知れたアオダイショウも英名はジャパニーズラットスネークです。アオダイショウは毒性がなく大人しいヘビのためペットとして飼う人もいます。しかし、成体のサイズは大きいもので2mと決して小さくはありません。
他にも英名ではスネークのつくヘビとして、セイブシシバナヘビ(ウエスタンホッグノーズスネーク)やヒゲミズヘビ(タンタクルスネーク)などがいます。これら二種は小型ですがこれまで例にあげたものと違い有毒種のため扱う際は注意が必要です。
「パイソン」のつくヘビ
パイソンと名のつくヘビでよく知られているのはボールパイソンやカーペットパイソンではないでしょうか。二種の特長は以下の通りです。
1.ボールパイソン
ボール状に丸まり身を守る性質があり臆病でおとなしい性格の個体が多く人気の高いヘビです。大きさは長くても2mに満たない中型サイズですが胴が太く重量感のあるヘビを飼いたい人に向いています。
2.カーペットパイソン
カーペットのような模様が美しく人気が高いヘビでボールパイソンと違い細身で成体の長さは2〜2.5mほどです。性格はボールパイソンと同様におとなしく餌の食いつきもいいため飼育もしやすいです。
なおパイソンはニシキヘビ科のヘビの英名のため和名にニシキヘビとつく品種の英名にはパイソンとつきます。オオアナコンダと並ぶ長さのアミメニシキヘビも別名レティキュレートパイソンとよばれています。
パイソンと名のつくヘビは小さくても2m近いサイズになり、太さがある品種もありずっしりとした重さが感じられる中型から大型のものが多いです。
1.ボールパイソン
ボール状に丸まり身を守る性質があり臆病でおとなしい性格の個体が多く人気の高いヘビです。大きさは長くても2mに満たない中型サイズですが胴が太く重量感のあるヘビを飼いたい人に向いています。
2.カーペットパイソン
カーペットのような模様が美しく人気が高いヘビでボールパイソンと違い細身で成体の長さは2〜2.5mほどです。性格はボールパイソンと同様におとなしく餌の食いつきもいいため飼育もしやすいです。
なおパイソンはニシキヘビ科のヘビの英名のため和名にニシキヘビとつく品種の英名にはパイソンとつきます。オオアナコンダと並ぶ長さのアミメニシキヘビも別名レティキュレートパイソンとよばれています。
パイソンと名のつくヘビは小さくても2m近いサイズになり、太さがある品種もありずっしりとした重さが感じられる中型から大型のものが多いです。
「ボア」のつくヘビ
ボアと名のつくヘビはボア科に属するヘビのみで、ペットとしても人気が高く知名度が高いのはボアコンストリクターです。大人しい性格でハンドリングも可能な上に大きいものは全長約3mにまで成長する迫力のあるヘビでペットとして人気が高い品種でした。
しかし、動物愛護管理法の変更があり人に危害を与える危険性のある特定動物に登録されペットとして新たに飼育を禁じられています。
それ以外にペットとしておすすめのボアと名のつくヘビは以下のとおりです。
1.エメラルドツリーボア
鮮やかな緑の皮膚を持ったヘビで成体の長さは約1.8〜2mです。ボアコンストリクターと違い臆病で神経質な性格のため手を差し込むだけで嚙みつきます。長く鋭い牙に毒はありませんが噛み付かれると流血は免れませんので、飼育する際は注意が必要です。
2.ケニアサンドボア
1日の大半を砂の中で過ごすヘビで成体の体長は大きくても約70cmと小型です。砂の中に隠れて獲物を待ち伏せし素早く嚙みついて捕食します。国内ではあまり繁殖されていないため高価ですが飼育しやすく他のボアとの性質の違いもあり人気の品種です。
しかし、動物愛護管理法の変更があり人に危害を与える危険性のある特定動物に登録されペットとして新たに飼育を禁じられています。
それ以外にペットとしておすすめのボアと名のつくヘビは以下のとおりです。
1.エメラルドツリーボア
鮮やかな緑の皮膚を持ったヘビで成体の長さは約1.8〜2mです。ボアコンストリクターと違い臆病で神経質な性格のため手を差し込むだけで嚙みつきます。長く鋭い牙に毒はありませんが噛み付かれると流血は免れませんので、飼育する際は注意が必要です。
2.ケニアサンドボア
1日の大半を砂の中で過ごすヘビで成体の体長は大きくても約70cmと小型です。砂の中に隠れて獲物を待ち伏せし素早く嚙みついて捕食します。国内ではあまり繁殖されていないため高価ですが飼育しやすく他のボアとの性質の違いもあり人気の品種です。
ヴァイパーとは?
スネークやパイソンという言葉は、詳しい内容は別として比較的に聞き覚えがある人も多いのではないでしょうか。しかし、ヴァイパーという言葉はどうでしょう。
ヴァイパーとは強い出血毒を持ったクサリヘビ科のヘビの英名です。また、コブラ科コブラ属以外の毒ヘビ全般を指す言葉でもあります。
クサリヘビ科に属するヘビの多くは胴回りが太く網目柄の模様で鎖のように見えるのが特徴です。他にも長い毒牙やエラの張った三角形の大きな頭も特徴としてあげられます。
コブラ科コブラ属のヘビを除く毒ヘビ全般を総称してヴァイパーという場合は、クサリヘビ科以外にウミヘビ科やナミヘビ科の有毒種なども含まれます。
ここでは日本にも多く生息するクサリヘビ科に属するヴァイパーを含め、毒ヘビ全般という意味でヴァイパーと呼ばれるヘビを具体的に紹介します。
ヴァイパーとは強い出血毒を持ったクサリヘビ科のヘビの英名です。また、コブラ科コブラ属以外の毒ヘビ全般を指す言葉でもあります。
クサリヘビ科に属するヘビの多くは胴回りが太く網目柄の模様で鎖のように見えるのが特徴です。他にも長い毒牙やエラの張った三角形の大きな頭も特徴としてあげられます。
コブラ科コブラ属のヘビを除く毒ヘビ全般を総称してヴァイパーという場合は、クサリヘビ科以外にウミヘビ科やナミヘビ科の有毒種なども含まれます。
ここでは日本にも多く生息するクサリヘビ科に属するヴァイパーを含め、毒ヘビ全般という意味でヴァイパーと呼ばれるヘビを具体的に紹介します。
ヴァイパー(毒ヘビ)の例
毒ヘビの総称を表す言葉としても使われるヴァイパーの名を英名に持つヘビの中には、日本人が知る人が多いマムシやハブ、ガラガラヘビなどが含まれています。所属ごとに紹介すると次の通りです。
クサリヘビ科マムシ属
・ニホンマムシ
クサリヘビ科ハブ属
・サキシマハブ
・ホンハブ
・トカラハブ
クサリヘビ科ガラガラヘビ属
・ヒガシダイヤガラガラヘビ
クサリヘビ科の品種であるヴァイパーはこれ以外にもたくさんおり、現在確認されている毒ヘビの中の約25%を占めていると言われています。
クサリヘビ科以外のヴァイパーとして挙げられる毒ヘビには、ウミヘビ科のほとんどの品種とナミヘビ科の一部も該当します。ウミヘビ科のヴァイパーはコブラの仲間から進化したという説もあり、コブラ科のウミヘビ亜科として取り扱う場合もあります。
ウミヘビの中でも特に強い毒を持つ品種として挙げられるのがベルチャーウミヘビです。コブラ科ウミヘビ属のヘビで神経毒を相手に注入し獲物痺れさせて捕食します。
ナミヘビ科に所属するヴァイパーは日本にも生息するオオカサントウやヤマカガシなどです。
クサリヘビ科マムシ属
・ニホンマムシ
クサリヘビ科ハブ属
・サキシマハブ
・ホンハブ
・トカラハブ
クサリヘビ科ガラガラヘビ属
・ヒガシダイヤガラガラヘビ
クサリヘビ科の品種であるヴァイパーはこれ以外にもたくさんおり、現在確認されている毒ヘビの中の約25%を占めていると言われています。
クサリヘビ科以外のヴァイパーとして挙げられる毒ヘビには、ウミヘビ科のほとんどの品種とナミヘビ科の一部も該当します。ウミヘビ科のヴァイパーはコブラの仲間から進化したという説もあり、コブラ科のウミヘビ亜科として取り扱う場合もあります。
ウミヘビの中でも特に強い毒を持つ品種として挙げられるのがベルチャーウミヘビです。コブラ科ウミヘビ属のヘビで神経毒を相手に注入し獲物痺れさせて捕食します。
ナミヘビ科に所属するヴァイパーは日本にも生息するオオカサントウやヤマカガシなどです。
ヘビの種類による呼び名の違いについて知ろう
ヘビには、スネーク、パイソン、ボア、ヴァイパーなどの呼び名があり、ボア以外の3種はそれぞれ2パターンの解釈ができる呼び方のため間違わないよう注意する必要があります。
パイソンやボアは品種名でありながら、パイソンは毒がなく獲物を締め上げて捕食する大蛇全般を表す言葉でもあるため、ボアの品種でありながら大型のアナコンダ系のヘビはパイソンと言われる場合もあります。
また、ヴァイパーもクサリヘビ科のヘビの品種名でありながら、クサリヘビ科以外で毒ヘビとして認知度が高い、コブラに属するヘビ以外の毒ヘビ全般を表す言葉です。
スネークは日本語でいうヘビの英訳以外に、大蛇全般を表すパイソンや、毒ヘビ全般を表すヴァイパー以外の無毒で小さくおとなしいヘビを指す場合もあります。
いずれにしても状況や相手の感覚で言葉のイメージに差があり、きっちりとした基準が定まっている言葉ではありませんがそれぞれの呼び名の持つ意味をしっかりと把握しておくと、誤った解釈をしにくくなるでしょう。
パイソンやボアは品種名でありながら、パイソンは毒がなく獲物を締め上げて捕食する大蛇全般を表す言葉でもあるため、ボアの品種でありながら大型のアナコンダ系のヘビはパイソンと言われる場合もあります。
また、ヴァイパーもクサリヘビ科のヘビの品種名でありながら、クサリヘビ科以外で毒ヘビとして認知度が高い、コブラに属するヘビ以外の毒ヘビ全般を表す言葉です。
スネークは日本語でいうヘビの英訳以外に、大蛇全般を表すパイソンや、毒ヘビ全般を表すヴァイパー以外の無毒で小さくおとなしいヘビを指す場合もあります。
いずれにしても状況や相手の感覚で言葉のイメージに差があり、きっちりとした基準が定まっている言葉ではありませんがそれぞれの呼び名の持つ意味をしっかりと把握しておくと、誤った解釈をしにくくなるでしょう。