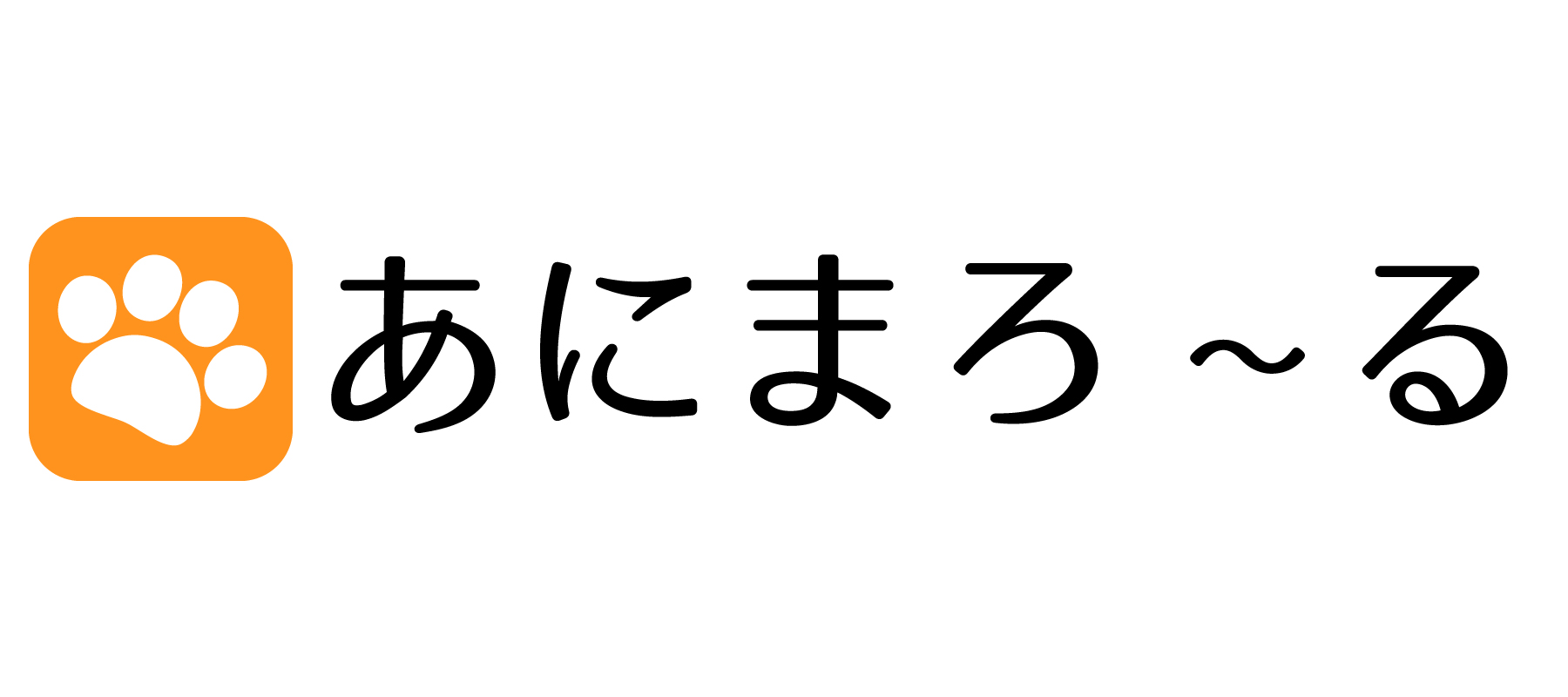犬と猫の食物アレルギー完全ガイド|原因・症状・検査方法・最適なフード選びを獣医師目線で徹底解説
更新日:2025年11月26日

- 犬猫の食物アレルギーは、特定の食べ物のタンパク質に免疫が過剰反応することで起こる病気です。
- 主な症状は季節を問わないしつこい皮膚の痒み、皮膚炎、慢性的な下痢や嘔吐などが挙げられます。
- 食物アレルギーの最も確実な診断方法は、獣医師指導のもとで実施される「食物除去試験」です。
- アレルギー対策の基本は、アレルゲンを含まない療法食を選び、食事管理を徹底することにあります。
- 愛犬・愛猫に疑わしい症状が見られたら、自己判断せず動物病院で専門的な相談をすることが重要です。
愛犬や愛猫がしきりに体を掻いていたり、原因不明の下痢や嘔吐を繰り返したりしていませんか?その症状、もしかしたら毎日の食事が原因の「食物アレルギー」かもしれません。
ペットの食物アレルギーは珍しいものではなく、多くの飼い主様が悩んでいます。しかし、何が原因で、どのフードを選べば良いのか、正しい情報を得るのは難しいものです。 この記事では、犬と猫の食物アレルギーについて、獣医師がその原因から症状、正確な検査方法、そして最も重要なフード選びのポイントまで、専門的な知見を交えて分かりやすく解説します。- 食物アレルギーの具体的な症状(皮膚・消化器)
- 犬と猫で報告の多いアレルゲン
- 動物病院で行う正確な検査方法と費用
- 症状やアレルゲンに合わせたフードの選び方
大切な家族であるペットの健康管理のために、正しい知識を身につけ、最適な対策を見つけましょう。
犬・猫の食物アレルギーとは?主な原因とアレルゲン

食物アレルギーは、特定の食べ物に含まれるタンパク質に対して、体の免疫システムが過剰に反応してしまうことで起こる病気です。本来、食べ物は体を構成するための栄養素であり無害なはずですが、免疫システムが特定のタンパク質を「敵」と誤認し攻撃することで、皮膚の痒みや消化器症状といった様々なアレルギー反応が引き起こされます。
主なアレルゲンは身近な食材
主なアレルゲンとなる食材
- 犬の主なアレルゲン: 牛肉、乳製品、鶏肉、小麦、卵、大豆など
- 猫の主なアレルゲン: 牛肉、乳製品、魚(三大アレルゲン)
これらはあくまで一般的な傾向であり、どの食材がアレルゲンになるかは個体差が非常に大きいのが特徴です。最近では、ペットフードの多様化に伴い、ラムや鹿肉、さらには新しい原材料に対するアレルギーも報告されています。
食物アレルギーの発生率
犬の皮膚疾患全体の中で、食物アレルギーが原因であるケースは約1〜5%、アレルギー性皮膚炎の中では約10%を占めるという報告があります。猫においても同様の傾向が見られます。決して稀な病気ではなく、皮膚や消化器に慢性的な問題を抱えている場合、常に食物アレルギーの可能性を考慮する必要があります。
もしかして…?見逃せない食物アレルギーの主な症状

食物アレルギーの症状は多岐にわたりますが、代表的なのは皮膚症状と消化器症状です。季節に関係なく一年中続く、しつこい痒みが最大の特徴と言えるでしょう。
皮膚に現れる症状:しつこい痒みや皮膚炎
ペットが体を掻きむしる、床にこすりつける、足先を執拗に舐めるといった行動は、強い痒みのサインです。
▼症状が出やすい場所
- 顔(目の周り、口の周り)
- 耳
- 足先
- 脇の下、内股
- お腹
- 肛門の周り
痒みが続くと、掻き壊しによる脱毛、赤み、湿疹、皮膚の肥厚(分厚くなること)といった皮膚炎に進行します。また、繰り返し発症する外耳炎も、食物アレルギーが背景にあるケースが少なくありません。
消化器系に現れる症状:嘔吐や下痢
皮膚症状と並行して、あるいは単独で消化器症状が現れることもあります。
- 慢性的な軟便や下痢
- 頻繁な嘔吐
- 食後の腹鳴(お腹がゴロゴロ鳴る)
- おならが増える
これらの消化器症状は、フードを変えてもなかなか改善しない場合に食物アレルギーが疑われます。特に、皮膚の痒みと下痢を併発している場合は、その可能性がより高まります。
その他の症状とアトピー性皮膚炎との違い
上記のほかにも、目の周りが赤くなる結膜炎や、元気・食欲の低下といった症状が見られることもあります。
犬のアレルギー性皮膚炎には、食物アレルギーの他に、ハウスダストや花粉などが原因の「アトピー性皮膚炎」があります。アトピーは季節によって症状が悪化しやすいのに対し、食物アレルギーは原因食物を摂取し続ける限り、季節を問わず症状が続くのが特徴です。ただし、両方を併発しているケースも多いため、正確な診断には獣医師による総合的な判断が不可欠です。
食物アレルギーの診断方法|動物病院での検査と費用は?

ペットに食物アレルギーが疑われる場合、自己判断せず、まずは動物病院で獣医師に相談することが重要です。原因アレルゲンを特定するためには、専門的な検査が必要となります。
確定診断のゴールドスタンダード「食物除去試験」
現在、食物アレルギーの最も信頼性の高い診断方法は「食物除去試験」です。
【食物除去試験の流れ】
- 除去食の開始:獣医師の指導のもと、今まで食べたことのないタンパク質源で作られた「除去食療法食」や「加水分解タンパク質フード」を8〜12週間程度与える。期間中、おやつや人の食べ物は一切禁止。
- 症状の改善を確認:皮膚の痒みや消化器症状が明らかに改善するかを観察する。
- 食物負荷試験の実施:症状改善後、元の食事や疑わしい食材を少量与え、症状が再発するかを確認する。
- 確定診断:症状が再発すれば、その食材がアレルゲンであったと確定できる。
時間と手間がかかりますが、原因を特定するための最も確実な検査です。
血液検査(アレルギー検査)で何がわかる?
血液を採取し、特定の食物に対する抗体(IgE抗体)の量を調べるアレルギー検査もあります。一度の採血で多くの項目を調べられるメリットがありますが、結果の解釈には注意が必要です。
血液検査の結果は、あくまでアレルゲンの候補を絞り込むための参考情報として用いられ、これだけで確定診断はできません。確定診断には前述の食物除去試験が必要です。検査費用は、調べる項目数にもよりますが、数万円程度かかるのが一般的です。
獣医師への相談の重要性
食物アレルギーの診断と対策は、獣医師との連携が不可欠です。症状が似ている他の病気の可能性を排除し、ペットの状態に合わせた最適な検査や食事管理を提案してもらう必要があります。動物病院へ行く際は、症状や食事の履歴を記録したメモを持参すると診察がスムーズに進みます。
アレルギー対策の要!フード選びの4つのポイント

食物アレルギーの管理において、最も重要なのがフード選びです。アレルゲンを食事から完全に除去することが治療の基本となります。
ポイント1:アレルゲンを特定し、それを避ける
食物除去試験でアレルゲンが特定できた場合、その原材料が含まれていないフードを選ぶことが大前提です。購入時は必ずパッケージ裏面の原材料表示を隅々まで確認しましょう。「チキンミール」「加水分解チキンエキス」のように、同じ動物由来でも様々な表記があるため注意が必要です。
ポイント2:「療法食」の種類と特徴
動物病院で処方される療法食は、食事管理の中心的な役割を果たします。主に2種類あります。
新奇タンパク質食
新奇タンパク質食
- 特徴: ペットがこれまで食べた経験のない珍しいタンパク質源(例:鹿、カンガルー、特定の魚など)で作られたフード。
- 理由: 食べたことがないタンパク質には免疫が反応しにくいため、アレルギー症状が出にくいと考えられています。
加水分解タンパク質食
加水分解タンパク質食
- 特徴: アレルギーの原因となりやすいタンパク質を、酵素などで非常に細かく分解(加水分解)したフード。
- 理由: タンパク質を免疫システムがアレルゲンとして認識できないくらい小さくすることで、アレルギー反応を防ぎます。
ポイント3:「低アレルゲンフード」や「グレインフリー」の考え方
市販の「低アレルゲン」や「アレルギー対応」フードは、アレルギーの原因になりやすいとされる特定の原材料を避けるなどの配慮がされています。アレルゲンが特定できていれば選択肢になりますが、基準はメーカーによって異なるため、必ず原材料を確認しましょう。
また、「グレインフリー(穀物不使用)」が必ずしも食物アレルギー対策になるわけではありません。アレルゲンは穀物よりも肉や魚などのタンパク質であることが多いため、穀物アレルギーと診断された場合を除き、グレインフリーに固執する必要はありません。
ポイント4:子犬・子猫の場合のフード選び
成長期の子犬・子猫が食物アレルギーと診断された場合、アレルゲン対策と同時に健全な発育に必要な栄養バランスの確保が重要です。自己判断で成犬・成猫用の療法食を与えると栄養不足になる可能性があります。必ず獣医師に相談し、成長ステージに合ったアレルギー対応の療法食を選びましょう。
食事管理と日常ケアでアレルギー症状をコントロール

適切なフードを選んだ後も、日々の管理とケアを継続することが症状を安定させる鍵となります。
フードの切り替えは慎重に
新しいフードに切り替える際は、1〜2週間かけてゆっくり行いましょう。今までのフードに新しいフードを少量混ぜ、便の状態などを見ながら徐々に割合を増やしていきます。急な切り替えは、下痢や嘔吐の原因になることがあります。
おやつやトッピングにも注意が必要
せっかくアレルギー対応フードを選んでも、おやつにアレルゲンが含まれていては意味がありません。市販のおやつや歯磨きガムも必ず原材料をチェックしましょう。人の食べ物を与えるのは厳禁です。家族全員でルールを共有し、アレルゲンを完全に除去する食事管理を徹底しましょう。
スキンケアや環境整備も並行して行う
食物アレルギーによって皮膚のバリア機能が低下している場合、外部からの刺激にも敏感になりがちです。獣医師の指示に従い、薬用シャンプーや保湿剤でスキンケアを行いましょう。アトピー性皮膚炎を併発していることも多いため、こまめな掃除でハウスダストを減らすなど、生活環境を清潔に保つことも症状の緩和につながります。
まとめ:正しい知識でペットのアレルギーと向き合い、食事管理を徹底しよう

犬と猫の食物アレルギーは、適切な対策と食事管理によって十分にコントロール可能な病気です。
- 原因:特定の食べ物のタンパク質への免疫の過剰反応。
- 症状:季節を問わない皮膚の痒み、皮膚炎、慢性的な下痢や嘔吐。
- 診断:最も確実な方法は、獣医師の指導のもとで行う「食物除去試験」。
- 対策:アレルゲンを含まないフード(療法食など)を選び、食事管理を徹底する。
- 日常ケア:おやつの管理やスキンケアといった対策も重要。
愛犬・愛猫にアレルギーが疑われる症状が見られたら、まずは動物病院で獣医師に相談してください。専門家と共に原因を突き止め、その子に合ったフードとケアプランを見つけることが、症状改善への一番の近道です。
よくある質問(FAQ)

Q1: 犬や猫の食物アレルギーは治りますか?
A1: 食物アレルギーは体質的なものであるため、「完治」するという概念はあまりありません。しかし、原因となるアレルゲンを食事から除去する「食事管理」を徹底することで、症状を出さずに健康な状態を維持することは十分に可能です。アレルギーと上手く付き合っていくという考え方が重要になります。
Q2: アレルギー対応フードはどこで買えますか?
A2: 「療法食」は獣医師の診断と処方が必要なため、基本的には動物病院でのみ購入できます。許可があればオンラインで購入できるサイトもあります。市販の「低アレルゲンフード」はペットショップやオンラインストアで販売されていますが、購入前に必ず原材料を確認してください。
Q3: 手作り食でアレルギー対策はできますか?
A3: 理論上は可能ですが、推奨はされません。犬や猫に必要な栄養素をバランス良く配合した食事を家庭で作り続けるのは非常に難しく、栄養偏りによる別の健康問題を引き起こすリスクがあります。手作り食を検討する場合は、必ずペット栄養管理士の資格を持つ獣医師に相談し、専門的な指導のもとでレシピを作成してもらいましょう。
- 犬猫の食物アレルギーは、特定の食べ物のタンパク質に対する免疫反応で生じ、皮膚炎や消化器症状が現れます。
- 正確な診断には食物除去試験が必須であり、自己判断せず動物病院での相談が症状改善の鍵です。
- アレルギー対策の基本は、アレルゲンを含まない療法食を選択し、食事管理を徹底することです。
- フードの切り替えやおやつ、人からの食べ物にも注意し、慎重な食事管理を家族全体で実践しましょう。
- 日々のスキンケアや生活環境の整備も並行して行い、獣医師と連携しながらアレルギーと上手く付き合いましょう。
初回公開日:2025年11月26日
記載されている内容は2025年11月26日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。