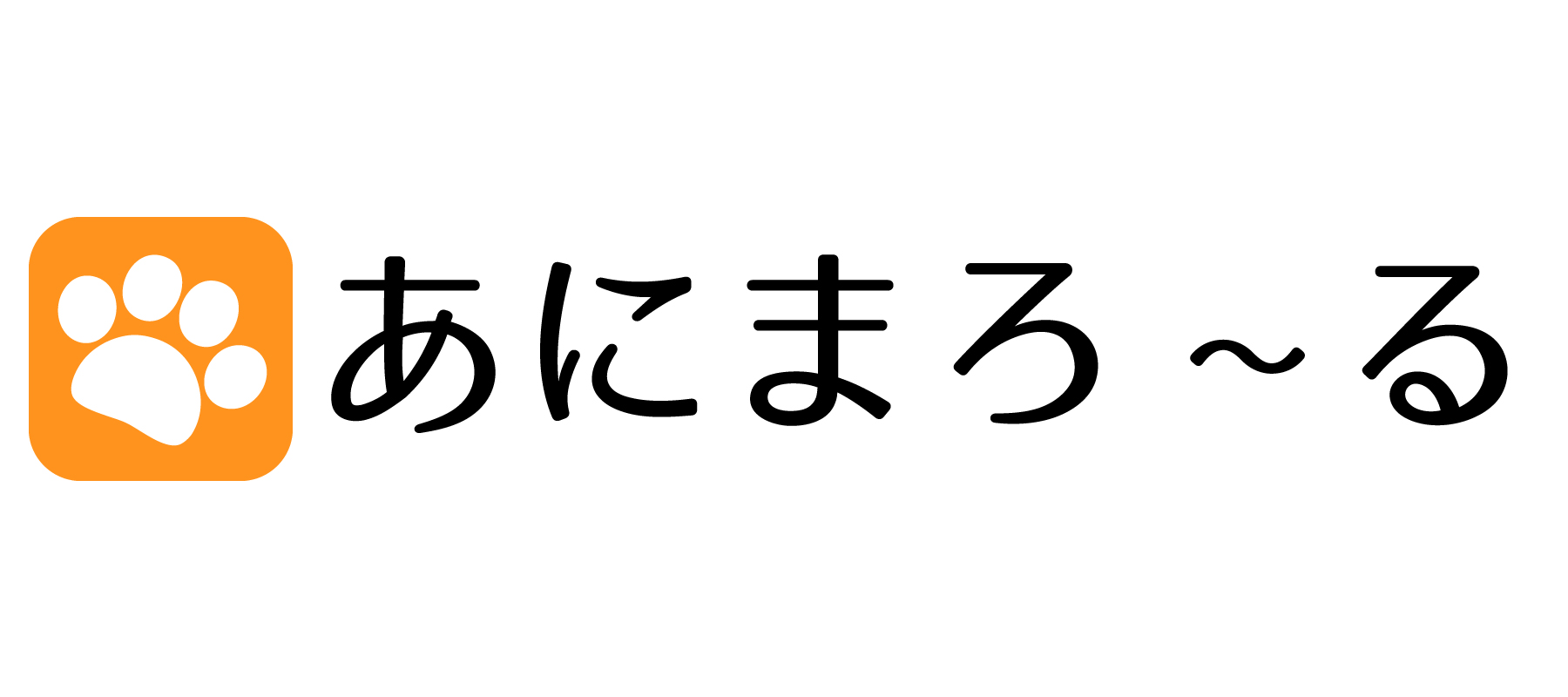ペット用IoT機器おすすめ15選|見守り・給餌・健康管理ができるスマートペット家電総まとめ
更新日:2025年11月08日

- ペット用IoT機器は、外出先からスマホでペットを見守り、お世話ができるスマート家電の総称です。
- 留守中の不安解消、正確な食事・健康管理、室温維持による安全確保など、多くのメリットがあります。
- 初期費用やWi-Fi環境の整備、セキュリティ対策が必要な点には注意が必要です。
- 見守り、食事、健康管理など目的に合わせて、カメラ、自動給餌器、スマートトイレなどの製品を選びましょう。
- 2025年最新のおすすめ製品15選を目的別に比較し、ペットとの暮らしを豊かにするヒントを提供します。
仕事や外出で家を空けるとき、「うちの子、元気にしているかな?」「ごはん、ちゃんと食べたかな?」と、留守番中のペットのことが気になってしまう飼い主さんは多いでしょう。そんな不安を解消し、ペットとの暮らしをより豊かで安心なものに変えてくれるのが「ペット用IoT機器」です。
この記事では、最新のスマートペット家電の魅力から、具体的な選び方、目的別のおすすめ製品まで、スマート飼育を始めるための情報を網羅的に解説します。
この記事でわかること
- ペットIoT機器(スマートペット家電)の基本と仕組み
- 導入する5つのメリットと知っておくべき4つのデメリット
- 目的別(見守り・食事・健康管理)の失敗しない選び方
- 【2025年】最新のおすすめペットIoT機器15選を徹底比較
- 導入に関するよくある質問(FAQ)
そもそもペット用IoT機器(スマートペット家電)とは?

ペット用IoT機器とは、インターネットに接続されたペット向けの家電製品のことです。「Internet of Things(モノのインターネット)」の技術を活用し、スマホの専用アプリと連携させることで、外出先からでもペットの様子を確認したり、お世話をしたりできる画期的なアイテムを指します。一般的には「スマートペット家電」とも呼ばれています。
これらのIoTデバイスにはカメラやセンサーが搭載されており、ペットの行動パターンや健康状態に関する様々なデータを収集・記録します。
- ペットカメラ:留守中の姿をリアルタイムで確認。AIが吠えやいたずらを検知し、スマホに通知する機能も。
- 自動給餌器(自動餌やり機):設定した時間に設定した量のごはんを自動で提供。肥満防止や正確な食事管理に貢献。
- スマートトイレ・給水器:排泄回数や飲水量を記録し、日々の健康状態をデータとして可視化。病気の早期発見をサポート。
このように、ペット用IoT機器は単なる便利グッズではありません。遠隔操作によるお世話、データの収集と分析を通じて、ペットの安全と健康を見守り、飼い主との絆を深める「スマート飼育」を実現するための重要なツールなのです。
ペット用IoT機器を導入する5つの大きなメリット

スマート飼育を始めることで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、ペット用IoT機器を導入する主な5つの利点について詳しく解説します。
メリット1:留守中のペットの様子がわかり、いつでも安心できる
最大のメリットは、飼い主が留守中でもペットの様子をリアルタイムで確認できる「安心感」です。高画質のペット見守りカメラを使えば、スマホアプリを通じて、いつでもどこでも愛犬や愛猫が元気に過ごしているかを確認できます。暗視機能付きなら、夜間や暗い部屋でも鮮明です。
また、マイクとスピーカー内蔵モデルなら、外出先からペットに話しかけることも可能。飼い主の声を聞かせることで、ペットの寂しさやストレス軽減につながります。異常な動きや鳴き声を検知して通知する機能があれば、万が一の事態にも迅速に対応できるでしょう。
メリット2:正確な食事・飲水管理で健康を維持できる
自動給餌器やスマート給水器は、ペットの健康管理において非常に強力なツールです。特に自動餌やり機は、タイマー機能で決まった時間に決まった量のごはんを正確に提供できます。これにより、食べ過ぎによる肥満を防いだり、早食いを防止したりする効果が期待できます。
多頭飼いの家庭では、個体別に給餌設定ができる製品で横取り問題も解決。スマート給水器は、フィルターで水を清潔に保ち、飲水量をアプリで記録・管理できます。飲水量の変化は泌尿器系の病気のサインでもあるため、データを獣医に見せることで、より的確な診断につながることもあります。
メリット3:ペットの健康状態の異常を早期に発見できる
近年のペット用IoT機器は、日々の活動データを蓄積し、健康状態の変化を知らせてくれる「デジタルヘルス」の役割も担っています。
- ウェアラブルデバイス:首輪やハーネスに装着し、運動量、睡眠時間、消費カロリーなどを記録。
- スマートトイレ(猫用):体重、尿の量や回数を自動で計測。普段と違うデータが続くとアプリが異常を通知。
言葉を話せないペットの体調変化は、飼い主でも気づきにくいもの。客観的なデータがあれば、病気のサインを早期に捉え、大事に至る前に獣医に相談するきっかけになります。
メリット4:快適な室温維持で熱中症や低体温症を予防する
ペットは人間よりも温度変化に敏感です。夏場の熱中症や冬場の低体温症は命に関わります。スマート温湿度計とスマートリモコンを連携させれば、このリスクを大幅に減らせます。
室内の温度や湿度をセンサーが常に監視し、設定した範囲から外れるとスマホに通知。外出先から遠隔操作でエアコンの電源を入れたり、温度設定を変更したりできます。これにより、ペットが常に快適な環境で過ごせるようになります。
メリット5:遠隔からのコミュニケーションでストレスを軽減する
留守番の時間は、ペットにとって退屈で寂しいものです。見守りカメラの中には、おやつが飛び出す機能や、レーザーポインターで遊べる機能を搭載した製品があります。
外出先の休憩時間にアプリを操作しておやつをあげたり、一緒に遊んであげたりすることで、ペットの孤独感や退屈を紛らわせ、ストレス軽減に繋がります。双方向の会話機能で優しく話しかけるだけでも、ペットは安心感を得られるでしょう。
知っておきたいペット用IoT機器のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方、導入にはいくつかの注意点も存在します。購入してから後悔しないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
デメリット1:初期費用やランニングコストがかかる
高機能な製品は数万円程度の初期費用がかかります。複数のデバイスを揃えると、それなりの出費に。また、製品によっては、クラウド録画やAI分析機能の利用に月額料金(サブスクリプション)が発生する場合があります。購入前に本体価格だけでなく、維持費も確認しましょう。
デメリット2:安定したWi-Fi環境や初期設定が必要
ほとんどの製品は、遠隔操作のために常時Wi-Fi接続が必要です。自宅に安定したWi-Fi環境がない場合、まずはネット環境の整備から始めなければなりません。また、購入後にはWi-Fi接続やアプリのアカウント登録などの初期設定が必要です。
デメリット3:故障や誤作動、停電時のリスク
精密な電子機器であるため、故障や誤作動のリスクはゼロではありません。自動給餌器が作動しない、停電でカメラが映らないといった事態も考えられます。特に食事や温度管理など、ペットの生命に直結する機能に完全に依存するのは危険です。長期間家を空ける際は、家族やペットシッターにお願いするなど、バックアップも考えておきましょう。
デメリット4:プライバシーとセキュリティへの配慮
見守りカメラは室内の映像をインターネット経由で送信するため、セキュリティ確保が非常に重要です。不正アクセスやハッキングのリスクを避けるため、信頼できるメーカーの製品を選び、パスワードを複雑にする、ファームウェアを最新に保つなどの対策を徹底しましょう。レンズを物理的に隠せるプライバシーシャッター機能付きのカメラもおすすめです。
【目的別】失敗しないペット用IoT機器の選び方とポイント

数多くの製品の中から、自分の目的やペットに合った最適なデバイスを選ぶためのポイントを目的別に解説します。
選び方1:「留守中の見守り」が目的ならペットカメラ
留守番中のペットの様子を確認したいなら、ペット見守りカメラが最適です。以下のポイントをチェックしましょう。
- 画質:ペットの表情まで見るならフルHD(1080p)以上がおすすめ。
- 首振り機能:部屋全体を見渡せるパン・チルト機能があると便利。
- 暗視機能:夜間や暗い部屋での使用には必須。
- 双方向会話機能:外出先からペットに話しかけたい場合に。
- 付加機能:おやつ機能、レーザーポインター、AIによる異常検知(鳴き声、動き)など。
選び方2:「食事・飲水管理」が目的なら自動給餌器・給水器
ペットの肥満防止や健康維持には、自動給餌器やスマート給水器が役立ちます。
- 自動給餌器のポイント:給餌量・回数の設定の細かさ、フードタンクの容量、対応フードサイズ、手入れのしやすさ(パーツを丸洗いできるか)。多頭飼いなら個体識別機能付きが便利。
- スマート給水器のポイント:フィルターの性能と交換頻度、タンク容量、静音性。
選び方3:「日々の健康管理」が目的ならスマートトイレやウェアラブル
より詳細な健康データを取得したい場合は、以下のデバイスが選択肢になります。
- スマートトイレ(猫用):体重や尿量・回数を自動記録し、泌尿器系疾患の早期発見に貢献。多頭飼いの場合は個体識別機能が重要。
- ウェアラブルデバイス(首輪型):活動量や睡眠パターンを記録し、運動不足や体調の変化を通知。獣医とデータを共有できる機能も。
選び方4:「室内の安全対策」が目的ならスマートセンサー類
ペットが快適かつ安全に過ごせる環境を整えるには、各種センサーが有効です。
- スマート温湿度計+スマートリモコン:夏・冬の温度管理に必須。室温を監視し、異常があればエアコンを遠隔操作。
- 開閉センサー:ドアや窓に設置し、ペットの脱走を検知して通知。
【2025年最新】目的別!おすすめのペット用IoT機器15選

選び方を踏まえ、おすすめのペット用IoT機器を「見守りカメラ」「自動給餌器・給水器」「ヘルスケアデバイス」の3つのカテゴリに分けてご紹介します。
留守番中の見守りに最適!おすすめペットカメラ5選
- Furbo(ファーボ)ドッグカメラ:犬の飼い主に人気の定番カメラ。高画質映像、双方向会話に加え、スマホからおやつをあげられる機能が特徴。AIが犬の鳴き声や活動を検知し通知します。
- SwitchBot 見守りカメラ 3MP:高コスパで人気のモデル。300万画素の高画質と360°の首振り機能で部屋の隅々まで確認可能。プライバシーモードも搭載し、同社のスマート家電との連携もスムーズ。
- Google Nest Cam(屋内用、バッテリー式):シンプルなデザインと簡単な設定が魅力。人、動物、車両を区別する高度なAI検知機能を搭載。Google Homeとの連携でスマートホームの中核としても機能します。
- みてるちゃん猫:猫の見守りに特化した機能を搭載。自動追尾機能で動き回る猫を逃さず捉えます。クラウド録画のプランも手頃で、長期の記録にも向いています。
- パナソニック HDペットカメラ KX-HDN215:国内大手メーカーならではの安心感。温度センサーを搭載し、設定範囲を超えると通知が来るため室温管理も同時に行えます。動作検知時の録画機能も充実。
正確な食事管理を実現!おすすめ自動給餌器・給水器5選
- PETKIT P5 自動給餌器:洗練されたデザインが人気の自動給餌器。専用アプリで細かく給餌スケジュールを設定可能。フードの残量センサーや、停電時も安心の電池駆動にも対応しています。
- カリカリマシーンSP:スマホ連動型のロングセラーモデル。1日4回まで10g単位で給餌量を設定可能。飼い主の声を録音して給餌時に再生する機能もあり、ペットも安心して食事できます。
- PETKIT Eversweet 3 Pro(給水器):ワイヤレスポンプ採用で手入れが非常に簡単なスマート給水器。フィルターで水を常に清潔に保ち、アプリで水質や残量を確認できます。静音性にも優れています。
- プラスアクア(給水器):獣医師推奨の給水器。コードレスでどこにでも置ける手軽さが魅力。3段階のろ過フィルターで不純物を除去。飲水量の計測機能はありませんが、清潔な水を提供できます。
- Take-One P1 Lite:多頭飼いにおすすめのカメラ付き自動給餌器。2WAYトレイ付属で2匹同時にごはんをあげられます。カメラで食事の様子を確認できるのも安心ポイントです。
健康状態をデータ化!おすすめスマートヘルスケアデバイス5選
- PETKIT Pura X(スマートトイレ):猫のトイレ掃除を自動化し、体重やトイレの滞在時間・回数を記録する全自動スマートトイレ。専用アプリで健康データを管理し、異常があれば通知します。
- toletta(トレッタ)猫用スマートトイレ:AIカメラが猫の顔を認識し、多頭飼いでも個別に体重・尿量・回数などを記録。獣医師と共同開発されたシステムで、日々のデータから健康状態の変化をチェックできます。
- CATlog(キャトログ):猫の首輪に装着するウェアラブルデバイス。「走る」「歩く」「睡眠」「食事」などの行動を24時間記録し、行動パターンを分析。普段と違う様子があればアプリでお知らせします。
- Animo(アニモ)犬用行動モニター:犬の行動と睡眠の質を学習し、吠える、ひっかくなどの行動の変化や活動量の低下を検知。分離不安などのストレスサインに気づくきっかけになります。
- SwitchBot 温湿度計プラス:ペットがいる部屋の温度・湿度を正確にモニタリング。画面が大きく見やすいのが特徴。SwitchBotハブミニと連携すれば、外出先から室温を確認し、エアコンを操作できます。
ペット用IoT機器に関するよくある質問(FAQ)
Q1: 自宅にWi-Fiがないと使えませんか?
A1: ほとんどの製品は、スマホとの連携や遠隔操作のためにWi-Fi接続が必須です。一部、Bluetooth接続のみで利用できる製品もありますが機能が限定されます。導入を検討する際は、まず安定したWi-Fi環境を整えることをおすすめします。
Q2: 機械が苦手でも設定は簡単ですか?
A2: 多くの製品は、専用アプリの指示に従うだけで比較的簡単に初期設定ができるように設計されています。説明書や公式サイトのサポートも充実しています。不安な場合は、国内メーカーやカスタマーサポートが手厚い製品を選ぶと良いでしょう。
Q3: カメラのプライバシーは大丈夫ですか?
A3: 信頼性の高いメーカーは通信の暗号化などセキュリティ対策を施しています。利用者側でも、推測されにくい複雑なパスワードを設定する、二段階認証を利用する、不要な時はプライバシーモードを利用するといった対策が大切です。
Q4: 複数のデバイスを1つのアプリで管理できますか?
A4: 同じメーカーの製品であれば、1つのアプリで一元管理できる場合がほとんどです。例えばSwitchBot社製品なら、カメラ、温湿度計、リモコンなどを「SwitchBotアプリ」一つで連携・操作できます。本格的に導入するならメーカーを揃えるのも便利です。
まとめ:スマート飼育でペットとの暮らしをより豊かに

ペット用IoT機器は、留守中の不安を和らげ、日々の健康管理をサポートし、ペットとのコミュニケーションをより密にしてくれる素晴らしいツールです。見守りカメラや自動餌やり機、スマートトイレなどを組み合わせることで、ペットはより安全で快適に、飼い主はより安心して毎日を過ごせるようになります。
もちろん、導入にはコストや設定の手間といった側面もありますが、それ以上に得られるメリットは大きいでしょう。この記事で紹介した選び方やおすすめ製品を参考に、あなたのライフスタイルや愛するペットに最適なスマートデバイスを見つけてみてください。スマート飼育は、ペットとの絆をさらに深め、かけがのない毎日をもっと豊かにしてくれるはずです。
- ペット用IoT機器は、外出先からペットを見守り、食事や健康状態を管理できる便利なツールです。
- 安心感の向上、正確な健康維持、異常の早期発見、快適な環境提供、遠隔コミュニケーションが主なメリットです。
- 初期費用、Wi-Fi環境、故障リスク、セキュリティ対策など、導入前に確認すべき注意点もあります。
- 見守りカメラ、自動給餌器、スマートトイレなど、目的とペットの状況に合わせて最適な製品を選びましょう。
- 賢くIoT機器を活用し、ペットとの生活の質を向上させ、より豊かな毎日を実現してください。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。