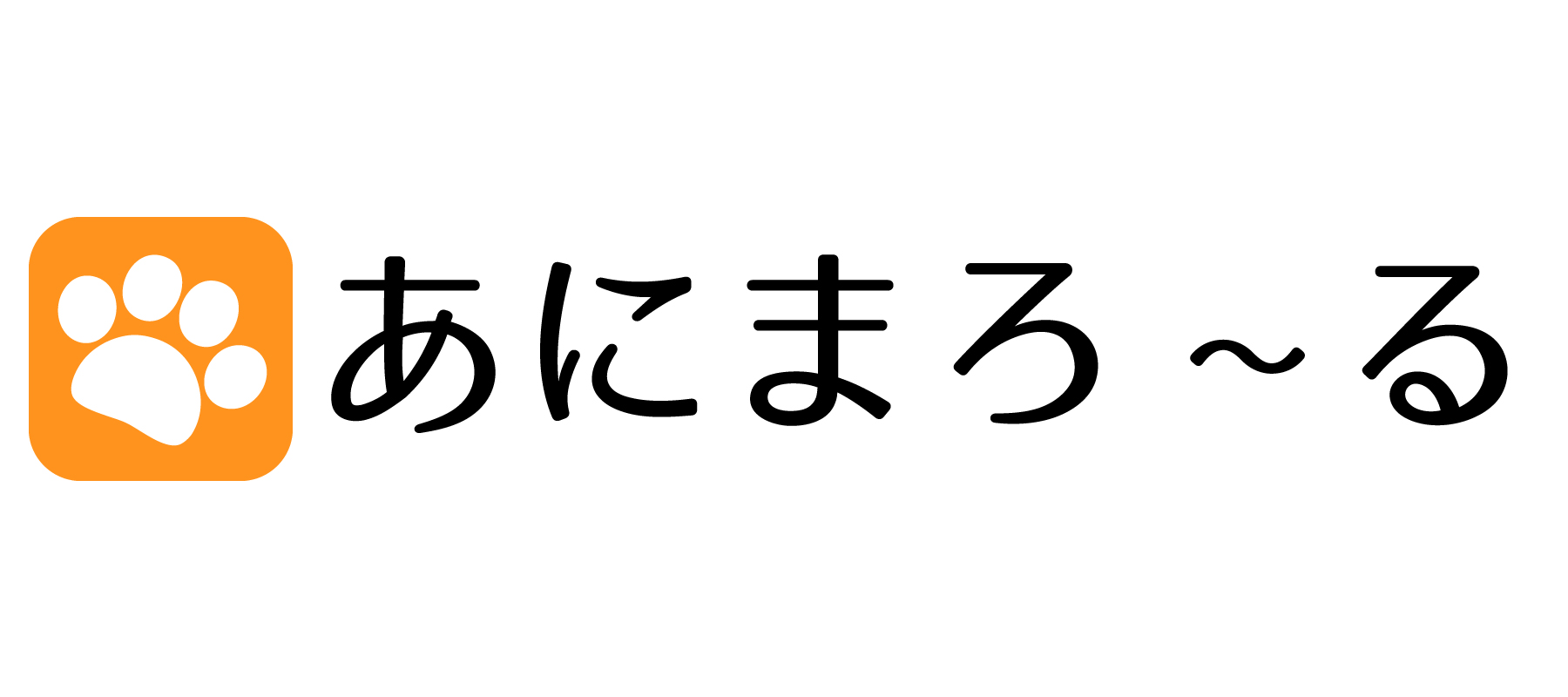犬の認知症とは?原因・初期症状・老化との違いを獣医師監修でわかりやすく解説【早期発見が鍵】
更新日:2025年11月08日

- 老犬の認知症は「犬の認知機能不全症候群(CDS)」と呼ばれ、加齢に伴う脳機能の低下が原因で発生します。
- 夜鳴きや徘徊、トイレの失敗、昼夜逆転などが主な初期症状であり、これらのサインに早期に気づくことが重要です。
- 安全な生活環境の整備、優しいコミュニケーション、脳への刺激、適切な食事やサプリメントが認知症のケアと予防に繋がります。
- 認知症は完治しませんが、適切な治療と飼い主さんの根気強いケアにより、愛犬との穏やかな生活を長く維持できます。
- 気になる症状があれば、一人で抱え込まず、獣医師に相談することが愛犬のQOL向上に繋がります。
老犬の認知症【初期症状】見逃したくない10のサイン

犬の認知症(認知機能不全症候群)は、ゆっくりと進行するため、初期段階では飼い主さんも気づきにくいことがあります。しかし、日々の暮らしの中に隠された「予兆」を見逃さないことが、早期対応の鍵となります。まずは、認知症の代表的なサインを理解し、愛犬の行動に変化がないか注意深く観察してみましょう。
1. 目的もなくウロウロ歩き回る(徘徊)
壁に沿って歩き続けたり、部屋の隅で動けなくなったり、同じ場所をぐるぐると回り続ける行動は、認知症の典型的な症状の一つです。これは空間認識能力の低下が原因で、犬自身も混乱している状態です。
2. 夜中に理由なく鳴き続ける(夜鳴き)
昼夜のリズムが崩れ、夜間に不安を感じて大きな声で鳴き続けることがあります。この夜鳴きは、飼い主さんの睡眠不足にも繋がり、介護の大きなストレスになるケースも少なくありません。
3. トイレの失敗が増える(排泄の問題)
これまで完璧だったトイレの場所がわからなくなったり、粗相が増えたりします。これは単なるしつけの問題ではなく、脳機能の低下によるものです。散歩中に排泄をしなくなることもあります。
4. 飼い主や家族がわからなくなる
長年連れ添った飼い主さんの顔を認識できなくなったり、名前を呼んでも反応が鈍くなったりします。ぼーっとしている時間が増え、まるで別の犬になってしまったかのように感じることもあります。
5. 睡眠サイクルの乱れ(昼夜逆転)
日中は寝てばかりいるのに、夜になると起きて活動を始める「昼夜逆転」の症状が見られます。体内時計が狂ってしまうことで、犬自身の睡眠の質も低下します。
6. 食欲の異常な増減
食欲が異常に旺盛になり、食べたばかりなのにご飯を催促したり、逆に全く興味を示さなくなったりと、食欲に極端な変化が現れることがあります。
7. 狭い場所に入りたがり、後ずさりできない
家具の隙間や部屋の隅など、狭い場所に入り込んだまま出られなくなることがあります。これは、後ずさりするという行動がわからなくなってしまうためです。
8. 感情の起伏が激しくなる(攻撃的・無気力)
穏やかだった性格が急に攻撃的になったり、逆に大好きだった散歩やおもちゃに全く興味を示さなくなったりと、感情のコントロールが難しくなります。
9. 日常的な習慣を忘れる
「おすわり」や「まて」などのコマンドを忘れてしまったり、散歩のルートがわからなくなったり、これまでできていた日常の習慣が困難になります。
10. 音や物への反応が鈍くなる
玄関のチャイムや電話の音など、以前は反応していた物音に無反応になることがあります。聴力の低下だけでなく、認知機能の低下が原因の場合もあります。
自宅で簡単!犬の認知症セルフチェックリスト

愛犬の様子が気になったら、以下の項目をチェックしてみましょう。複数当てはまる場合は、認知症の可能性があるため、早めに動物病院に相談することをおすすめします。
- 名前の呼びかけへの反応が薄い、または無視する
- 目的もなく部屋の中を歩き回っている
- 壁や家具にぶつかることが増えた
- 夜中に何度も起きたり、鳴いたりする
- 日中、寝ている時間が極端に長くなった
- トイレ以外の場所で排泄してしまう
- ご飯を食べたことを忘れ、すぐに催促する
- 大好きだった散歩に行きたがらない
- 狭い場所に入って動けなくなっている
- 家族に対して唸ったり、噛み付こうとしたりする
- ぼーっと一点を見つめている時間が増えた
犬の認知症(認知機能不全症候群)とは?原因と老化との違いを解説

犬の認知症は、正式には「犬の認知機能不全症候群(CDS)」と呼ばれます。加齢に伴い脳の神経細胞がダメージを受け、認知機能が低下することで様々な行動変化が起こる病気です。11〜12歳の犬の約3割、15〜16歳になると約7割が何らかの症状を示すというデータもあり、決して珍しい病気ではありません。
認知症のメカニズムと原因
犬の認知症の明確な原因はまだ完全には解明されていません。しかし、人間のアルツハイマー病と同様に、脳内にβアミロイドというタンパク質が蓄積し、神経細胞を破壊することが一因と考えられています。これにより、脳が萎縮し、記憶力、学習能力、空間認識能力といった認知機能が低下していくのです。
単なる「老化」との見分け方
「年を取ったから仕方ない」と見過ごされがちですが、認知症は単なる老化現象とは異なります。
- 老化による身体機能の低下: 耳が遠くなる、目が見えにくくなるなど。
- 認知症による脳機能の低下: 音は聞こえているはずなのに反応しない、見えているはずなのに飼い主を認識できないなど。
老化の場合、行動の変化は比較的緩やかですが、認知症の場合は、これまでできていたことが急にできなくなる、不可解な行動が増えるといった特徴があります。見分け方が難しい場合は、自己判断せず獣医師に相談することが重要です。
老犬の認知症ケア|今日からできる具体的な対策

愛犬が認知症と診断されても、悲観的になる必要はありません。飼い主さんの適切なケアで症状の進行を緩やかにし、愛犬が安心して暮らせる環境を整えることができます。大切なのは、変わってしまった愛犬を受け入れ、根気強く寄り添うことです。
1. 安全な生活環境を整える
認知症の犬にとって、住み慣れた家も危険な場所になり得ます。徘徊による怪我や事故を防ぐため、安全な居住空間を確保しましょう。
- 滑りにくい床材にする:フローリングにはカーペットやコルクマットを敷き、転倒を防ぎます。
- 危険な場所へのアクセスを制限する:階段や玄関にはペットゲートを設置します。ストーブやコード類も片付けましょう。
- 家具の配置を見直す:徘徊ルートを確保し、家具の角にクッション材をつけるなど工夫します。
- トイレの環境を整える:寝床の近くなど複数箇所にトイレシートを敷きましょう。おむつの利用も有効です。
2. 不安を取り除く接し方・コミュニケーション
認知症の犬は常に不安を抱えています。飼い主さんの優しい接し方が、何よりの薬になります。
- 叱らない、怒らない:トイレの失敗や夜鳴きは、犬自身もコントロールできません。叱ることは犬の不安を煽り、症状を悪化させる可能性があります。
- 優しく声をかける:「大丈夫だよ」と優しく話しかけ、安心感を与えましょう。耳が遠い場合は、少し高めの声でゆっくり話すと伝わりやすいです。
- スキンシップを増やす:優しく撫でたり、マッサージをしたりすることで、犬のストレスを和らげます。
3.【症状別】夜鳴き・徘徊・トイレ失敗への対策
特に飼い主さんの負担が大きい症状には、個別の対策が必要です。
- 夜鳴き対策:昼夜逆転が原因の場合、日中に適度な運動や刺激で疲れさせることが有効です。動物病院で精神を安定させる薬やサプリメントを処方してもらうこともできます。
- 徘徊対策:安全が確保された部屋やサークルの中で自由に歩かせましょう。無理に止めようとすると、かえって興奮させてしまうことがあります。
- 排泄の失敗対策:叱らずに淡々と片付け、消臭スプレーで臭いを完全に消します。排泄のタイミングを記録し、トイレに誘導するのも効果的です。おむつやマナーベルトも活用しましょう。
犬の認知症を予防するには?進行を遅らせるリハビリ方法

認知症を完全に予防する方法はまだありません。しかし、日々の生活習慣を見直すことで、発症リスクを下げたり、進行を緩やかにしたりすることが期待できます。
脳への刺激がカギ!散歩と遊びの工夫
脳に適度な刺激を与え続けることは、認知機能の維持に繋がります。
- 散歩コースを変える:時々違うコースを歩き、新しい匂いや景色で脳を刺激しましょう。
- 五感を刺激する遊び:ノーズワーク(おやつ探しゲーム)や知育トイを取り入れ、嗅覚や思考力を刺激します。
- コミュニケーションを大切に:積極的に話しかけ、ブラッシングやマッサージなどのスキンシップで精神的な安定を促します。
食生活の見直し:認知症予防におすすめのフード・栄養素
脳の健康をサポートする栄養素を積極的に摂取することも、予防策の一つです。
- 抗酸化物質(ビタミンC、Eなど):脳細胞の老化の原因となる活性酸素を除去する働きがあります。
- DHA・EPA(オメガ3脂肪酸):脳の神経細胞を活性化させる効果が期待できます。青魚に多く含まれます。
- シニア犬向けのフード:消化しやすく、脳の健康維持に配慮されたシニア犬・ハイシニア犬向けのドッグフードを選びましょう。
サプリメントの活用は獣医師に相談を
DHA・EPAや中鎖脂肪酸(MCTオイル)など、認知機能の維持をサポートするサプリメントも市販されています。しかし、サプリメントはあくまで栄養補助食品です。必ずかかりつけの獣医師に相談し、愛犬の健康状態に合ったものを指導のもとで活用しましょう。
犬の認知症の治療法と動物病院との付き合い方

認知症の症状が見られたら、できるだけ早く動物病院を受診することが重要です。適切な診断と治療は、愛犬と飼い主のQOLを向上させます。
現代の獣医療でできる認知症の治療法
残念ながら、犬の認知症を完治させる治療法はまだ確立されていません。しかし、薬物療法、サプリメント、食事療法などを組み合わせ、症状の進行を遅らせたり、夜鳴きや徘徊といった行動を緩和させたりすることは可能です。治療の目的は、病気を治すことではなく、犬と飼い主が少しでも快適に暮らせるようにサポートすることです。
信頼できる動物病院の選び方と相談のポイント
老犬の介護は長期戦になるため、親身に相談に乗ってくれる獣医師を見つけることが大切です。
- 動画を持参する:気になる行動を動画で撮影していくと、正確に症状を伝えられます。
- メモを準備する:いつから、どのような頻度・状況でその行動が見られるかメモしておくと診察がスムーズです。
- 一人で悩まない:飼い主だけで悩まず、専門家である獣医師を頼ることが、より良いケアへの第一歩です。
老犬の認知症に関するQ&A
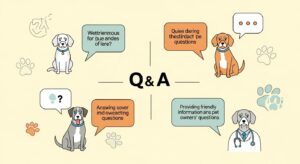
Q1: 認知症の末期症状はどのようなものですか?
A1: 認知症が末期になると、ほとんど寝たきりの状態になることが多く、自力での食事や排泄が困難になり全面的な介助が必要になります。昼夜を問わず鳴き続けたり、感情表現が乏しくなったりすることも。この段階では、犬の尊厳を守りつつ、いかに苦痛を和らげてあげるかがケアの焦点となります。
Q2: アロマテラピーは効果がありますか?
A2: ラベンダーなどのアロマはリラックス効果が期待できますが、犬は人間より嗅覚が鋭いため、使用には細心の注意が必要です。犬にとって有毒なアロマもあるため、必ず獣医師や専門家に相談してから安全な方法で取り入れてください。
Q3: 介護で飼い主が疲れてしまったらどうすればいいですか?
A3: 老犬の介護は心身ともに大きな負担です。飼い主さんが倒れては元も子もありません。決して一人で抱え込まず、家族と協力したり、かかりつけの動物病院、ペットシッター、老犬ホームなどの専門サービスに相談したりしましょう。飼い主さん自身の健康を守ることが最も重要です。
まとめ:老犬の認知症は早期発見と愛情あるケアが大切

老犬の認知症は、飼い主にとって辛い病気ですが、それは愛犬が長生きしてくれた証でもあります。大切なのは、認知症のサインを早期に発見し、病気を正しく理解し、愛犬が安心して過ごせる環境を整えてあげることです。
生活環境の見直し、脳への刺激、食事管理、そして何よりも飼い主さんの深い愛情と根気強いケアが、愛犬の穏やかな老後を支えます。愛犬との残された時間を大切にするために、日々の小さな変化に気づくことから始め、少しでも気になることがあれば迷わず動物病院に相談してください。
- 老犬の認知症は、早期発見と病気の正しい理解が愛犬の穏やかな老後を支える鍵となります。
- 安全な生活環境の整備、脳への適度な刺激、適切な食事管理、そして深い愛情によるケアが非常に重要です。
- 夜鳴きや徘徊、排泄の失敗といった症状には個別に対策し、愛犬が安心して過ごせる環境を整えましょう。
- 認知症は完治しない病気ですが、獣医師と連携し、症状の進行を遅らせる治療やケアを継続することが可能です。
- 飼い主さん一人で抱え込まず、家族や専門サービスを頼り、愛犬との残された時間を大切にしてください。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。