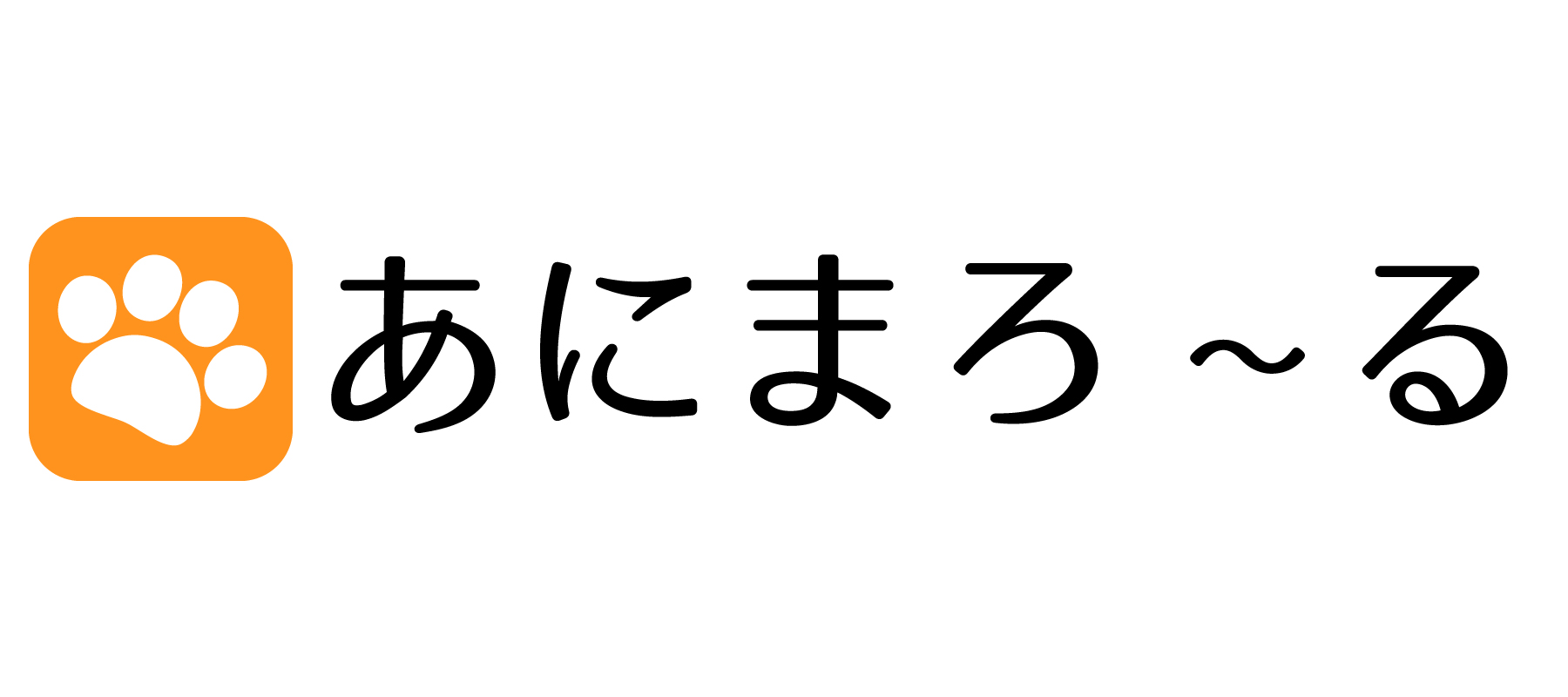猫の多頭飼いで喧嘩が起きる原因と解決法|仲良く暮らすための3つのポイント
更新日:2025年11月08日

- 猫の多頭飼いにおける喧嘩は、序列争いではなくテリトリーや資源の不足、相性、ストレスが主な原因です。
- 本気の喧嘩は威嚇音や爪を立てた攻撃などのサインで見分け、速やかに適切な方法で仲裁しましょう。
- 喧嘩解決には、猫の数に見合った十分な環境と資源の確保、飼い主の公平な対応が不可欠です。
- 新入り猫との対面は、隔離から段階的に進め、先住猫の気持ちを最優先に配慮することが重要です。
- 家庭での対策が難しい場合は、フェロモン剤の活用や行動診療科の専門家への相談も有効な手段です。
愛猫が2匹、3匹と増える多頭飼いは、猫たちがじゃれ合ったり、一緒に眠ったりする姿を見られる、飼い主にとって大きな喜びです。しかし、その一方で「猫同士の喧嘩が絶えない」「新入り猫を先住猫が威嚇する」といった悩みを抱える方も少なくありません。この問題の背景には、猫特有の「序列争い」が関係しているのでしょうか。
この記事では、猫の多頭飼いで喧嘩が起こる本当の理由を解き明かし、猫たちが安心して仲良く暮らすための具体的な3つのポイントを解説します。愛猫たちのストレスを減らし、穏やかな関係を築くためのヒントがきっと見つかるはずです。
猫の多頭飼いに「序列」は存在する?犬との違い

多頭飼いのトラブルと聞くと、まず「序列争い」という言葉を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、猫の社会における「序列」は、リーダーを頂点としたピラミッド型の階級社会を形成する犬のそれとは大きく異なります。
猫はもともと単独で狩りをして生活してきた動物であり、犬のように群れで協力して獲物を狩る習性がありません。そのため、猫同士の関係性には厳密な上下関係は存在しないとされています。猫の社会にあるのは、どちらが優位かという程度の緩やかな力関係です。「この場所は自分が優先的に使う」「ご飯は自分が先に食べる」といった、特定の状況における優先権のようなものだと考えられています。
この優先権をめぐる争いの根底にあるのが、猫の強い「テリトリー(縄張り)意識」です。自分のテリトリー内に他の猫が入ってくること、特に新入り猫が現れることは、自分の安全な空間や資源が脅かされる一大事。そのため、追い払おうとして威嚇や攻撃といった行動に出ることがあります。
つまり、猫の喧嘩は単純な上下関係を決めるためというより、自分のテリトリーと資源を守るための防衛行動という側面が強いのです。この習性を理解することが、多頭飼いの問題を解決する第一歩となります。
なぜ起こる?猫の多頭飼いで喧嘩や威嚇が起きる5つの理由

猫たちが争う背景には、序列の問題だけでなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは、喧嘩や威嚇を引き起こす主な5つの理由を詳しく見ていきましょう。
1. テリトリー(縄張り)争い
前述の通り、猫にとってテリトリーは非常に重要です。家の中を自分の縄張りだと認識している猫にとって、新参者の登場は大きなストレスとなります。特に、安心して食事をする場所、排泄をするトイレ、そして休息をとる寝床は、テリトリーの中でも特に重要な「コアエリア」です。
先住猫は、このコアエリアを新入り猫に侵害されることを極端に嫌います。新入り猫が自分の使っているトイレや食器に近づくだけで、威嚇したり攻撃したりすることがあります。これは、自分の安全な生活空間を守ろうとする本能的な行動なのです。
2. 資源(リソース)の奪い合い
猫にとっての「資源」とは、ご飯や水、トイレ、寝床、おもちゃ、そして飼い主からの愛情など、生きていく上で必要なものすべてを指します。これらの資源が十分にないと、猫たちの間で奪い合いが発生し、喧嘩の原因となります。
例えば、フードボウルが一つしかない場合、力の強い猫が独占してしまい、他の猫が安心してご飯を食べられません。また、飼い主の愛情も重要な資源です。新入り猫ばかりを可愛がっていると、先住猫が嫉妬し、攻撃的な行動で飼い主の注意を引こうとすることがあります。
3. 猫同士の相性の問題
人間と同じように、猫にも個体差があり、それぞれ性格が異なります。活発で遊び好きな猫と、静かで穏やかに過ごしたい猫とでは、ライフスタイルが合わないかもしれません。片方が遊びたくてちょっかいを出しても、もう片方にとっては迷惑でストレスに感じてしまい、威嚇や猫パンチにつながることがあります。
また、年齢差も関係します。好奇心旺盛な子猫と、落ち着いて過ごしたいシニア猫の組み合わせでは、子猫の無邪気な行動がシニア猫の負担になることも少なくありません。
4. 不安やストレスによる攻撃性(転嫁行動)
「転嫁行動」とは、ある対象に対する不満や恐怖を、全く関係のない別の対象に向けて発散させてしまう行動のことです。例えば、窓の外に見知らぬ猫が通りかかって興奮した猫が、たまたま近くにいた同居猫に突然襲いかかるといったケースがこれにあたります。
飼い主から見ると、何の前触れもなく急に喧嘩が始まったように見えますが、実は猫は何らかの外部からの刺激によって強いストレスを感じています。大きな物音、来客、部屋の模様替えなど、環境の変化が引き金になることもあります。
5. 急な環境変化や体調不良
これまで仲良く過ごしていた猫たちの関係が、ある日を境に急に悪化することがあります。その原因として、引っ越しや家具の配置換え、家族構成の変化(赤ちゃんの誕生など)が挙げられます。
また、見過ごされがちですが、体調不良も攻撃性の原因となります。関節炎などの痛みや病気による不快感を抱えている猫は、他の猫が近くに寄ってくるだけで過敏に反応し、威嚇することがあります。急に関係が悪化した場合は、まず動物病院で獣医に相談することが重要です。
これって本気の喧嘩?遊びとの見分け方

猫同士が取っ組み合いをしているとハラハラしますが、本気の喧嘩なのか、じゃれ合っている遊びなのかを見極めることが大切です。むやみに介入すると、かえって関係をこじらせることもあります。
遊びのサイン
猫のプロレスごっこのような遊びには、以下の特徴があります。これらが見られれば、基本的には見守っていて問題ありません。
- 無言か、優しい鳴き声: 唸り声や「シャー」という威嚇音がない。
- 爪を出していない: 猫パンチを繰り出していても、爪はしまわれている。
- 攻守交替がある: 追いかける側と追いかけられる側が入れ替わる。
- 体の力が抜けている: リラックスした様子で、動きがしなやか。
- 終わった後はケロッとしている: 終わるとお互いに毛づくろいをしたり、一緒にくつろいだりする。
本気の喧嘩のサイン
以下のようなサインが見られた場合は、怪我につながる可能性のある本気の喧嘩です。飼い主が適切に介入する必要があります。
- 威嚇音や唸り声: 「シャーッ!」「ウーーッ!」といった低い声や、叫び声が聞こえる。
- 体を大きく見せる行動: 全身の毛を逆立て、背中を丸めて体を大きく見せようとする。
- 耳やヒゲの変化: 耳が横に倒れる「イカ耳」になり、ヒゲが前方に張っている。
- 爪を立てた攻撃: 爪をむき出しにして、本気で引っ掻いたり噛みついたりする。
- 一方的な攻撃: 一方が執拗に相手を追い詰め、もう一方は怯えて逃げようとしている。
本気の喧嘩はエスカレートすると大怪我につながる危険性があります。サインを見極め、早めに仲裁することが重要です。
猫の多頭飼いの喧嘩を解決!仲良く暮らすための3つの重要ポイント

猫たちの関係性を良好に保ち、喧嘩を減らすためには、「環境」「飼い主の対応」「科学的アプローチ」の3つの側面から対策を講じることが効果的です。
ポイント1:環境の最適化 – テリトリーと資源を十分に確保する
猫たちが無用な争いをしなくて済むよう、それぞれが安心して過ごせる環境を整えることが最も重要です。
- トイレの数と配置: 「猫の数+1個」を目安に、複数のトイレを家の別々の場所に設置しましょう。
- 食事と水の場所: ご飯の場所は、それぞれの猫が落ち着いて食べられるよう、少し離れた場所に個別に用意します。お互いの姿が見えないように仕切るのも良い方法です。水飲み場も複数箇所に設置しましょう。
- 寝床と隠れ家: それぞれの猫が誰にも邪魔されずに休める、パーソナルな寝床や隠れ家(段ボール箱やキャットハウスなど)を用意します。
- 上下運動できる環境: キャットタワーやキャットステップを設置し、垂直方向のスペースを増やしましょう。高い場所は猫にとって安心できる避難場所になります。
ポイント2:飼い主の適切な対応とコミュニケーション
飼い主の行動一つで、猫たちの関係性は大きく変わります。公平で一貫した態度を心がけましょう。
- 公平な愛情と先住猫優先の原則: すべての猫に平等に愛情を注ぐことが基本ですが、新入り猫を迎えたばかりの時期は、特に先住猫のケアを優先してください。「あなたの場所は奪われない」という安心感を与えることが大切です。
- 喧嘩の止め方: 本気の喧嘩が始まったら、絶対に直接手を出してはいけません。手を叩いて大きな音を出したり、クッションを間に投げ入れたりして注意をそらしましょう。その後は、それぞれ別の部屋に一時的に分離し、冷静になる時間を与えます。
- ポジティブな関係づくり: 2匹が穏やかに同じ空間にいる時に、同時におやつを与えるなどして、「他の猫と一緒にいると良いことがある」と学習させます。
- 個別のケア時間: ブラッシングやマッサージなど、それぞれの猫と一対一で向き合う時間を意識的に作りましょう。これにより、飼主との絆が深まり、猫の心の安定につながります。
ポイント3:科学的アプローチの活用と専門家への相談
家庭での対策だけでは改善が難しい場合は、科学的なアイテムや専門家の力を借りることも有効です。
- 猫用フェロモン剤の活用: 猫に安心感を与え、ストレスを軽減する効果が期待できる製品です。コンセントに差す拡散タイプなどがあり、緊張関係の緩和に役立ちます。
- 去勢・避妊手術: 未去勢のオスは縄張り意識や攻撃性が強くなる傾向があります。去勢手術は、ホルモンに起因する攻撃性を抑えるのに非常に効果的です。
- 専門家への相談: 対策を試みても改善しない場合は、一人で悩まずに専門家に相談しましょう。まずはかかりつけの動物病院で体調に問題がないか確認し、必要であれば行動診療科のある病院を紹介してもらうとよいでしょう。
新入り猫を迎える際の注意点|喧嘩を未然に防ぐ対面の進め方

これから新しい猫を迎える場合は、最初の対面のさせ方がその後の関係性を大きく左右します。焦らず、段階的に慣らしていくことが喧嘩を未然に防ぐ鍵となります。
- ステップ1:隔離期間を設ける(分離) 新入り猫を家に連れて帰ったら、すぐに先住猫と対面させず、まずは新入り猫専用の部屋で数日〜1週間ほど完全に分離します。この期間は、お互いの匂いがついたタオルなどを交換し、匂いで相手の存在に慣れさせます。
- ステップ2:ケージ越しの対面 お互いが匂いに慣れてきたら、新入り猫をケージに入れた状態で、先住猫と対面させます。最初は短い時間から始め、威嚇せずに落ち着いていられるなら、徐々に時間を延ばします。この時、先住猫におやつを与え、ポジティブな経験と結びつけましょう。
- ステップ3:飼い主の監視下での対面 ケージ越しで問題がなければ、いよいよ直接対面です。必ず飼い主が監督できる状況で、短い時間から始めます。万が一喧嘩になりそうになったら、すぐに引き離せるように準備しておきましょう。常に先住猫の気持ちを優先することが成功の秘訣です。
よくある質問(FAQ)

Q1. 猫の序列争いはいつまで続くのですか?
A. 猫の関係性が安定するまでの期間は、猫たちの性格や相性によって大きく異なり、数週間から数年かかることもあります。完全に仲良しにならなくても、お互いの存在を認め、争いを避ける「共存」という形で落ち着くことも多いです。焦らず、長期的な視点で見守ることが大切です。
Q2. 急に猫同士が仲悪くなったのですが、なぜですか?
A. 家具の配置換えや来客など、些細な環境の変化がストレスになっている可能性があります。また、どちらかの猫が病気や怪我で体調を崩していることも考えられます。まずは両方の猫の健康状態をチェックし、動物病院に相談してください。
Q3. 喧嘩がひどい場合、寝床は別々にしたほうが良いですか?
A. はい、その方が良いでしょう。猫にとって寝床は最も安心できるべき場所です。関係が緊張している状態で無理に一緒に寝かせると、お互いのストレスになります。それぞれの猫が邪魔されずにリラックスして眠れるよう、個別の寝床や隠れ家を用意してあげてください。
まとめ

猫の多頭飼いにおける喧嘩は、単なる序列争いではなく、テリトリー意識、資源の確保、相性、ストレスなど、複数の要因が絡み合って発生します。その背景にある猫の習性を理解し、それぞれの猫が安心して暮らせる環境を整えることが、問題解決への最も重要な鍵となります。
「十分な資源の確保」「飼い主の公平な対応」「焦らない段階的な対面」この3つのポイントを意識し、時には専門家の力も借りながら、愛猫たちのペースに合わせて関係構築をサポートしてあげましょう。時間はかかるかもしれませんが、飼い主の適切なケアと愛情があれば、猫たちはきっと穏やかで平和な暮らしを築いていけるはずです。
- 猫の多頭飼いでの喧嘩は、序列争いではなく、テリトリーや資源の不足、相性、ストレスなど複合的な要因で発生します。
- 喧嘩を解決するには、猫の数に見合った十分な環境(トイレ、食事、隠れ家)を用意することが不可欠です。
- 飼い主はすべての猫に公平な愛情を注ぎ、特に新入り猫を迎える際は先住猫を優先し、段階的な対面を進めるべきです。
- 本気の喧嘩は手を出さずに仲裁し、必要に応じてフェロモン剤の活用や専門家への相談を検討しましょう。
- 長期的な視点で猫たちの関係性を見守り、安心できる環境と適切なケアを通じて、穏やかな共存を目指しましょう。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。