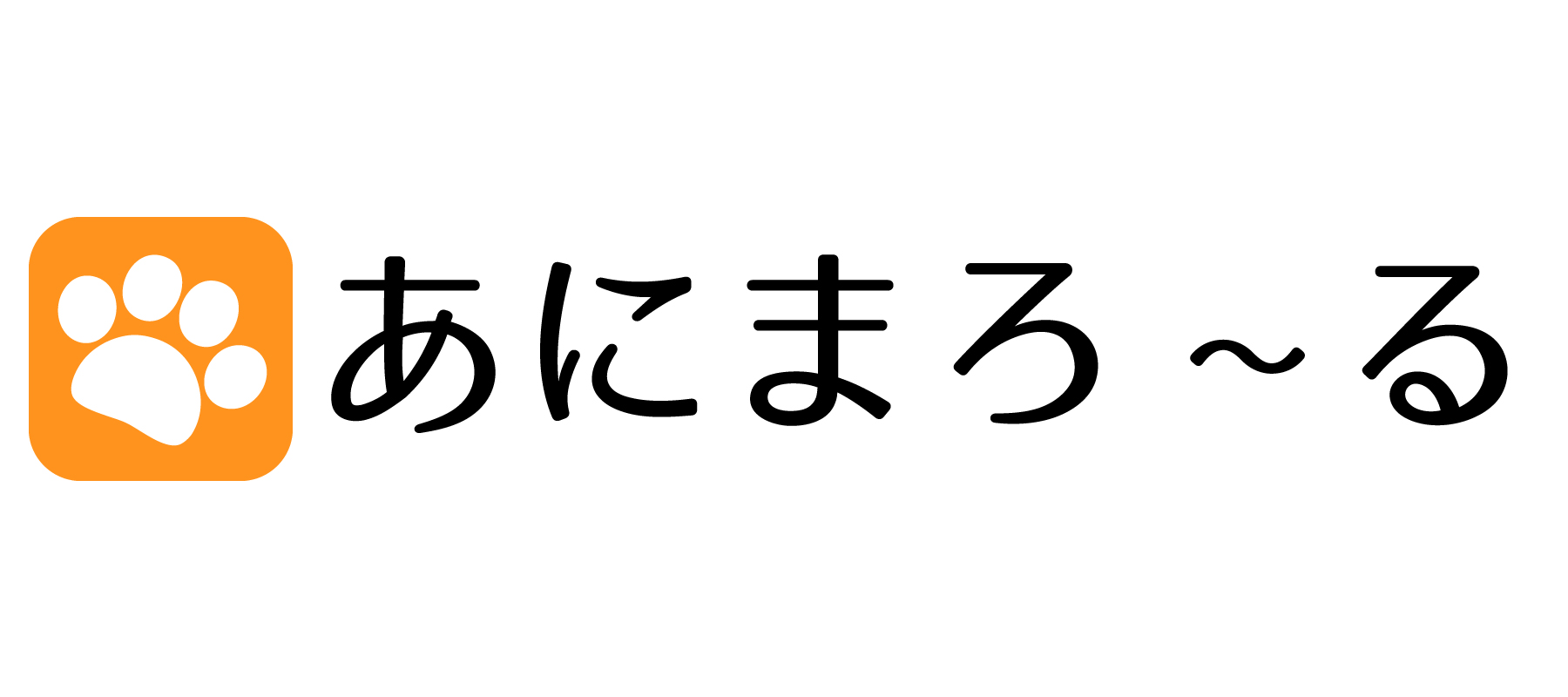深夜に鳴く猫の理由は?夜行性ペットのケアと対策
更新日:2025年11月08日

- 猫の夜泣きの多くは空腹、運動不足、ストレスなどの心理的要因が原因です。
- 高齢猫では認知症や身体の不調が夜泣きを引き起こす可能性もあります。
- 食事回数の見直しや遊び時間の確保、トイレ環境の整備が主な対策です。
- 要求鳴きを無視する、動物病院での相談も効果的な解決策となります。
愛猫が深夜や早朝に大きな声で鳴き続けると、心配になるだけでなく、飼い主自身の睡眠不足にもつながり、心身ともに疲れてしまいますよね。「どうして鳴くのをやめてくれないの?」「何かの病気?」その行動には、猫からの様々なサインが隠されています。
この記事では、猫が深夜に鳴くうるさい夜泣きの原因を子猫・成猫・高齢猫(老猫)のライフステージ別に詳しく解説し、飼主さんが今すぐできる具体的な対策から、やってはいけないNG対応、病気の可能性までを徹底的にご紹介します。
猫は本当に夜行性?猫の睡眠サイクル

一般的に「猫は夜行性」というイメージがありますが、厳密には「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」の動物です。これは、夜明け前や夕暮れ時に獲物となる小動物が活発になるため、その時間帯に狩りをする習性が残っているからです。そのため、人間が寝静まる深夜や早朝に猫の活動がピークになるのは、ごく自然な行動といえます。
しかし、人と暮らす多くの猫は飼い主の生活リズムに合わせてくれます。日中は留守番で寝て過ごし、夜に飼い主が帰宅すると活動的になるパターンも少なくありません。深夜に鳴く行動も、こうした猫本来の習性と現在の生活リズムのズレが一因となっている可能性があります。
猫が深夜や早朝に鳴く主な原因【要求・心理編】

猫が夜中に鳴く理由の多くは、飼い主に対する何らかの「要求」や、心理的な要因が関係しています。まずは、病気以外の一般的な原因から見ていきましょう。
原因①:お腹が空いた(空腹)
猫が深夜や早朝に鳴く最も多い原因の一つが「空腹」です。特に、1日2回の食事スタイルでは、夜ご飯から朝ごはんまでの時間が長く空いてしまい、夜中にお腹を空かせた猫が飼い主を起こして食事を要求することがあります。「この時間に鳴けばご飯がもらえる」と猫が学習し、夜泣きが習慣化するケースも少なくありません。
【対策】 食事の与え方を見直しましょう。1日の食事量は変えずに回数を3〜4回に増やして空腹の時間を短くしたり、就寝前に少量の夜食を与えたりする方法が有効です。また、設定した時間に給餌できる「自動給餌器」の導入も非常に効果的です。飼い主が直接与えずに済むため、「鳴いて要求する」という習慣を断ち切る助けになります。
原因②:構ってほしい・遊びたい(運動不足・退屈)
日中の活動量が少なく、有り余ったエネルギーを発散させたいという欲求から、深夜に鳴いて飼い主の注意を引こうとすることがあります。特に、日中留守番が長い猫は寝て過ごすことが多く、運動不足になりがちです。その結果、飼い主が寝る時間帯に「遊んでほしい」「構ってほしい」という気持ちが高まり、鳴き声でアピールするのです。
【対策】 日中の刺激と運動量を増やすことが鍵です。帰宅後や就寝前に、おもちゃで15分程度、集中的に遊ぶ時間を作りましょう。猫が満足するまで走り回ったりジャンプしたりすることで、適度な疲労感が得られ、夜はぐっすり眠りやすくなります。キャットタワーで上下運動を促したり、知育トイで退屈な時間を減らしたりと、猫が一人でも楽しめる環境を整えることも重要です。
原因③:トイレが汚い・不満がある
猫は非常にきれい好きな動物で、トイレ環境に敏感です。トイレが汚れていたり、砂の種類や設置場所が気に入らなかったりすると、飼い主に知らせるために鳴くことがあります。特に夜間、トイレが汚れてしまうと、次の排泄ができずに不満を訴えるのです。
【対策】 トイレは常に清潔に保つことが基本です。1日に最低2回は掃除し、猫がいつでも気持ちよく使える状態を維持しましょう。トイレの数は「猫の数+1個」が理想です。また、静かで落ち着ける場所にトイレを設置し、猫が好むタイプの砂を選ぶことも大切です。
原因④:不安や寂しい気持ち(ストレス)
猫は環境の変化に敏感で、ストレスを感じやすい生き物です。引っ越しや模様替え、新しい家族が増えた、飼い主の生活リズムが変わったなど、些細な変化が不安や寂しさを引き起こし、夜鳴きの原因になることがあります。飼い主が見えなくなる夜は、特に不安を感じやすくなるのです。
【対策】 まずは猫が安心できる環境を整えることが最優先です。猫が隠れられる場所や、外を眺められる窓辺、高い場所など、お気に入りのパーソナルスペースを確保してあげましょう。飼い主の匂いがついた毛布を寝床に置くのも効果的です。また、猫の気持ちを落ち着かせるフェロモン製剤(フェリウェイなど)を試してみるのも一つの手です。
猫が夜中に鳴く原因【身体的・病気編】

要求や心理的な要因だけでなく、身体的な変化や病気が原因で夜中に鳴くこともあります。特に、鳴き方がいつもと違う、急に始まったという場合は注意が必要です。
発情期による特有の鳴き声
避妊・去勢手術をしていない猫の場合、発情期が夜泣きの原因かもしれません。発情期の鳴き声は、普段とは違う、人間の赤ちゃんが泣くような大きく独特の声で、昼夜を問わず鳴き続けることがあります。これは交尾相手を探す本能的な行動です。
【対策】 発情期の鳴き声をしつけでやめさせることは困難です。最も効果的な対策は、動物病院で避妊・去勢手術を受けることです。手術は望まない妊娠を防ぐだけでなく、発情期のストレスや生殖器系の病気リスクを軽減するメリットもあります。
高齢猫(老猫)の夜泣きと認知症の可能性
猫も高齢になると、人間のように認知機能が低下することがあります。いわゆる「認知症」を発症すると、時間や場所の感覚がわからなくなり、強い不安から夜中に大きな声で鳴き続けることがあります。目的もなくウロウロしながら鳴く、飼い主を認識できないなどの行動は認知症のサインかもしれません。
【対策】 高齢猫の夜泣きに対しては、叱るのではなく、優しく声をかけて撫でるなど、不安を取り除く対応が求められます。夜間も部屋の照明をうっすらとつけておくと、暗闇への恐怖を和らげることができます。症状が気になる場合は、かかりつけの獣医に相談し、適切なケアやサプリメントについてアドバイスをもらいましょう。
体のどこかに痛みや不調がある(病気のサイン)
甲状腺機能亢進症、高血圧、腎臓病、関節炎、脳腫瘍など、様々な病気が夜泣きの原因となることがあります。体のどこかの痛みや不快感を訴えようと鳴いているのかもしれません。特に甲状腺機能亢進症は高齢猫に多く、性格が攻撃的になったり、落ち着きがなくなって鳴き続けたりします。
以下の症状が見られる場合は、病気の可能性が高いと考えられます。すぐに動物病院で診察を受けてください。
- 食欲はあるのに痩せてきた
- 水をたくさん飲む、おしっこの量が増えた
- 元気がない、あまり動かない
- 触られるのを嫌がる
今すぐできる!猫の夜泣きへの具体的な対策8選

原因が分かったら、いよいよ具体的な対策です。愛猫の状況に合わせて、できることから試してみてください。
- 日中の運動量を増やす:就寝前に猫じゃらしなどで思い切り遊び、エネルギーを発散させましょう。15分程度でも集中して遊ぶことがポイントです。
- 食事の時間と回数を見直す:空腹での要求鳴きを防ぐため、食事の回数を増やしたり、タイマー式の自動給餌器を活用したりしましょう。
- トイレ環境を常に清潔に保つ:こまめな掃除を徹底し、トイレの数や場所、砂の種類が愛猫に合っているか見直しましょう。
- 生活リズムを整える:飼い主が規則正しい生活を送ることで、猫の体内時計も安定しやすくなります。
- ストレスの原因を取り除く:キャットタワーや隠れ家を用意し、猫が安心して過ごせるプライベートな空間を確保しましょう。
- 要求鳴きは無視する:「鳴けば要求が通る」と学習させないため、体調に問題がないと判断できる場合は、心を鬼にして無視することも必要なしつけです。鳴きやんだら褒めてあげましょう。
- 寝室の環境を整える:早朝の光を防ぐために遮光カーテンを利用するのが有効です。どうしても眠れない場合は一時的に寝室を分ける選択肢もありますが、猫の性格をよく見極めましょう。
- 病気や高齢化が疑われる場合は獣医に相談:鳴き方がおかしい、他の症状もある場合は、迷わず動物病院を受診してください。専門家への相談が解決への一番の近道です。
これはNG!猫の夜泣きでやってはいけない対応

良かれと思った対応が、問題を悪化させることもあります。以下の行動は絶対に避けましょう。
- 大声で叱る、叩く 猫はなぜ叱られているか理解できず、飼い主への恐怖心や不信感を抱くだけです。ストレスが増し、さらに夜泣きが悪化する可能性があります。
- 要求に応えてすぐにご飯やおやつをあげる これは夜泣きを「成功体験」として学習させてしまう最たるものです。要求鳴きの習慣化に直結するため、絶対やめましょう。
- 飼い主がイライラする 飼い主の不安は敏感な猫に伝わり、猫の不安を煽ってしまいます。難しいことですが、できるだけ冷静に対処することを心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 子猫の夜泣きはいつまで続きますか?
A1: 子猫の夜泣きは、母猫や兄弟と離れた寂しさや新しい環境への不安が主な原因です。通常、新しい家に慣れるまでの数週間から1ヶ月程度で自然と収まることが多いです。安心して眠れるよう、温かい毛布や飼い主の匂いがついたタオルを寝床に入れてあげましょう。
Q2: マンションでの猫の鳴き声、防音対策はありますか?
A2: まずは夜泣きの根本原因への対策が最も重要です。その上で、物理的な対策として、厚手の防音カーテンを設置する、床に防音マットを敷く、夜間は窓をしっかり閉めるなどの工夫が考えられます。近隣への配慮も大切ですが、原因解決が一番の近道です。
Q3: 夜泣きを無視するのはかわいそう…本当に大丈夫?
A3: 要求鳴きを無視するのは、愛情がなくなったわけではなく、望ましくない行動を習慣化させないための「しつけ」の一環です。もちろん、痛みや苦しみを訴えている可能性もあるため、猫の様子をよく観察し、体調不良のサインではないか見極めることが大前提です。その上で要求だと判断できれば、心を強く持って見守ることも必要です。
まとめ

猫が深夜に鳴く背景には、空腹や運動不足といった単純な要求から、ストレス、発情期、さらには病気や認知症といった深刻な問題まで、様々な原因が潜んでいます。大切なのは、愛猫の行動や様子を日頃からよく観察し、「なぜ鳴いているのか?」そのサインを正しく読み取ろうとすることです。
日中の遊びを充実させ、食事やトイレの環境を整えるなど、飼い主が日々の生活の中でできる対策はたくさんあります。この記事で紹介した対処法を参考に、まずは一つずつ試してみてください。それでも改善しない場合や、少しでも体調に異変を感じた際には、ためらわずに動物病院に相談しましょう。飼い主と愛猫が、共に穏やかで快適な夜を過ごせるようになることを心から願っています。
- 猫の夜泣きには空腹、運動不足、ストレス、病気、認知症など多様な原因があります。
- 日中の活動充実、適切な食事・トイレ環境、生活リズムの改善が有効です。
- 要求鳴きを無視するしつけも必要ですが、体調不良のサインは見逃さないでください。
- 解決しない場合や異変を感じる場合は、動物病院への相談が最も確実な方法です。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。