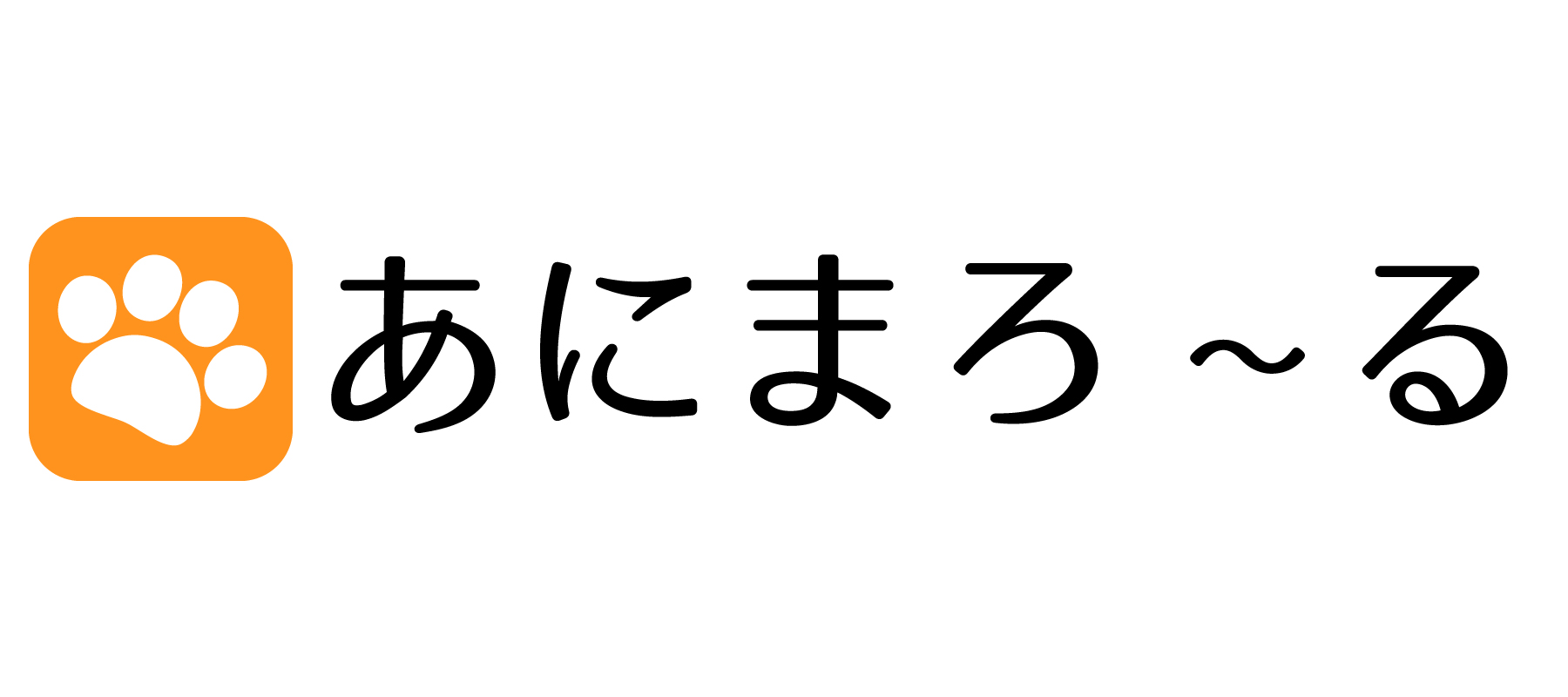【獣医師監修】14歳の老犬ケア完全ガイド|食事・介護・病気の注意点と長生きの秘訣
更新日:2025年11月08日

1分でわかるこの記事の要約
- 14歳の老犬は人間でいう70代。適切なケアでQOL(生活の質)維持が可能です。
- 足腰の衰え、視力・聴力低下、食欲不振、認知機能の変化など、老化サインを早期に発見しましょう。
- 食事は高タンパク質・低脂肪のシニア向けフードを選び、散歩は無理なく短時間で工夫します。
- 滑り止めや段差解消など、バリアフリー化で安全な居住環境を整えましょう。
- 定期的な健康診断と、愛犬の心に寄り添うケアが長生きの秘訣です。

愛犬が14歳を迎え、「最近、足腰が弱くなったかも」「寝ている時間が増えたな」と感じていませんか?犬の14歳は人間で言えば70代以上の高齢期。長年連れ添った家族だからこそ、小さな変化に気づき不安になることもあるでしょう。老化は自然なことですが、適切なケアで愛犬のQOL(生活の質)を維持し、穏やかで快適な毎日をサポートすることは可能です。
この記事では、14歳以上の高齢犬(老犬)と元気に過ごすために、飼い主さんができる食事、運動、介護、環境整備、そして心のケアについて、具体的なポイントを網羅的に解説します。
14歳はどんな時期?見逃したくない老犬の老化サイン

犬の14歳は、犬種によりますが、小型犬ではシニア期の後半、大型犬ではスーパーシニア期にあたります。この時期には、目に見える形で老化のサインが現れ始めます。「歳のせい」と片付けず、愛犬からのメッセージとして受け止め、適切に対応することが重要です。
身体的な変化
- 足腰の衰え: 散歩のスピードが落ちる、段差をためらう、立ち上がりに時間がかかる。関節炎を発症し、特定の足をかばうこともあります。
- 視力・聴力の低下: 目が白く濁る(白内障)、物によくぶつかる。名前を呼んでも反応が鈍い、後ろから近づいても気づかない。
これらの変化は愛犬の不安を増大させます。早期に気づき獣医師に相談することで、痛みの緩和や生活環境の見直しに繋がります。
行動の変化
- 睡眠時間の増加: 一日の大半を寝て過ごすようになります。ただし、ぐったりして元気がない状態が続く場合は病気の可能性も。
- 食欲不振: 代謝が落ち、食の好みが変わったり、硬いものが食べにくくなったりします。歯周病や口内炎が原因のこともあります。
- トイレの失敗: 筋力や認知機能の低下により、粗相が増えることがあります。叱らずに原因を探り、環境を整えることが大切です。
認知機能の変化(犬の認知症)
犬の認知症(認知機能不全症候群)は14歳以上で発症リスクが高まります。
- 夜鳴き: 理由もなく夜中にクーンクーンと鳴き続ける。
- 徘徊(はいかい): 目的もなく部屋の中をぐるぐると歩き回る。
- その他の症状: 飼い主がわからない、狭い場所で動けなくなる、昼夜逆転など。
これらの行動は飼い主さんの負担も大きいですが、病気の一環です。気になる行動が見られたら、まずは動物病院で獣医師に相談しましょう。
高齢犬のQOLを高める食事のケア【ご飯を食べない時】

14歳以上の犬は消化機能や代謝が衰え、歯の問題も抱えがちです。年齢に合わせた食事で健康をサポートしましょう。
高齢犬向けドッグフードの選び方
高齢犬向けドッグフードのポイント
- 基本: 「高タンパク質・低脂肪・低カロリー」が基本です。
- 主原料: 筋肉維持のため、消化しやすい魚や鶏肉などの良質なタンパク質を選びましょう。
- サポート成分: 関節ケアの「グルコサミン・コンドロイチン」、心臓ケアの「タウリン」、抗酸化作用のある「ビタミンE・C」などが含まれていると尚良いです。
- 形状: ドライだけでなく、ウェットフードや療法食も活用。ドライフードはぬるま湯でふやかすと食べやすくなります。
食欲がない時の対処法と工夫
老犬がご飯を食べないと心配になりますが、まずは家庭でできる工夫を試しましょう。
- 香りで刺激: フードを人肌程度に温める。
- トッピング: 茹でたささみや野菜、犬用ふりかけなどを少量加える。
- 食器の高さ調整: 台などを使い、首や足腰に負担のかからない高さに調整する。
食欲不振が続く場合は、歯周病や内臓疾患のサインかもしれません。口内の確認と、早めの動物病院受診が重要です。
水分補給とサプリメントの活用
高齢犬は喉の渇きを感じにくく、脱水になりがちです。いつでも新鮮な水が飲めるようにし、ウェットフードやスープなどで食事からも水分を摂れるように工夫しましょう。
また、関節や認知機能などをサポートするサプリメントも有効ですが、必ず事前に獣医師に相談し、愛犬に合ったものを適切な量で与えてください。
無理なく続ける!14歳からの運動・散歩のポイント

14歳以上の老犬にとって、運動は筋力維持や気分転換に欠かせません。「無理をさせない」ことを大前提に、愛犬のペースに合わせて続けましょう。
高齢犬に最適な散歩の時間と距離
散歩の時間や距離に決まりはありません。その日の体調を最優先し、1回10分~15分程度の短い散歩を複数回に分けるなどの工夫が有効です。真夏は涼しい早朝や夜に、冬は暖かい日中に行くなど、気候への配慮も大切です。
足腰が弱ってきた犬への散歩サポート
歩行がおぼつかなくても、散歩で外の刺激を感じることは大切です。
- 歩行補助ハーネス: 飼い主が体重を支え、ふらつきや転倒を防ぎます。特に後ろ足が弱い子に効果的です。
- コース選び: 坂道や階段を避け、足に優しい芝生や土の上など平坦な道を選びましょう。
- 休憩: 疲れた様子なら無理せず、一緒に休憩しましょう。
室内でできる簡単な運動とマッサージ
散歩に行けない日は、室内で心と体を刺激しましょう。
- ノーズワーク: おやつを隠して匂いで探させる遊び。体への負担が少なく、脳を活性化させます。
- マッサージ: 優しく体を撫で、筋肉を揉みほぐすことで血行を促進し、リラックス効果も期待できます。体を触ることは、しこりなどの早期発見にも繋がります。
安全で快適な暮らしのための環境整備(バリアフリー化)

筋力や視力が衰えた老犬にとって、家の中も危険な場所になり得ます。怪我のリスクを減らし、安心して過ごせるよう環境を見直しましょう。
バリアフリー化のポイント
- 滑り止め対策: フローリングは非常に滑りやすく、足腰に負担をかけます。愛犬がよく通る場所には、滑り止めマットやカーペットを敷きましょう。
- 段差の解消: ソファやベッドにはペット用のスロープやステップを設置し、飛び乗り・飛び降りによる怪我を防ぎます。
- 危険な場所への対策: 階段やストーブ周りにはペットゲートを設置し、立ち入りを制限しましょう。
- 快適な寝床: 睡眠時間が長くなるため、体圧を分散できる低反発ベッドや床ずれ予防マットがおすすめです。静かで家族の気配が感じられる場所に設置しましょう。
- トイレ環境の見直し: トイレの失敗は叱らず、数を増やしたり、寝床の近くに設置したりして対応します。段差の低いトレーに変えるのも有効です。寝たきりの場合はおむつをこまめに交換し、体を清潔に保ちましょう。
心のケアと飼い主の役割|介護ストレスと向き合う

高齢犬のケアは、身体的なサポートだけでなく、不安を和らげる「心のケア」が非常に重要です。
コミュニケーションとスキンシップを大切に
目や耳が不自由になると、犬は不安を感じやすくなります。優しい声かけやマッサージなど、意識的に触れ合う時間を増やし、「いつもそばにいるよ」と伝えてあげましょう。飼い主の匂いや温もりは、何よりの安心材料です。
認知症の症状と向き合う方法
夜鳴きや徘徊は飼い主さんにとっても大きなストレスですが、まずは怪我をしない環境を整えましょう。昼間に適度な刺激を与えて昼夜逆転のリズムを整える、獣医師に相談してサプリや薬を処方してもらうなどの対処法があります。一人で抱え込まず、専門家を頼りましょう。
飼い主自身のストレスケア
老犬介護は精神的・肉体的に大きな負担がかかります。「完璧な介護」を目指さず、「できる範囲で精一杯やっている」とご自身を認めてあげてください。家族と役割を分担したり、ペットシッターや老犬ホームの一時預かりなどを利用したりして、休息時間を確保することも重要です。飼い主さんが笑顔でいることが、愛犬にとって一番の安心に繋がります。
知っておきたい高齢期の病気と医療ケア

14歳は様々な病気のリスクが高まる時期です。かかりやすい病気を知り、定期的な健康診断で早期発見に努めましょう。
高齢犬がかかりやすい代表的な病気
代表的な病気と症状
- 心臓病: 咳が増える、疲れやすくなる。
- 腎臓病: 水を飲む量や尿の量が増える(多飲多尿)。
- 関節炎: 歩き方がおかしい、触ると痛がる。
- 歯周病: 口臭、歯のぐらつき。全身の病気に繋がることも。
- 腫瘍(がん): 体にしこりができる、急に元気がなくなる。
「いつもと違う」と感じたら、すぐに動物病院を受診してください。
定期的な健康診断のすすめ
症状が出にくい病気の早期発見のため、半年に1回程度の健康診断が推奨されます。血液検査やエコー検査などで、目に見えない体の変化をチェックすることが大切です。かかりつけの獣医師に普段の様子を知ってもらうことも、いざという時の助けになります。
終末期医療(ターミナルケア)について考える
いつか訪れるお別れの時、愛犬にどんな最期を迎えさせてあげたいか、事前に考えておくことも大切です。延命治療を望むのか、苦痛を取り除く緩和ケアを中心にするのか。正解はありません。「この子にとって何が一番幸せか」を基準に、元気なうちから家族や獣医師と話し合っておきましょう。
まとめ

14歳以上の高齢犬との暮らしは、これまで以上にきめ細やかなケアが求められます。戸惑うことも多いかもしれませんが、長年連れ添った愛犬との時間はかけがえのない宝物です。
完璧を目指すのではなく、愛犬のペースに合わせて、できることから始めてみましょう。そして、飼い主さん一人で抱え込まず、獣医師や専門家の力も借りてください。深い愛情と正しいケアで、愛犬との残された貴重な時間を、一日一日大切に過ごしていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 14歳の老犬が急にご飯を食べなくなりました。どうすればいいですか?
A1: まず口の中に痛みがないか確認し、フードを温めたりトッピングを試したりしてください。それでも数日食べない、元気がない、嘔吐するなどの症状があれば、病気の可能性があります。できるだけ早く動物病院を受診してください。
Q2: 高齢犬の夜鳴きがひどく、近所への迷惑も心配です。何か対策はありますか?
A2: 夜鳴きは認知症や体の痛み、不安など様々な原因が考えられます。まずは獣医師に相談し、原因を探ることが大切です。生活リズムの改善やサプリ・薬の使用で改善する場合もあります。飼い主さんがそばにいて安心させてあげることも効果的です。
Q3: 老犬の介護に精神的に疲れてしまいました。どうしたらいいですか?
A3: 介護疲れは当然のことで、ご自身を責めないでください。飼い主さんが倒れないことが一番です。完璧を目指さず、家族と協力したり、ペットシッターや老犬ホームの一時預かりサービスを利用したりして、意識的に休息を取りましょう。飼い主さんのリフレッシュが、愛犬へのより良いケアに繋がります。
この記事のまとめ
- 14歳以上の高齢犬には、きめ細やかな食事、運動、介護、環境整備が必要です。
- 老化サインを見逃さず、早期に獣医師に相談し、痛みの緩和やQOL維持に努めましょう。
- 飼い主自身のストレスケアも重要であり、完璧を目指さず、周囲のサポートを頼ることが大切です。
- 定期的な健康診断で病気を早期発見し、終末期医療についても家族で話し合いましょう。
- 深い愛情と適切なケアで、愛犬との残された貴重な時間を豊かに過ごしていきましょう。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。