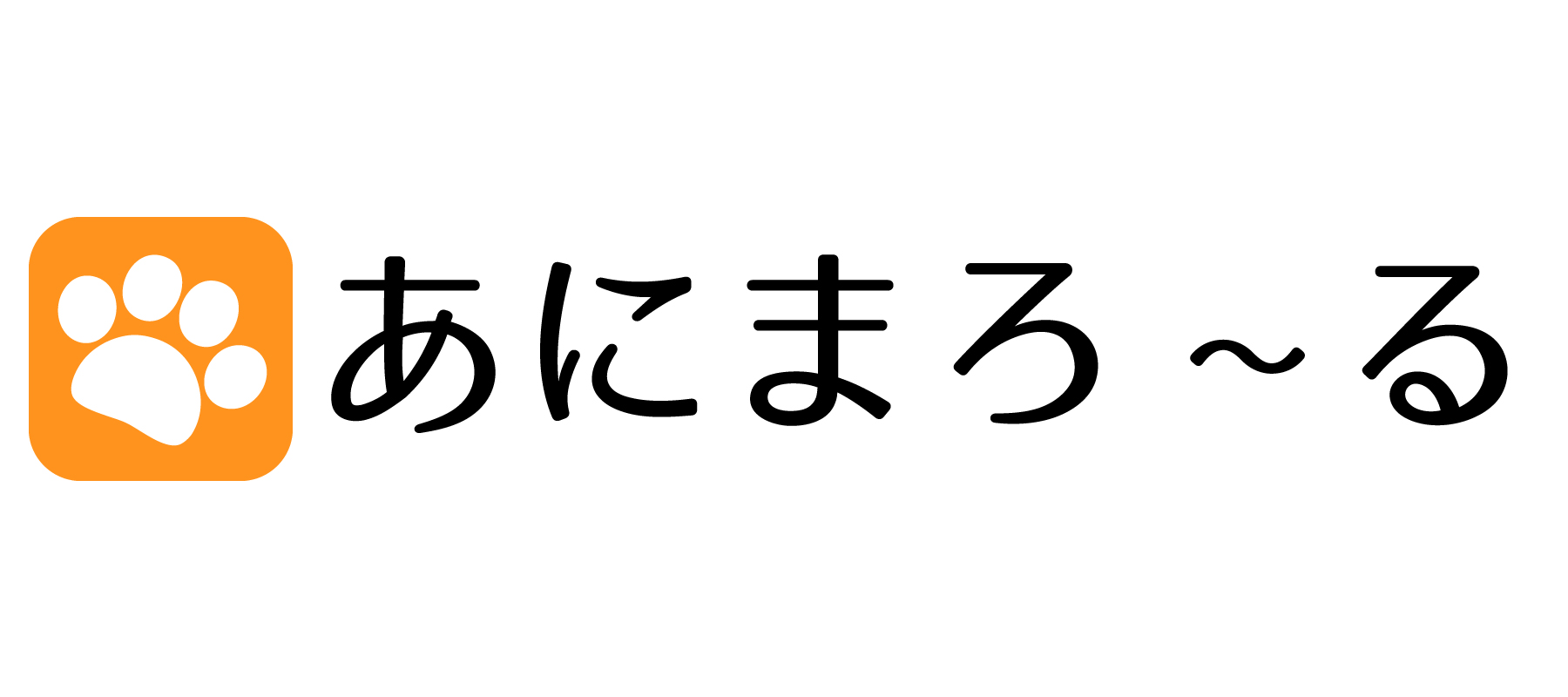高齢ペットのための食事&運動ガイド:シニア期の犬猫ケア
更新日:2025年11月08日

- シニア期のペットケアはQOL向上に不可欠であり、早期の老化サイン察知が健康寿命を延ばす鍵となります。
- 食事管理では低カロリーで良質なタンパク質を含むフードを選び、適切な栄養バランスで体重を維持しましょう。
- 適度な運動は筋力維持、肥満・ストレス・認知症予防に繋がり、ペットのペースに合わせた工夫が重要です。
- 定期的な健康チェックと快適な環境整備、そして獣医師との連携がシニアペットの穏やかな生活を支えます。
シニア期とは?犬と猫の老化のサインを見逃さない

ペットの老化は緩やかに進行するため、日々の生活の中では気づきにくいものです。しかし、早期にサインを察知し、適切なケアを始めることが健康寿命を延ばす鍵となります。まずは、犬と猫が何歳からシニア期に入るのか、そしてどのような変化が現れるのかを理解しましょう。
犬と猫は何歳からシニア期(高齢期)?
一般的に、ペットのシニア期は7歳頃から始まると言われています。ただし、これはあくまで目安であり、犬種や猫種、個体差によって異なります。
- 犬の場合:体の大きさによってシニア期に入る年齢が変わります。小型犬や中型犬は7〜10歳頃から、大型犬は体の負担が大きいため5〜7歳頃から老化のサインが見られ始めます。
- 猫の場合:犬種ほどの大きな差はなく、おおよそ7歳頃からシニア期、11歳を超えると高齢期、15歳以上は老齢期と分類されることが多いです。
大切なのは年齢の数字だけでなく、日々の様子を観察し、個々のペースに合わせたケアに切り替えていくことです。
見逃したくない老化のサイン一覧
シニア期に入ると、ペットには様々な心身の変化が現れます。これらの老化現象は、病気のサインである可能性も秘めているため、見逃さないように注意深く観察しましょう。
身体的な変化
- 被毛に白髪が増える、毛艶がなくなる
- 目が白っぽく濁る(白内障の可能性)
- 口臭が強くなる(歯周病のサイン)
- 歩き方がおぼつかなくなる、段差を嫌がる(関節炎の可能性)
- 体重の増減が激しい
- イボやしこりができる
特に歯周病は多くのシニアペットが抱える問題で、放置すると食欲不振や全身の病気に繋がるため注意が必要です。
行動の変化
- 寝ている時間が格段に増えた
- 食欲にムラがある、あるいは食欲不振になった
- トイレの失敗が増える
- 名前を呼んでも反応が鈍い(聴力の低下)
- 夜中に意味なく鳴き続ける(認知症の可能性)
- 狭い場所に入りたがる、ぐるぐる回る
少しでも気になる変化があれば、自己判断せず、かかりつけの獣医師に相談することが重要です。
高齢ペットの食事管理:シニア犬・老猫の栄養とフード選び

シニア期のケアにおいて、食事管理は最も重要な要素の一つです。若い頃と同じ食事を続けていると、肥満や内臓への負担、栄養不足などを引き起こす可能性があります。ペットの年齢や健康状態に合わせた食事に切り替え、健康を内側からサポートしましょう。
シニア期の食事で重要な栄養バランスとは?
高齢になると、運動量の低下に伴い基礎代謝が落ちるため、成犬・成猫期と同じ量の食事では太りやすくなります。肥満は関節や心臓に大きな負担をかけるため、体重管理は非常に重要です。
シニア向けのペットフードは、低カロリーでありながら、筋力維持に必要な良質なタンパク質を豊富に含むように設計されています。また、消化機能も衰えるため、消化に優しく、吸収しやすい原材料が使われているフードを選びましょう。
さらに、関節の健康をサポートするグルコサミンやコンドロイチン、皮膚や被毛の健康を保つオメガ3脂肪酸など、シニア期に特有の悩みに配慮した栄養素が配合されているものが理想的です。
高齢犬(シニア犬)の食事選びのポイント
シニア犬向けのドッグフードに切り替える際は、急に変えるのではなく、今まで食べていたフードに新しいフードを少量混ぜ、1〜2週間かけて徐々に割合を増やしていくと、胃腸への負担を減らせます。
噛む力や飲み込む力が弱くなっている場合は、ドライフードをお湯でふやかす、またはウェットフードを活用するのがおすすめです。食事と一緒に水分補給もできます。
食事の量は、フードのパッケージに記載されている給与量を目安にしつつ、ペットの体重や体型(ボディコンディションスコア)を見ながら調整することが大切です。
高齢猫(老猫)の食事で特に気をつけたいこと
猫は元々、腎臓病や心臓病になりやすい動物です。特に高齢猫ではそのリスクが高まるため、リンやナトリウムの含有量が調整されたシニア向けキャットフードを選ぶことが推奨されます。
また、猫は脱水や泌尿器系のトラブルを起こしやすいため、水分補給は非常に重要です。ウェットフードを取り入れたり、水飲み場を複数箇所に設置したり、給水器を導入したりするなどの工夫をしましょう。
食欲不振が見られる場合は、フードを人肌程度に温めて香りを立たせたり、好みのトッピングを少量加えたりすると食べてくれることがあります。それでも食べない場合は病気の可能性も考えられるため、早めに動物病院を受診してください。
病気や症状に合わせた療法食とサプリメントの活用

シニア期になると、慢性的な病気を抱えるペットも増えてきます。そのような場合は、獣医師の指導のもとで療法食やサプリメントを上手に活用することが、症状の緩和やQOLの維持に繋がります。
獣医師に相談すべき「療法食」とは?
療法食とは、特定の病気や健康状態に合わせて栄養バランスが特別に調整された食事のことです。例えば、腎臓病のペットにはタンパク質やリンを制限したもの、心臓病にはナトリウムを控えたものなど、様々な種類があります。
重要なのは、療法食は飼い主の自己判断で与えるべきではないということです。症状に合わない療法食は、かえって健康を損なう危険性があります。必ず獣医師の診断と処方に従って、ペットの状態に最適なものを選びましょう。
健康維持をサポートするサプリメントの選び方
加齢による体の衰えをサポートするためにサプリメントを取り入れるのも有効です。関節の動きを滑らかにするグルコサミンやコンドロイチン、認知機能の維持を助けるDHA・EPA、腸内環境を整えるプロバイオティクスなどがあります。
ただし、サプリメントも過剰摂取は禁物です。また、薬との飲み合わせに注意が必要なこともあります。サプリメントを始める前にも、必ずかかりつけの獣医師に相談し、ペットに合ったものを推奨してもらうようにしましょう。
シニア期の運動と筋力維持:無理なく続けるコツ

「年だから」と運動をさせないと、筋力はますます低下し、寝たきりのリスクを高めます。適度な運動は、筋力維持、肥満予防、ストレス軽減、認知症の予防にも繋がります。ペットの体に負担をかけない範囲で、毎日の生活に運動を取り入れましょう。
なぜ運動が重要?高齢ペットの筋力維持とストレス軽減
シニア期は活動量が減り、筋肉が少しずつ落ちていきます。特に後ろ足の筋力が衰えると、歩行が困難になりQOLが著しく低下します。適度な運動は、この筋力の低下を緩やかにするために不可欠です。
また、外の空気を吸ったり、匂いを嗅いだりすることは、ペットにとって大きな喜びであり、精神的な満足感を与えます。老化の進行を穏やかにし、いきいきとしたシニアライフを送るために、運動は食事と同じくらい大切なのです。
シニア犬の散歩と室内運動のポイント
シニア犬の散歩は、時間や距離よりも犬自身のペースを優先しましょう。短い距離をゆっくり歩くだけでも十分な運動になります。関節炎を患っている場合は、アスファルトよりも土や芝生の上など、足腰への負担が少ない場所がおすすめです。
天候が悪い日は、室内でできる簡単な運動を取り入れましょう。おやつを隠して探させる「ノーズワーク」は、足腰に負担をかけずに脳を刺激できるため、シニア犬にぴったりの遊びです。マッサージやストレッチも血行促進やリラックスに繋がります。
シニア猫の運動不足を解消する工夫
室内飼いの猫は、高齢になるとさらに運動不足になりがちです。猫が自発的に少しでも動きたくなるような環境を整えてあげることが大切です。
例えば、キャットタワーの段差を低くしたり、スロープを設置したりして、安全に上り下りできるように工夫しましょう。また、鳥の羽がついたおもちゃやレーザーポインターなどを短時間使って、狩猟本能をくすぐるのも良い方法です。遊びを強要せず、少しでも体を動かす機会を作ることが筋力維持に繋がります。
自宅でできる!シニアペットの健康チェックと快適な環境づくり

日々のケアを丁寧に行うことで、病気の早期発見・早期治療に繋げることができます。また、生活環境を少し見直すだけで、高齢ペットの身体的な負担を大きく軽減できます。
毎日の健康チェックリスト
毎日ペットと触れ合う時間に、以下の項目をさりげなく確認する習慣をつけましょう。
- 体重:定期的に測定し、急な増減がないか確認
- 食欲と飲水量:いつもと比べて量に変化はないか
- おしっことうんち:色、量、回数、状態は正常か
- 歩き方:ふらつき、足を引きずるなどの異常はないか
- 目、耳、鼻、口:目やに、耳の汚れ、鼻水、口臭や歯茎の色はどうか
- 体全体を触る:しこりや痛みがないか、被毛の状態はどうか
これらのチェックを習慣にすることで、異常の早期発見に繋がります。
高齢ペットが安心して暮らせる快適な環境とは
筋力や視力が低下した高齢ペットにとって、住み慣れた家も危険な場所になり得ます。
- 床:フローリングなどの滑りやすい床には、カーペットや滑り止めのマットを敷く。
- 段差:ソファやベッドへの上り下りには、ペット用のスロープやステップを設置する。
- 寝床:体圧を分散してくれる低反発のマットなどを用意し、床ずれを予防する。
- トイレ:寝床の近くにも設置したり、入り口の段差が低いものに変えたりする。
老犬・老猫の介護と介護用品の活用
もしペットが寝たきりになった場合、床ずれ(褥瘡)の予防が最も重要です。2〜3時間おきに体の向きを変える「体位変換」を行いましょう。
食事や排泄の補助には、体を支える食器や、おむつ、ペットシーツ、歩行補助ハーネスなどの介護用品を活用することで、ペットと飼い主双方の負担を軽減できます。
高齢ペットによくある悩みと対策(Q&A)

Q1. 15歳の犬が食事を食べないのですが、どうすればいいですか?
- A1: 高齢犬の食欲不振は、歯周病などの口の痛み、内臓疾患、認知症など様々な原因が考えられます。まずは動物病院で診察を受け、病気が隠れていないか確認することが最優先です。病的な問題がない場合、フードを人肌に温める、ウェットフードを混ぜる、手から与えるなどを試してみてください。
Q2. 老猫が夜鳴きをするのは認知症でしょうか?
- A2: 老猫の夜鳴きは認知症の可能性もありますが、体の痛み、視力や聴力の低下による不安、空腹など他の原因も考えられます。まずは生活環境を見直し、猫が不快に感じていないか確認しましょう。夜鳴きが続く場合は、痛みの緩和や不安を和らげる治療について獣医師に相談できます。
Q3. シニアペットの健康診断はどのくらいの頻度で行うべきですか?
- A3: シニア期(7歳以上)に入ったら、特に症状がなくても半年に1回の健康診断が推奨されます。病気は初期症状が出にくいため、定期的な血液検査や画像検査によって早期発見・早期治療に繋げることができます。
まとめ:愛情あるケアで、穏やかなシニアライフを

高齢ペットのケアで最も大切なことは、日々の小さな変化に気づき、愛情を持って優しく寄り添うことです。シニア期は様々な課題に直面する時期ですが、飼い主の適切なサポートがあれば、ペットは穏やかで快適な生活を送ることができます。
- 食事管理
- 無理のない運動
- 安全で快適な環境づくり
- 日々の健康チェック
これらを基本に、ペット一人ひとりの状態に合わせてケアを調整していくことが、QOLと健康寿命を延バスことに繋がります。
愛するペットとの時間は、何にも代えがたい宝物です。決して一人で悩まず、かかりつけの獣医師という心強いパートナーと相談しながら、これからの時間をより豊かで幸せなものにしていきましょう。
- シニア期のペットは、適切な食事、運動、環境整備、健康チェックでQOLと健康寿命を維持できます。
- 老化のサインを早期に察知し、体調や個体差に合わせた柔軟なケアが非常に重要となります。
- 療法食やサプリメントの活用、介護用品の導入は獣医師と相談しながら慎重に進めましょう。
- 大切なペットとの時間を豊かにするため、日々の観察と愛情深いサポートを継続しましょう。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。