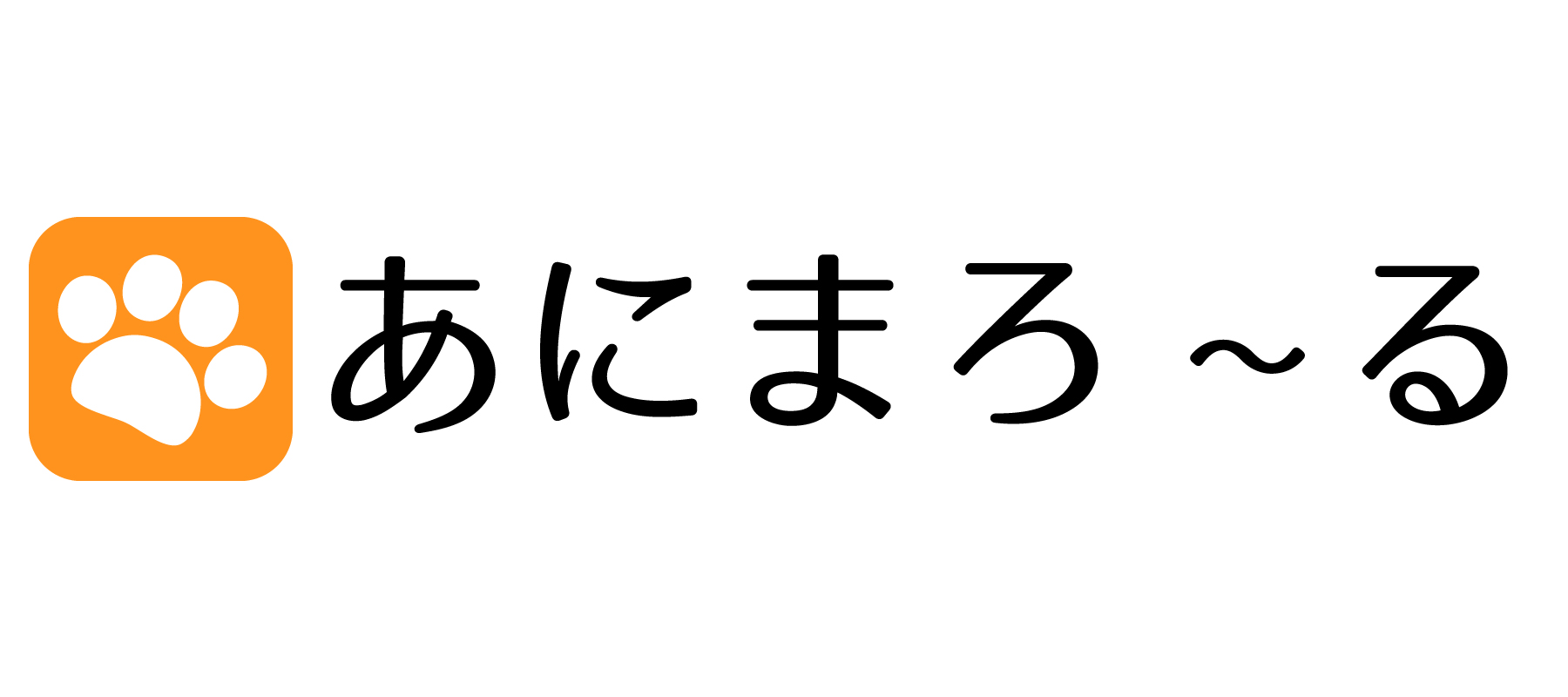伊勢海老は飼育できる?必要なものや気を付ける点などについて解説
更新日:2025年03月05日
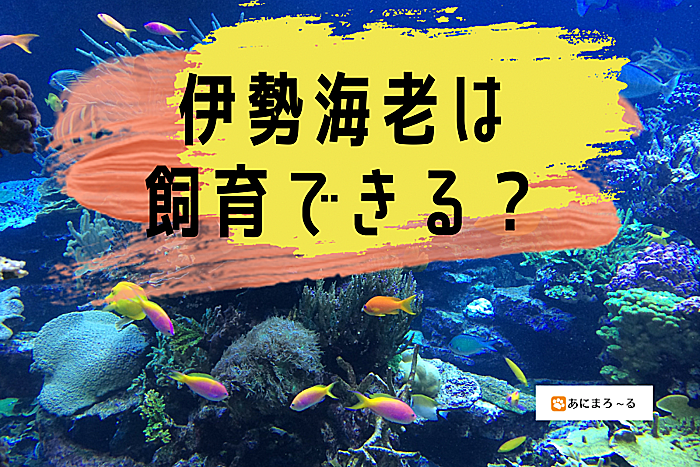
飼育には、ろ過能力が非常に高いオーバーフロー水槽が最適です。しかし、オーバーフロー水槽を立ち上げるには、専用の水槽や水槽を乗せる台、配管などの特殊な機材が必要になります。そのため、初期費用は約200,000~300,000円と高額になる場合が多いでしょう。
ほかにも、飼育中は水道代や電気代、餌代が必要です。ひと月の維持費用は、およそ2,000~4,000円を見越しておくとよいでしょう。
ほかにも、飼育中は水道代や電気代、餌代が必要です。ひと月の維持費用は、およそ2,000~4,000円を見越しておくとよいでしょう。
伊勢海老の飼育で気を付けること
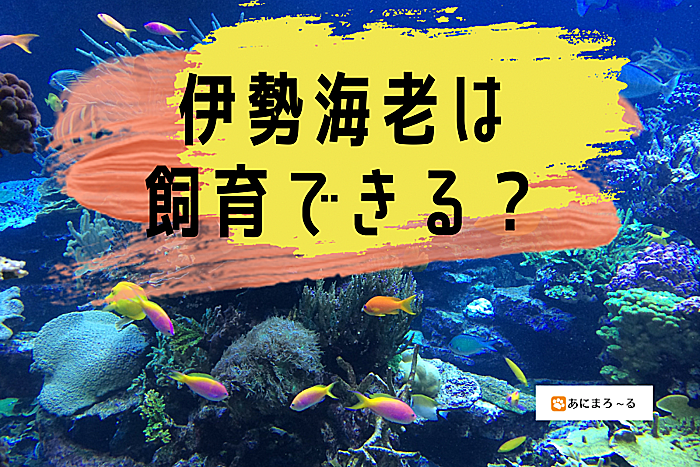
伊勢海老を初めて飼育するときや飼育中の伊勢海老が弱っている場合は、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。ここからは、伊勢海老の飼育における4つの注意点をくわしく解説します。
水質に注意する
伊勢海老は、環境の変化を感じ取りやすい生き物です。そのため、飼育するときは、伊勢海老が住んでいた海の水質に合わせた環境を用意するとよいでしょう。
水槽に入れる水は、海水の比重や塩分濃度に注意してアルカリ性を保つようにします。床材にサンゴ砂を使用すれば、水質はアルカリ性に傾きやすくなるでしょう。
水槽内を安定した水質に保つには、数か月程度かかる場合があります。そのため、飼育前から水槽内の環境を整えておくことが重要です。水質が安定したら、水替えは1年に1回程度でよいといわれています。
水槽に入れる水は、海水の比重や塩分濃度に注意してアルカリ性を保つようにします。床材にサンゴ砂を使用すれば、水質はアルカリ性に傾きやすくなるでしょう。
水槽内を安定した水質に保つには、数か月程度かかる場合があります。そのため、飼育前から水槽内の環境を整えておくことが重要です。水質が安定したら、水替えは1年に1回程度でよいといわれています。
水温に注意する
伊勢海老の飼育に最適な水温は、22~25℃程度です。必要に応じて水槽用のヒーターやクーラーを使い、水温を一定に保ちましょう。ただし、これらを使用するときは時間をかけて行い、水槽内に急激な温度変化が起こらないよう注意が必要です。
脱皮期間に注意する
伊勢海老は、1年に2回程度の回数で脱皮します。脱皮期間中は、水槽の水替えや触れることはできるだけ避けましょう。脱皮後の殻を食べることもありますが、しばらく残っているなら回収しても大丈夫です。
一方で、伊勢海老の死因の1つに脱皮不全があげられます。脱皮不全とは、脱皮したはずの殻が体の一部に残ってしまう脱皮の失敗です。
飼育されている伊勢海老は、環境の変化により脱皮の回数が増える場合があります。脱皮不全のリスクを避けるには、脱皮の回数を増やさないように、水質や水温を一定に保つことが大切です。
一方で、伊勢海老の死因の1つに脱皮不全があげられます。脱皮不全とは、脱皮したはずの殻が体の一部に残ってしまう脱皮の失敗です。
飼育されている伊勢海老は、環境の変化により脱皮の回数が増える場合があります。脱皮不全のリスクを避けるには、脱皮の回数を増やさないように、水質や水温を一定に保つことが大切です。
給餌頻度と量に注意する
給餌頻度は、3~4日に1回程度が目安です。餌の与えすぎは、水質の悪化につながるため注意しましょう。
伊勢海老は肉食性で、貝類や魚の切り身、海藻類など幅広い餌を食べます。特に生きたままの餌を好むため、まずは活アサリを与えてみるとよいでしょう。ほかにも、釣りの餌として使用されるオキアミやイソメ、サンマやサバの切り身などもおすすめです。
伊勢海老は肉食性で、貝類や魚の切り身、海藻類など幅広い餌を食べます。特に生きたままの餌を好むため、まずは活アサリを与えてみるとよいでしょう。ほかにも、釣りの餌として使用されるオキアミやイソメ、サンマやサバの切り身などもおすすめです。
伊勢海老は環境を整えれば自宅でも飼育できる

伊勢海老は大きい体とはうらはらに、環境の変化に弱い生物です。自宅で飼育するときは、水槽の水質や水温管理に気を付けて最適な環境を保ちましょう。
伊勢海老の迫力ある姿を直接見られるのは、飼育ならではの醍醐味です。難しいようにみえる飼育も、注意点を意識すれば問題ないでしょう。飼育環境を整えて、伊勢海老の魅力を自宅で存分に味わってください。
伊勢海老の迫力ある姿を直接見られるのは、飼育ならではの醍醐味です。難しいようにみえる飼育も、注意点を意識すれば問題ないでしょう。飼育環境を整えて、伊勢海老の魅力を自宅で存分に味わってください。
初回公開日:2022年08月04日
記載されている内容は2022年08月04日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。