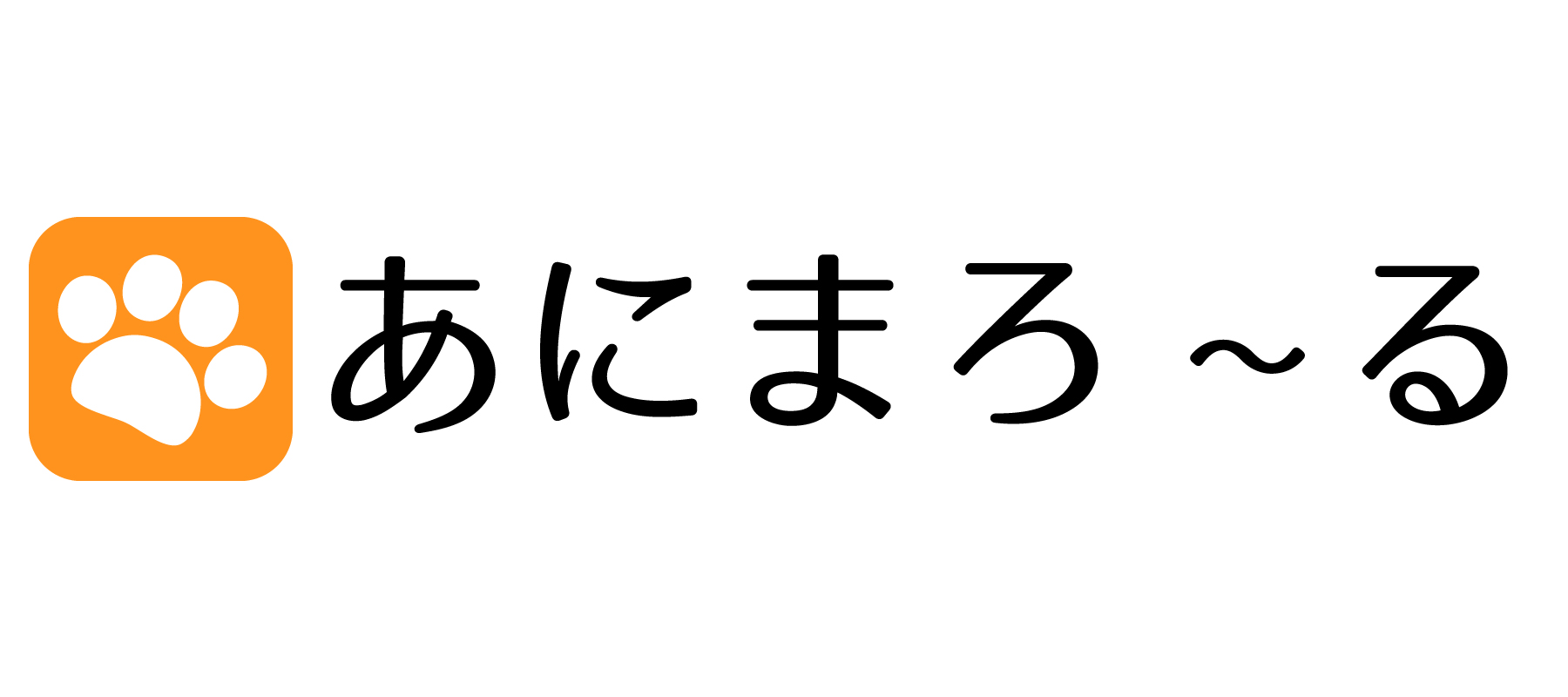【初心者向け】爬虫類の飼育ガイド|トカゲ・カメ・ヘビの難易度・費用・法律を比較
更新日:2025年11月08日

- 爬虫類は鳴き声や臭いが少なく、アレルギー持ちの方でも飼育しやすい魅力的なペットです。
- トカゲ、カメ、ヘビそれぞれに初心者向けの種類があり、飼育難易度や必要な設備が異なります。
- 飼育費用は初期で約4万〜10万円、月々2千〜8千円が目安で、種類によって変動します。
- ほとんどの種類は許可不要ですが、「特定動物」は許可が必要なため、事前確認が重要です。
- 温度・湿度管理や特殊な餌、専門病院の少なさなど、飼育前の注意点も理解し準備しましょう。
爬虫類をペットにする魅力とは?メリット・デメリット

まず、爬虫類をペットとして迎えることの魅力と、知っておくべき注意点を解説します。
爬虫類飼育の4つのメリット
爬虫類飼育のメリット
- 多くの爬虫類は鳴き声がなく非常に静かで、マンションやアパートでも近隣を気にせず飼育できます。体臭もほとんどなく、ケージ内を清潔に保てば部屋の臭いも気になりません。鳴かない・臭わないペットを探している方におすすめです。
- 犬や猫の毛やフケと違い、爬虫類には毛がないため、動物アレルギーを持つ人でも飼育しやすいのが特徴です。家族にアレルギー体質の方がいても、ペットとの暮らしを実現できる可能性があります。
- 多くの爬虫類はケージ内で生涯を過ごすため、広い飼育スペースを必要としません。一人暮らしの部屋でも、ケージを置くスペースさえ確保できれば飼育が可能です。
- 感情表現が分かりにくいと思われがちですが、長く一緒に暮らすと飼い主を認識し、餌をねだったり手に乗ったりと、種によってはコミュニケーションがとれます。その奥ゆかしい姿が多くの飼い主を魅了しています。
爬虫類飼育の4つのデメリットと注意点
爬虫類飼育のデメリットと注意点
- 爬虫類は自分で体温調節ができない変温動物です。そのため、ヒーターやライトを使い、種類ごとに適した温度・湿度を一年中維持する必要があります。これは爬虫類飼育で最も重要なポイントです。
- 種類によって、コオロギなどの昆虫や冷凍マウスといった餌が必要です。虫やネズミが苦手な人にはハードルが高いかもしれません。もちろん人工飼料で飼育できる種類もいますが、餌の準備と管理は事前に必ず確認しましょう。
- 爬虫類は体調不良を隠す習性があり、病気の発見が遅れがちです。さらに、爬虫類を専門的に診てくれる動物病院はまだ多くありません。飼う前に、近隣のエキゾチックアニマル対応病院を探しておくことが非常に重要です。
- 爬虫類はわずかな隙間から脱走することがあります。特にヘビは脱走の名人です。ケージには必ず鍵をかける、隙間をなくすなどの対策が不可欠です。万が一脱走した場合、大きな問題になる可能性もあるため管理を徹底しましょう。
【種類別】初心者におすすめの爬虫類|トカゲ・カメ・ヘビ飼育難易度比較

それでは、具体的にトカゲ・カメ・ヘビ、それぞれの飼育難易度や特徴を比較します。初心者におすすめの人気種も合わせて紹介します。
| 種類 | 飼育難易度(5段階) | 初期費用 | 月々の維持費 | コミュニケーション |
|---|---|---|---|---|
| トカゲ | ★★☆☆☆~★★★★☆ | 中~高 | 中~高 | 比較的取りやすい |
| カメ | ★★☆☆☆~★★★☆☆ | 中 | 低~中 | 種による |
| ヘビ | ★☆☆☆☆~★★★☆☆ | 低~中 | 低 | 控えめ |
トカゲの飼育難易度と特徴
トカゲは種類が非常に多く、大きさや性格も様々。活発に動き回る姿を観察したい人に向いています。
初心者におすすめのトカゲ①:ヒョウモントカゲモドキ
「レオパ」の愛称で親しまれ、爬虫類ペット入門の代表格です。小型で性格も温和な個体が多く、ハンドリング(手に乗せること)も楽しめます。夜行性のため強い紫外線ライトが不要な点も、飼いやすさの理由です。餌は昆虫が主ですが、近年は栄養バランスの取れた人工飼料も普及しています。
初心者におすすめのトカゲ②:フトアゴヒゲトカゲ
人によく慣れ、「ペットリザード」として絶大な人気を誇ります。昼行性で、バスキング(日光浴)をする姿は非常に愛らしいです。レオパよりは大きくなるため、広めのケージと紫外線ライト・バスキングライトが必須。雑食性で昆虫の他に野菜も食べます。飼育環境を整えれば、コミュニケーションが取りやすく満足度の高い種類です。
カメの飼育難易度と特徴
カメは長寿で、ゆっくりとした動きが魅力です。数十年という長い付き合いになることを覚悟して迎えましょう。
初心者におすすめのリクガメ:ヘルマンリクガメ
リクガメの中では比較的丈夫で飼育しやすく、性格も穏やか。最大20cm程度と家庭でも飼いやすいサイズです。草食性で、小松菜などの野菜やリクガメフードが主食。健康な甲羅の成長のため、強い紫外線ライトが不可欠です。寿命が非常に長いことを理解し、生涯飼育できるかよく考えましょう。
初心者におすすめのミズガメ:ニオイガメ
大きな水槽が不要で、省スペースで飼育を始めたい方におすすめの小型ミズガメです。水中ヒーターとろ過フィルターを設置した水槽で飼育できます。非常に丈夫で病気に強く、人工飼料もよく食べるため管理が楽です。ただし、危険を感じると臭いを出すことがあります。
ヘビの飼育難易度と特徴
独特の見た目とは裏腹に、実は飼育しやすい種類が多いのがヘビの魅力。給餌頻度が少なく、静かで場所も取らないため、忙しい人や一人暮らしにもおすすめです。
初心者におすすめのヘビ①:コーンスネーク
「最も飼いやすいヘビ」として世界中で愛されています。性格が非常に温和でハンドリングも容易。カラーバリエーションが豊富なため、自分好みの個体を選ぶ楽しみもあります。餌は冷凍マウスを週に1回程度与えればOK。脱走対策は必須ですが、基本的な設備と温度管理を怠らなければ、初心者でも安心して飼育できます。
初心者におすすめのヘビ②:ボールパイソン
コーンスネークと並んで人気のヘビ。驚くとボールのように丸くなる臆病で大人しい性格です。最大でも150cm程度と比較的コンパクト。餌は冷凍マウスで、給餌間隔はコーンスネークよりさらに長くても問題ありません。ただし、環境の変化に敏感で拒食することがあるため、落ち着いた環境作りが大切です。
爬虫類の飼育費用を徹底解説!初期費用と月々の維持費

次に、爬虫類の飼育にかかる具体的な費用を見ていきましょう。
飼育を始めるための初期費用(約4万円~10万円)
初期費用は「生体価格」と「飼育設備」の合計です。
生体価格:数千円~数十万円
ヒョウモントカゲモドキやコーンスネークのノーマル個体なら5,000円~15,000円程度。珍しい品種(モルフ)は数十万円することもあります。
飼育設備一式:30,000円~70,000円程度
- ケージ:10,000円~30,000円
- 保温器具(パネルヒーター、保温球など):5,000円~10,000円
- 照明器具(紫外線ライト、バスキングライトなど):5,000円~15,000円
- 温度計・湿度計:2,000円~5,000円
- その他(床材、水入れ、シェルターなど):3,000円~10,000円
初心者向けの種類であれば、総額で40,000円~100,000円程度を見積もっておくと安心です。必要なものが揃った「飼育スタートセット」を利用するのも良いでしょう。
月々の維持費(約2,000円~8,000円)
毎月かかる費用は主に餌代と電気代です。
- 餌代:1,000円~5,000円 成長期や、昆虫と野菜を食べるフトアゴヒゲトカゲなどは高くなる傾向があります。給餌頻度の少ないヘビは安く抑えられます。
- 電気代:1,000円~4,000円 保温・照明器具を稼働させるための費用です。特に冬場は高くなります。
- 消耗品代:月平均500円~1,000円 床材や交換用ライトの費用も考慮しておきましょう。
種類別の費用比較
初期費用・維持費ともに、フトアゴヒゲトカゲのように広いケージや高出力のライトが必要な種類は高くなる傾向にあります。一方、ヒョウモントカゲモドキやコーンスネークは費用を抑えやすいと言えるでしょう。
【知らないと危険】爬虫類飼育に関する法律と許可

爬虫類の飼育には法律が関わってきます。トラブルを避けるため、基本的なルールを理解しておきましょう。
ほとんどの種類は許可不要
ペットショップで一般的に販売されているヒョウモントカゲモドキ、フトアゴヒゲトカゲ、コーンスネークなどを家庭で飼育する場合、特別な許可は必要ありません。
「特定動物」の飼育には許可が必要
人の生命や身体に害を加えるおそれがある動物は「特定動物」に指定されており、飼育には都道府県知事などの許可が必要です。ワニガメ、ドクトカゲ、一部の大型ヘビなどが該当します。許可基準は非常に厳しく、初心者が安易に手を出すべきではありません。飼いたい種類が該当しないか、購入前に環境省のリストで必ず確認しましょう。
その他の法律と注意点
- 特定外来生物:日本の生態系に影響を与えるとして指定された生物は、飼育や運搬が原則禁止されています。
- 遺棄の禁止:飼えなくなったペットを野外に放すことは絶対に許されません。法律で罰せられるだけでなく、生態系を破壊する原因になります。最後まで責任を持って飼育しましょう。
初心者が爬虫類飼育を始めるための準備と選び方

最後に、実際に爬虫類を迎えるための具体的な準備と、健康な個体の選び方を解説します。
必要な飼育設備の選び方
飼育設備のポイント
- ケージ: 成長後も使えるサイズを選び、脱走防止に鍵がかけられるものが理想です。
- 保温器具: ケージ全体を暖めるパネルヒーターと、局所的に高温部を作るバスキングライトを組み合わせるのが基本。サーモスタットで温度を自動管理すると非常に便利です。
- 照明: 昼行性のトカゲやリクガメには、骨の形成を助ける紫外線ライトが必須です。
- 床材: 種類によって最適なものが異なります。誤飲の危険がなく、掃除しやすいものを選びましょう。
餌の種類と準備
餌は主に活餌・冷凍餌・人工飼料の3種類。最初はペットショップで与えられていた餌と同じものを準備すると、スムーズに餌付いてくれます。
健康な個体の選び方と購入場所
健康な個体のチェックポイント
- 購入は、知識豊富なスタッフがいる爬虫類専門店が初心者にはおすすめです。
- 目がぱっちりと開いているか
- 痩せすぎていないか(骨が浮き出ていないか)
- 口や鼻の周りが汚れていないか
- 皮膚にダニや傷がないか
- 活発に動いているか(夜行性の種類は除く)
可能であれば、餌を食べる様子を見せてもらうとより安心です。
まとめ

爬虫類の飼育は、犬や猫とは違う奥深い魅力に満ちています。
- トカゲ:活発な姿を楽しみたい人向け
- カメ:長寿で、じっくり付き合いたい人向け
- ヘビ:省スペースで手間が少なく、忙しい人向け
それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルや予算に合わせて、最高のパートナーを見つけてください。準備を万全に整え、あなただけの爬虫類ライフを始めましょう。
- 爬虫類は静かで臭いが少なく、アレルギーのリスクが低い点が魅力的なペットです。
- トカゲ、カメ、ヘビそれぞれに初心者向けの種類があり、飼育難易度や必要な設備が異なります。
- 初期費用は約4万〜10万円、月々の維持費は2千〜8千円が目安ですが、種類によって幅があります。
- 「特定動物」以外の一般的な爬虫類に飼育許可は不要ですが、脱走防止や遺棄禁止は厳守しましょう。
- 温度・湿度管理、特殊な餌の準備、専門病院の確保など、飼育前の綿密な準備が成功の鍵です。
よくある質問(FAQ)
Q1: 一人暮らしでも爬虫類は飼えますか?
A1: はい、飼育可能です。鳴き声や臭いが少なく、散歩も不要なため、爬虫類は一人暮らしの方に非常に向いています。ただし、年間を通した温度管理のため、エアコンやヒーターを適切に使用できる環境が必須です。
Q2: 爬虫類の臭いや鳴き声は気になりますか?
A2: ほとんどの爬虫類は鳴きません。臭いも生体自体にはほとんどなく、ケージ内のフンなどをこまめに掃除していれば気になることは稀です。清潔な環境を保つことが大切です。
Q3: 病気になったらどこに連れて行けばいいですか?
A3: 爬虫類を診察できる動物病院は限られています。飼育を始める前に、自宅の近くに爬虫類対応(エキゾチックアニマル)の動物病院があるか必ず調べておきましょう。事前にリストアップしておくと、いざという時に安心です。
Q4: 旅行などで家を空けるときはどうすればいいですか?
A4: 1~2泊程度なら、出かける前に餌と水を与え、タイマーで照明やヒーターを管理すれば問題ない場合が多いです。長期の場合は、エキゾチックアニマル対応のペットホテルに預けるか、飼育経験者に世話を頼む必要があります。
Q5: 爬虫類の寿命はどのくらいですか?
A5: 種類によって大きく異なりますが、一般的に長寿です。ヒョウモントカゲモドキで10~15年、コーンスネークは15~20年、リクガメは数十年生きることもあります。飼う前にその種の平均寿命を調べ、生涯にわたって責任を持てるか考えることが非常に重要です。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。