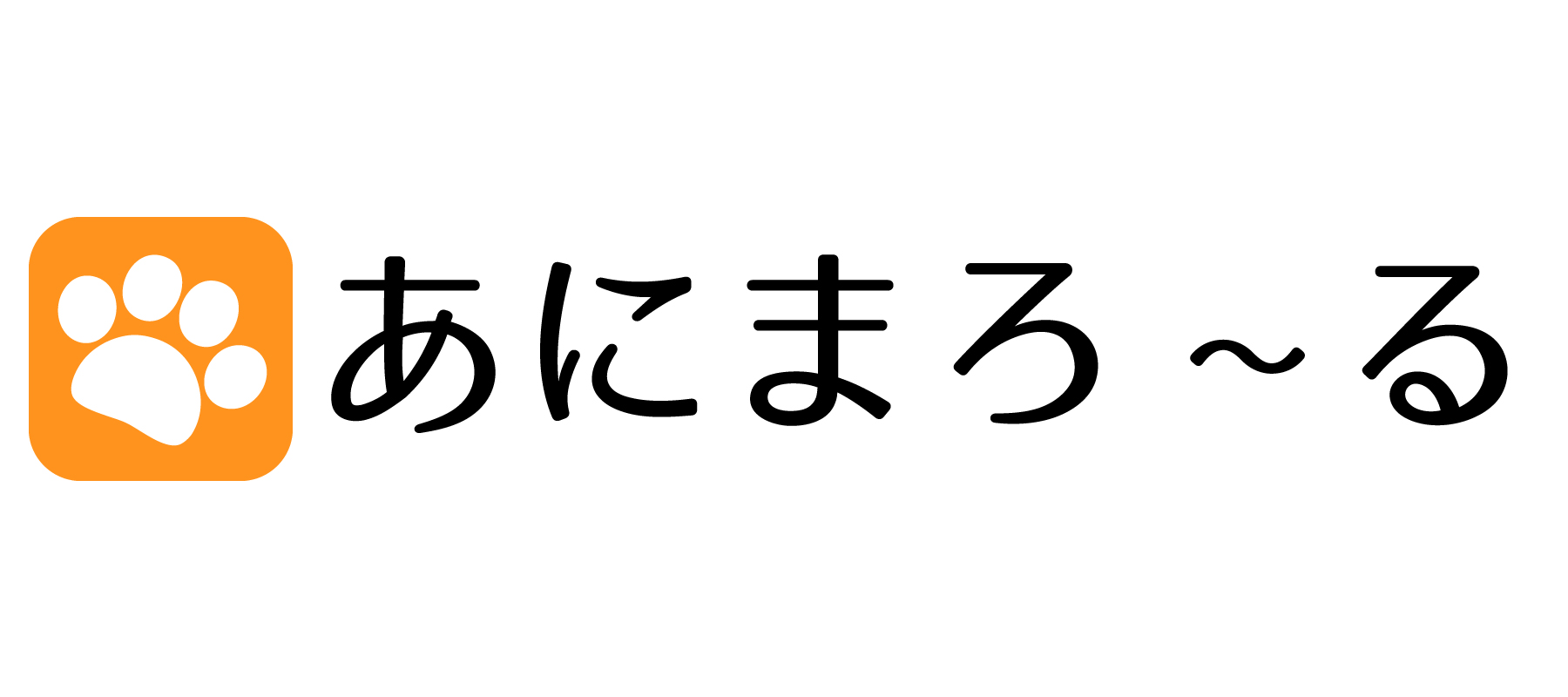爬虫類をペットに迎える前に知っておきたい5つのポイント
更新日:2025年11月08日

- 爬虫類飼育には、動物愛護管理法や特定動物規制などの法律知識と「終生飼養」の責任が伴うことを理解しましょう。
- 種類ごとの適切な温度・湿度・UVBライトといった飼育環境の完璧な準備が、生命維持と健康の鍵となります。
- 食性に応じた正しい餌やり、適切な給餌頻度、そして常に新鮮な水を提供し栄養と水分を管理しましょう。
- 予想以上に長い寿命(15~50年以上)と、初期費用・ランニングコスト・高額になる医療費を事前に考慮し計画を立てることが重要です。
- 万が一の病気や怪我に備え、飼い始める前に爬虫類を診察できるエキゾチックアニマル専門病院を必ず見つけておきましょう。
ポイント1:爬虫類飼育に関わる法律と規制
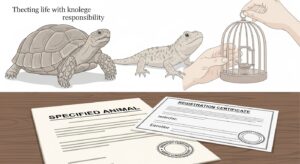
爬虫類をペットとして飼う上で、最初に理解すべきなのが法律の知識です。可愛い、珍しいという理由だけで飼い始めると、知らず知らずのうちに法律違反を犯す可能性があります。飼育を検討する前に、関連法規をしっかり確認しましょう。
動物愛護管理法と終生飼養の責任
爬虫類も犬や猫と同様に「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の対象です。この法律は、動物の虐待や遺棄を禁止し、飼い主にはペットが命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任を定めています。一度飼い始めたら、最後まで責任を持つという強い心構えが必要です。飼えなくなったからと野外に放すことは、生態系を破壊するだけでなく、法律で固く禁じられています。
特定動物(危険な動物)の飼育許可
爬虫類の中には、人の生命や身体に害を加える恐れがあるとして「特定動物」に指定されている種がいます。例えば、ワニ類、オオトカゲの一部、大型のヘビ(ボア・ニシキヘビなど)が該当します。これらの特定動物を飼育するには、都道府県知事等の許可が必須です。許可には、脱走を防ぐ極めて頑丈なケージの設置やマイクロチップによる個体識別など、厳しい基準をクリアしなければなりません。初心者が安易に手を出すべき領域ではありません。
外来生物法と種の保存法
海外から輸入される爬虫類も多いため、「外来生物法」や「種の保存法」も知っておく必要があります。これらの法律により、輸入や国内での飼育、譲渡が規制されている種がいます。特に、ワシントン条約で保護されている希少種は、正規の証明書がなければ売買も飼育もできません。購入時は必ず信頼できる専門店を選び、個体の由来が確かかを確認することが、違法取引に加担しないために重要です。
ポイント2:【最重要】種類に合わせた飼育環境の準備

爬虫類飼育で最も重要なのが、それぞれの種類に合った飼育環境を整えることです。生息地が砂漠、熱帯雨林など多岐にわたるため、必要な温度・湿度、照明が全く異なります。飼いたい種類が決まったら、まずその生態を詳しく調べ、完璧な環境を準備してから生体を迎えましょう。
爬虫類飼育に必要な基本セット
まず、どのような爬虫類でも基本となる飼育用品を事前に揃えましょう。
基本の飼育用品
- ケージ:生体の大きさや生態に合ったサイズと形状。脱走防止のため、鍵付きが理想。
- 床材:ペットシーツ、砂、ウッドチップなど。種類や清掃のしやすさ、誤飲の危険がないかを考慮。
- 照明器具:体内リズムを整えるライト、体を温めるバスキングライト、骨の形成に必要なUVBライトなど。
- 保温器具:パネルヒーターや保温球など、ケージ内の温度を適切に保つ。
- 温度計・湿度計:ケージ内の環境を正確に把握するために必須。
- 水入れ・餌入れ:倒れにくく安定したものを選ぶ。
- シェルター:隠れて安心できる場所。ストレス軽減に役立つ。
最重要!適切な温度と湿度の管理
爬虫類は自分で体温を調節できない変温動物です。そのため、飼育環境の温度管理が生命維持の鍵となります。ケージ内には、バスキングライトで局所的に温める「ホットスポット」と、涼しい「クールスポット」を作り、温度勾配を設けるのが基本です。これにより、爬虫類自身が移動して体温調節できます。また、湿度も種類により適切な数値が大きく異なるため、霧吹きや加湿器で管理が必要です。温度や湿度が不適切だと、食欲不振や脱皮不全、呼吸器系の病気など、様々な健康問題を引き起こします。
照明の役割と正しい選び方
特にトカゲなどの昼行性の爬虫類にとって、照明は単なる明かりではありません。太陽光に含まれる紫外線(UVB)は、体内でビタミンD3を合成し、カルシウムを吸収するために不可欠です。UVBが不足すると、骨が変形・脆弱化する「代謝性骨疾患(くる病)」という深刻な病気になるリスクが高まります。専用のUVBライトを設置し、定期的に交換しましょう。一方、ヒョウモントカゲモドキのような夜行性の種類には強いUVBは不要ですが、昼夜のリズムを作るために照明は有効です。
ポイント3:餌の種類と正しい与え方

爬虫類の食性は、肉食、昆虫食、草食、雑食と様々です。飼育する種類が何を食べるのかを正確に把握し、栄養バランスの取れた餌を適切な頻度で与えることが健康管理の基本です。
肉食・昆虫食の爬虫類の餌
多くのトカゲやヘビは昆虫や小型哺乳類を食べます。主な餌はコオロギ、デュビア等の生き餌や、冷凍マウス・ラットです。これらの餌を自宅で管理することに抵抗がないか、飼う前に家族にも確認しておくことが重要です。昆虫を餌にする場合、栄養価を高めるために昆虫自身に栄養ある餌を与えておく「ガットローディング」が推奨されます。また、栄養補助として、餌にカルシウム剤等を振りかける「ダスティング」も、健康な骨格維持に欠かせません。
草食・雑食の爬虫類の餌
リクガメやグリーンイグアナなどの草食性爬虫類には、小松菜やチンゲンサイといったカルシウム豊富な葉野菜を中心に与えます。ほうれん草などシュウ酸を多く含む野菜は、カルシウム吸収を阻害するため避けましょう。最近では栄養バランスが考慮された専用の人工フードも市販されており、野菜と組み合わせて与えるのが一般的です。
給餌の頻度と水やりの重要性
給餌頻度は、種類、年齢、大きさで異なります。成長期の若い個体は毎日、成体では週に1〜2回で十分な場合もあります。食べ残しはすぐに片付け、ケージ内を清潔に保ちましょう。また、新鮮な水をいつでも飲めるようにしておくことも非常に重要です。水入れの水は毎日交換し、容器も定期的に清掃してください。
ポイント4:覚悟が必要!爬虫類の寿命と生涯かかる費用

「生体価格が安いから」という理由で安易に飼い始めるのは危険です。初期費用や維持費、そして何より彼らの長い寿命を考慮する必要があります。
爬虫類の寿命は意外と長い
爬虫類の寿命は想像以上に長く、飼い主より長生きする可能性もあります。例えば、初心者に人気のヒョウモントカゲモドキで15〜20年、ボールパイソンで20〜30年、リクガメは50年以上生きることも珍しくありません。ご自身のライフプランと照らし合わせ、最後まで飼い続けられるか真剣に考える必要があります。
初期費用と月々のランニングコスト
飼育開始には初期費用がかかります。生体代のほか、ケージや照明などの飼育設備一式で、安くても数万円、こだわれば十数万円以上になることも。月々のランニングコストは、餌代、消耗品(床材、UVBライト等)、そして温度管理のための電気代です。これらで毎月数千円から1万円程度かかると考えておきましょう。
忘れてはならない医療費という備え
万が一の病気やケガに備えた医療費も必要です。爬虫類を診察できる動物病院は専門性が高く、治療費が高額になる傾向があります。ペット保険も対象外が多いため、急な出費に備えてペット用の貯金をしておくと賢明です。
ポイント5:【飼う前に】爬虫類を診てくれる動物病院の探し方

爬虫類も病気やケガをします。その際、専門知識を持つ獣医の存在が不可欠です。しかし、犬猫中心の病院では爬虫類の診察を断られることが少なくありません。
なぜ専門病院(エキゾチックアニマル)が必要か
爬虫類の体は哺乳類と構造が大きく異なり、診断と治療には専門知識が不可欠です。そのため、爬虫類や鳥類などを専門に診る「エキゾチックアニマル」対応の病院でなければ、適切な治療を受けられない可能性が高いのです。
飼い始める前に必ず病院を探しておく
最大の注意点は、「飼い始めてから」ではなく、「飼い始める前」に通える範囲に専門病院があるか確認しておくことです。いざという時に慌てて探してもすぐには見つかりません。「(地域名) 爬虫類 病院」などで検索し、複数の病院をリストアップしておきましょう。夜間や休日の救急対応の有無も確認しておくと、より安心です。
日頃の健康管理と病気のサイン
最高の治療は予防です。毎日ペットをよく観察し、以下のようなサインがないかチェックしましょう。
- 食欲がない、全く食べない
- 元気がない、ぐったりしている
- 口を不自然に開けている、呼吸が苦しそう
- 脱皮不全(古い皮が体に残っている)
- 便の状態がいつもと違う(下痢など)
- 体に腫れや傷がある
これらの異変に気づいたら、自己判断せず、速やかに専門の獣医に相談することが重要です。
まとめ:後悔しないために。爬虫類と豊かに暮らす準備

この記事では、爬虫類をペットとして迎える前に知っておきたい5つのポイントを解説しました。
- 法律を理解し、終生飼養の責任を持つ。
- 種類に合った飼育環境(特に温度・湿度)を完璧に準備する。
- 正しい餌を適切な方法で与え、栄養管理を徹底する。
- 長い寿命と生涯かかる費用を覚悟し、計画を立てる。
- 飼育開始前に、必ず通える専門病院を見つけておく。
爬虫類の飼育は手間も責任も伴いますが、そのユニークな生態を間近で観察できる喜びは格別です。十分な知識と準備、そして深い愛情を持って迎えれば、彼らはあなたの人生を豊かにしてくれる素晴らしいパートナーとなるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 初心者におすすめの爬虫類は何ですか?
A1. 比較的飼育がしやすく情報も豊富な、トカゲなら「ヒョウモントカゲモドキ」「フトアゴヒゲトカゲ」、ヘビなら「コーンスネーク」などが人気です。ヒョウモントカゲモドキは小型で温和、フトアゴヒゲトカゲは人懐っこい個体が多く、コーンスネークは性格が大人しくカラーが豊富です。
Q2. 一人暮らしでも爬虫類は飼えますか?
A2. はい、可能です。鳴き声で近隣に迷惑をかけることがなく、散歩も不要なため一人暮らしに向いています。ただし、温度管理のための電気設備は常に稼働させる必要があり、停電対策も考えておくと安心です。また、旅行などで長期不在にする際の預け先(友人やペットホテル)を事前に見つけておく必要があります。
Q3. 爬虫類を飼うデメリットはありますか?
A3. いくつか考えられます。①餌が昆虫や冷凍マウスなど、人によっては抵抗がある場合がある。②適切な温度・湿度維持のため電気代が常にかかる。③診てくれる専門病院が少なく、遠方まで行く必要があるかもしれない。④犬猫のような感情表現が分かりにくく、コミュニケーションを求める方には物足りない可能性がある。⑤脱走のリスクも常に念頭に置く必要があります。
- 爬虫類を飼育する際は、動物愛護管理法や特定動物規制など、必ず関連法律を確認し「終生飼養」の責任を持ちましょう。
- 飼育する種類ごとに、温度・湿度・UVBライト等の最適な飼育環境を事前に完璧に整えることが健康維持の基本です。
- 適切な餌の種類と給餌方法、毎日新鮮な水を提供することで、栄養と水分の管理を徹底し病気を防ぎましょう。
- 爬虫類は寿命が長く、初期費用・ランニングコスト・医療費が高額になるため、ライフプランと合わせて計画的な飼育が不可欠です。
- 万一の事態に備え、飼い始める前に爬虫類を診察できるエキゾチックアニマル専門の動物病院を必ず探しておきましょう。
初回公開日:2025年11月08日
記載されている内容は2025年11月08日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。